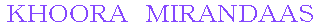|
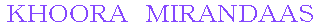
  Mysterium Naturale Mysterium Naturale 自然の神秘主義 自然の神秘主義 
 [Mysteria Mirandae] [LINK] 「MN#1: 霧の神秘主義―Mist」 [Mysteria Mirandae] [LINK] 「MN#1: 霧の神秘主義―Mist」 |
 [Mysteria Mirandae] [LINK] 「MN#2: 炎の神秘主義―Flame, Fire」 [Mysteria Mirandae] [LINK] 「MN#2: 炎の神秘主義―Flame, Fire」 |
 [Mysteria Mirandae] [LINK] 「MN#3: 風の神秘主義―Ventus, Wind」 [Mysteria Mirandae] [LINK] 「MN#3: 風の神秘主義―Ventus, Wind」 |
 [Mysteria Mirandae] [LINK] 「MN#4: 石の瞑想―Lapis」 [Mysteria Mirandae] [LINK] 「MN#4: 石の瞑想―Lapis」 |
|
 [Mysteria Mirandae] [LINK] 「MN#5: 樹木の霊―Arbor」 Partie I [Mysteria Mirandae] [LINK] 「MN#5: 樹木の霊―Arbor」 Partie I |
 [Mysteria Mirandae] [LINK] 「MN#5: 樹木の霊―Arbor」 Partie II [Mysteria Mirandae] [LINK] 「MN#5: 樹木の霊―Arbor」 Partie II |
 [Mysteria Mirandae] [LINK] 「MN#6: 森の神秘―Silva」 [Mysteria Mirandae] [LINK] 「MN#6: 森の神秘―Silva」 |
 [Mysteria Mirandae] [LINK] 「MN#7: 光・光明―Lumen, Lux」 [Mysteria Mirandae] [LINK] 「MN#7: 光・光明―Lumen, Lux」 |
 [ROOM] Outline of the Gnosticism [ROOM] Outline of the Gnosticism |
 グノーシス主義概説 グノーシス主義概説 |
 [ROOM] Mysticism and Gnosis [ROOM] Mysticism and Gnosis |
 神秘主義とグノーシス主義 神秘主義とグノーシス主義 |
 [ROOM] Mysticism and Gnosis II [ROOM] Mysticism and Gnosis II |
 神秘主義とグノーシス主義 II 神秘主義とグノーシス主義 II |
 [ROOM] Mysticism and Gnosis III [ROOM] Mysticism and Gnosis III |
 神秘主義とグノーシス主義 III 神秘主義とグノーシス主義 III |
 [ROOM] Mysticism and Gnosis IV [ROOM] Mysticism and Gnosis IV |
 神秘主義とグノーシス主義 IV 神秘主義とグノーシス主義 IV |
 [ROOM] Mysticism and Gnosis V [ROOM] Mysticism and Gnosis V |
 神秘主義とグノーシス主義 V 神秘主義とグノーシス主義 V |
 [ROOM] Mysticism and Gnosis VI [ROOM] Mysticism and Gnosis VI |
 神秘主義とグノーシス主義 VI 神秘主義とグノーシス主義 VI |
 [ROOM] Mysticism and Gnosis VII [ROOM] Mysticism and Gnosis VII |
 神秘主義とグノーシス主義 VII 神秘主義とグノーシス主義 VII |
|
[LIST] [HOME] [END] [THOUGHTS] [LITERARY] [MISCELLAN] [INFOR]
  [Mysteria Mirandae] [TOP] [Mysteria Mirandae] [TOP]
Mysterium Naturale # 1
Mysterium Nebulae
『霧の神秘主義』
|
さて、以下において、シリーズの形で、「自然界」の諸現象が、私たち人間の心に喚起する「想像力の神秘主義」、いわば、「深層意識の起動」としての神秘主義について、随想的に短く、記してみたいと思います。その最初のものとして、「Mysterium Naturale # 1」=『霧の神秘主義』を記します。
「霧」mist, nebula, と云うと、わたくしの思い浮かべるのは、はるか昔、早朝しばしば訪れたことのある、或る池(湖、と云うとかっこいいですが、あいにく日本には多数の池はあっても、湖と云えるものは余りありません)の畔に出て、その水面や背景の山々の緑などを眺めていたことがあります。季節によって違いがあるのですが、池の表に霧がかかっていることが稀にあります。この時、濃霧ではなく、薄い霧である場合、池の表面の水面を霧が流れて行く姿が見えます。早朝の金色の太陽の光が昇って来ますと、この霧が素晴らしい美しさで風に乗って流れて行く状態となります。
そこで、わたくしの「空想の翼」が遠い昔にはばたいたのですが、どういう「空想」であったかは、ここで記さないこととします。ただそれは、大層ミステリックな、つまり神秘主義的な空想であったとは申しましょう。この形の空想または構想は、「原型的に」わたくしの人生に刻印されているらしく、この『神秘構造』のなかで、結局生きているわたくしでもあるのです。
「霧の神秘主義」には、もう一つ、「暗黒の霧の神秘主義」があり、これについては以前に少しこの会議室で記しましたが、いまは、明るい方の「霧の神秘主義」を考えましょう。
別の経験として、非常に広い場所(具体的には、学校の運動場とか、屋上)が、淡い靄に包まれた時の情景の記憶があります。山に昇りますと、ガスと云う非常に濃い濃霧があり、ガスはしばしば急速な温度低下をもたらし、また登山者を道に迷わせるものですが、わたくしが云っているのは、もっと淡い靄で、それも平地での話です。
わたくしが記憶しているのは、学校での情景で、この学校は実は三方を山の緑に囲まれています。運動場は学校の窓から見ますと、一面の白い霧に隠れているのですが、屋上にでかけますと、霧と云うより靄と云った方がよく、屋上の端に出入り口階段の扉があるのですが、そこから離れて、屋上の真ん中辺りまで来ますと、入り口階段の辺りが、夢のように白く霞み、そこにいる人々の姿も定かでないと云う程度の靄です。この靄のなかに一人でいますと、広義の「道」とは何であるのかと云う思いが浮かんだのを、いまになって思います。
つまり、靄の冷んやりした白いヴェイルのなかにいますと、世界から隔絶され、別世界にいるような気になる一方、四周には見渡す限り白い膜が重なり、屋上ですから、当然見晴らしがいいはずですが、逆に、宙に浮かんでいるような気分にもなり、また淡い白の向こうには、緑の山々の影が仄見えると云うことで、「別世界」「この世界とは異なる次元の世界」に自分がいるような錯覚が起こると云うことです。
「死後の世界」のイメージの一つとして、このような霧に包まれて、自分がどこにいるのか分からない状態にあると云うものがあります。霧が晴れると何が見え、何が待っているのか、この先になりますと、色々と展望シナリオに差が出て来ますが、「霧の国」とは「死者の世界」とも云えるでしょう。
また深い霧に包まれて、方向を見失い彷徨う裡に、幻覚か現実か何とも判断のつかない不思議な体験をすると云うことが云われています。この体験が「神話の一つの起源」であり、ここに「霧の神秘主義」とも云えるものがあり得ると云うことになります。
ガストン・バシュラールは、「物質的想像力」概念を提唱し、様々な物質をめぐるイマージュについての精神分析的・科学基礎論的議論を展開しましたが、バシュラールの挙げている例はおそらくすべて、「何々物質の神秘主義」と云うものに通じて行くものでしょう。そこから云えば、「水の神秘主義」「火の神秘主義」「空の神秘主義」「風の神秘主義」「大地の神秘主義」など、幾らでも出て来るように思えます。
ともあれ、「霧の神秘主義」の話の終わりに、イギリスの画家のターナーと云う人の名前を挙げておきます。このターナーと云う人は、或る面で「霧」に取り付かれていたような人で、「霧の神秘主義」を絵画としてキャンバスに移すことに色々と努力したようで、非常に有名な「霧」の絵画が残っています。まさに金色の夜明けの光が満ちる霧の向こうに、姿定かならぬ古城が浮かび上がると云う絵がありますが、この絵の写真複製を幾ら見ても、その「古城」と云うものが、金色と白の霧の向こうに隠れて見えません。さながら、バルザックの『知られざる傑作』に出て来る、絵画中に埋もれた肖像のような感じです。
最後に、ターナーが、何故、わたくしの関心を引いているかと云いますと、これは、ジェイムズ・フレーザー卿の古典的名著『金枝篇』の最初の章の冒頭の冒頭の書き出しを読むと、ある程度分かります。ネミの森、アルバの山々、そして黄金の枝です。この場合にも、金色の「霧」が出て来ます。
冥界を暗示するのか、「永遠の命」、あるいは「永遠の謎」をメタフォアライズするのか、『霧の神秘主義』のスケッチです。
|
 Miranda ☆☆☆☆ 1996:1204:1730 Miranda ☆☆☆☆ 1996:1204:1730
 Miranda ☆☆☆☆ 2000:0123:2105 Miranda ☆☆☆☆ 2000:0123:2105
[TOP] [LIST] [HOME] [END] [THOUGHTS] [LITERARY] [MISCELLAN] [INFOR]
  [Mysteria Mirandae] [TOP] [Mysteria Mirandae] [TOP]
Mysterium Naturale # 2
Mysterium Flammeum
『炎の神秘主義』
|
此のシリーズの最初に当たる上の文書では、「霧の神秘主義」と云うことを述べました。そしてこれはバシュラールの云う物質的想像力に関係しており、人間の深層心理において大きな意味を持つ物質・自然現象であり、また、それらをめぐる想像や構想・ファンタシーが「神話」を生み出し、広義の『神秘主義思想』の基底部分をも支え、構成すると云うことが云えると云うことが、ある程度、明らかになったものと思います。
そこで、今回は「炎」fire, flame,をめぐるイメージまた原神話・瞑想とも云えるものを述べてみます。
「火」が古代から重要な宇宙の要素であり、五大エレメントの一つでもあることはよく知られており、「火」が、人間の文化における一つの指標・文化段階のインデックスとしての意味を持つことも周知のことです。「火」には実に色々な神話的・深層心理的意味があり、それをいま論じる訳でも述べる訳でもありません。ここで、考えたいのは、「火」ではなく、その一つの現れである「炎」の心理現象・神話ファンタシー誘導作用です。
炎を見つめ眺めると云うのが、一つの神秘主義や宗教における「瞑想」であると云うことをご存じでしょうか。「炎」はそれを見つめ、その姿の変容を観察していると、無限のヴァリエーションで姿を変え、人間の心を沈静化させると共に、想像力を掻き立て、不思議なイメージを展開します。丁度、雲を眺めていると起こることに似ていますが、いささかに事情が異なる処もあります。
現代の時代において、先進国では、「炎の瞑想」と云うものは日常的にはいささか遠いものになったようにも思えます。つまり電気ストーヴとか石油・ガスストーヴとか、エアコンディショナー、また種々の電気熱発生家庭生活道具類の普及により、日常生活で「炎」を実際に眼にする機会が少なくなったと云うことがあります。
しかし、暫く前の時代においては、そして人類の長い何十万年かの歴史においては、火またはその具体的な姿としての炎は、非常に身近な何かだったのです。つい半世紀前までは、電気炊飯器もガス炊飯器もなく、多くの家庭では、釜などで煮炊きをしていた訳ですが、釜をかけるのは当然「かまど」な訳で、今の台所には「かまど」などはありませんが、昔はすべて「かまど」であったのです。そしてかまどにおいては、燃料は何かと云いますと、これは薪とか、また種々の雑木の枝とか、その他色々な燃焼材料だったのですが、いずれにせよ、これらの燃焼材料は「炎」を出して燃える訳です。
台所のかまどと限らなくとも、昔の日本の囲炉裏や西欧の暖炉、またそれに類似した、暖房兼調理用熱源設備は世界中の文化で存在しました。これらの道具で火を起こす時、やはり「炎」が生まれたと云うことです。人々が「炎」を眼にし、それを長いあいだ眺めて過ごす時間が昔は多かったのですが、最近の先進国では、それは稀なことともなったと云えるでしょう。
「炎」をじっと眺め、その姿の変容を見守り続けますと、人間の深層心理に何かの作用が加わるらしく、そこに実に多様な想像・ファンタシーが生まれます。炎の姿の中に人間は非常に多数のものを見出す訳で、更に炎の燃える変容を眺めている時、人の心理には「癒し」が訪れ、精神の沈静化がもたらされると云う事実もあります。マッチの炎や蝋燭やライターの火でも多少、こういう効果がありますが、やはり持続する「炎」の観察・瞑想は、思いもかけなかった心の反応を顕にします。
イギリスの子供向けの詩であったと思いますが、「火の国」の想像を歌ったものがあったように記憶します。子供は、川を見ても、雲を見ても、海を見ても、何を見ても「想像力」を働かせますが、「炎」はまた、格別な想像力をもたらすようです。燃える暖炉の炎のなかに、遠い東洋の国々を想像するのか、あの炎は宮殿で、あの小さな炎は王様で、あそこの炎は象であるとか、炎を見つめていると、わき上がる想像はほとんど無尽蔵とも云えるでしょう。
『炎を見つめる瞑想』と云うのは、余り聞かないもののように思えるかも知れませんが、実は近代以前においては非常に普遍的に庶民的でもあった「瞑想法」であったとも云えます。ヨーガのように姿勢を定め呼吸法を実践したり、ロヨラの霊操のように、キリストについてのイメージを心のなかに結像させる瞑想(仏教にも、天国のありさまを心のなかで観想する瞑想がありますし、死体の腐敗状態を観想して行くと云うチベット仏教だったかの瞑想法もあります)などと違い、ごく身近な生活のなかに『炎の瞑想』と云うものは存在する訳です。
「火・炎」が人間の心にとって何であるのか、炎を眺めて、それでどこが神秘主義修行かと云うと、実際に長時間眺めてみれば分かります。炎に自分の心の内容が映し出され、炎のパターンの変容に応じて、自分の心のありようもまた連動して変化して行くことが確かめられます。「炎の瞑想」の実践と云うものは、昔はごくごく普通のことだったのでしょうし、「炎」の現象には、「終末」と「永遠」の二つの位相があるように思えると云うこともあります。物理的日常的に、燃える炎は燃料が切れれば消える訳で、これが「終末」ですが、しかし人間の心の反映としての「炎」は物理的な炎が消えた後にも心に残る訳で、これが『永遠の炎』であって、この場合、心が永遠であるので、炎も永遠となるのか、炎の深層心理的意味が、心に「永遠」の意味を付与するのかも知れません。
『旧約聖書』『出エジプト記』に出て来る、モーセが見た、「決して消えることのない、永遠の燃える薪」と云うのは、そもそも、この『炎の瞑想』における『炎の永遠性』の反映であるとも思えるのです。また英国のブレイクの絵画には、天国の光・炎、煉獄・地獄の炎などが頻出しますが、これらの豊かな暗喩意味を持つ炎のイメージは、ブレイクが「炎の瞑想」に親しんでおり、炎のもたらす『神秘の意味』をよく理解していたためとも云うことができるでしょう。
どういう場面であるかは申しませんが、わたくしはかなりこの「炎の瞑想」とも云えるものを経験しています。それ故、この瞑想には、心の鎮静作用があると同時に、無限の変容のイマジネーションの泉としての意味があり、そこに「はかなさ」と「永遠性」の二つの時間展望の両方が顕現していると云う確信が、ある訳です。「炎の瞑想」と云うのは、能動的意志的瞑想または言語理性思考とは違い、能動受動双方向性の「直観的思索」とも云える何かであるのです。記憶が定かでありませんが、「炎の瞑想」を神秘主義修行の一つとして数えていた人が多くいたようにも思います。
皆様には、日常的世俗慣性思考や、言語理性的反省思考や、フォーミュラ化された宗教修行のヴァリエーション以外にも、このような素朴であるが、しかし「底の限りなく深い」「瞑想」があると云うことを知っていただきたく思います。こういう「経験」をしているのと、していないのでは、『心の深層』のありようについての「考え方」が違って来ると云うことです。
『炎の瞑想』とは、「能動的な理性的思考」でも、何か目的のある枠や手順のある「修行」とも異なり、向こうから訪れる何かと、自我の表面の底の「心」の深層のあいだの相互作用事態なのです。そして、このような相互作用を日常的自我意識は、いわば受動的に傍観し観察している訳で、そこに起こっていることは、人間の通常の思考とは別の何かなのです。また、こういった『瞑想経験』を通じて『神秘主義的洞察』が、開かれると云うことです。
|
 Miranda ☆☆☆☆ 1996:1206:1950 Miranda ☆☆☆☆ 1996:1206:1950
 Miranda ☆☆☆☆ 2000:0123:2142 Miranda ☆☆☆☆ 2000:0123:2142
[TOP] [LIST] [HOME] [END] [THOUGHTS] [LITERARY] [MISCELLAN] [INFOR]
  [Mysteria Mirandae] [TOP] [Mysteria Mirandae] [TOP]
Mysterium Naturale # 3
Mysterium Venti
『風の神秘主義』
|
何かいま風邪を引いているらしく頭が痛く、また色々と憂鬱なことがございまして、文章を書く気分ではないのですが、ともあれ、何か書いてみることにします。
さて、風邪を引いているので「風」の話ではなく、何となくそのような気分ですので、「風の神秘主義」と云うタイトルの話です。風 wind, vent, と云うのは、いま示しましたのが英語とフラス語の形で、ドイツ語では英語と綴りが同じで発音の違う Wind,(ヴィント)と云い、ラテン語で ventus,(ウェントゥス)、ギリシア語で anemos,と云いますが、いずれも(英語の場合を除き)男性名詞です。風と云うのは男性だと云うことになります。何故、風は男性なのかと云うことは興味深いですが(フランス語・ラテン語で男性で、ドイツ語・ギリシア語でも男性と云うことは、印欧語族において、『風』は男性なのではないのかと云う想定が出て来ますが、イラン語とサンスクリット語を参照してみないと何とも云えません。ロシア語でも vjetjer,[ヴェティル]で男性です)。ところで:
◇ (覆された宝石のような)朝
と云う、詩の一行があります。これはいまは昔の話になりましたが、西脇順三郎と云う詩人のシュールレアリズム詩とでも呼べばよい作風の、第一詩集の始めの方に出て来る三行詩のその最初の一行です。この詩については、解説があってそれに従っているのか、または、わたくしの心の中で勝手に解釈が出て来たのかよく分かりませんが、「嵐」の後の清明で生き生きして、しかも神秘的な爽やかさの満ちる早朝の情景を描写したものであると、わたくしはイメージで考えています。
日本で云えば台風で、昔の野分ですが、「嵐の怒り」と云う言葉がわたくしにはすぐに思いつくほど、「嵐」と云うものは、自然の「力」の象徴のようにも感じられます。そして「嵐」と云う漢字はよく見ますと、「山」の「風」と云う風に分解されます。山々に吹き荒れる風、これが即ち嵐であると云うのは少し牽強付会ですが、「風」は「嵐」であり、それは共に「自然の力・暴威」の象徴であると云うことです。
夢の象徴解釈において、ユング派での考えでは、蛇とか嵐の出て来る夢は、「深いレヴェルの無意識」の「活発な活動」を示すと考えられています。従って、嵐や風の吹く夢を見ると云うことは、昼間の現実生活における何かの「危機状態」または「異変状態」を意味するのではなく、『深層無意識』の活発な活動を意味すると解釈されると云うことです。それは言い換えれば、人間の文化的社会的生活における「秩序規範」に抵抗する何か、またはそのような小賢しい秩序規範を凌駕し、秩序を凌辱して破壊する者としての「風・嵐」が、『心』において「象徴的意味」を持つと云うことを意味します。
「嵐」とは「山」と「風」であると云いましたが、通俗語源解釈は別に、風が戦う相手は何であるかと云いますと、わたくしのイメージにおいては、それは「森」であり、「森の木々」であると云うことになります。風は森を揺るがせ靡かせ、一晩中咆吼を続けて、森と云う生命と争い続ける訳です。そして、青空と金の太陽の透明な夜明けが訪れた時、風と森の争いは終わっており、風はいづこかに去り、森において、風に破れた老木や若木は折れ倒れ、または枝をもぎ取られ、無惨な姿を晒していると云うことになります。
(風が相当大きな枝をもぎ取り、時には、樹木そのものをずたずたに引き裂くほどの力を持っていると云うことは、嵐の後、無惨に凌辱された木々の姿を実際に目の当たりにしないと信じられないでしょうが、これは事実です。枝や葉が多いほどに抵抗力が大きく、それだけ、樹木に対する「風の力」は壮絶なものとなります。ブレーズ・パスカルの云ったように、「葦」は風の力に逆らわない賢明な生命とも云うべきで、人間は、巨大な樹木として自然に対すれば、「自然の力=風」によって滅ぼされ、打破されるざるを得ないのです。いま20世紀の終わりに、人類の文明は、この「自然の風」と「内なる狂気の風」の二つの『風』によって、「滅び」を前にしているとも云えるのです。『思惟ある葦』として何故『智慧と謙虚さ』で人間は生きられないのか。「神秘主義思想」的にも、このように人間の奢り[ヒュブリス]が、自らの「滅び」をもたらすことは明らかなのです)。
ところで、この「森と風の戦い」には、実は、人間は関与しておりません。人間が関与できない、凄まじい原初の力と力の争い、生命と生命の争いが、風と森の争いであり、人間を含め、あらゆる動物たちは、風が咆吼し猛威を揮って森の木々に戦いを挑んでいるあいだ、どこかの洞窟とか、倒れそうもない巨樹の蔭とか、または粗末な小屋などに息を潜めて隠れている訳で、時には、風は木々諸共、小屋諸共、動物や人間を吹き飛ばし、どこかへ運び去り、命を奪ってしまうような何かなのです。
「風」とはいわば、「自然の力」の象徴であり、その具体的顕現であるとも云えます。わたくしが念頭しています風は、一応森林地帯に吹く風で、砂漠の風とか海洋の風のことは、ここでは考えていないのですが、地球と云う惑星規模で考えますと、風は、めぐりにめぐって地球を一周し、再び元の場所に還って来るとも云えます。昨年訪れた風は、一年の時の経過の後、再び今年も還り来たり、再度、森の生命に挑戦する訳です。
常識的には、森や木々は植物と云う生命ですが、風はあくまで「自然現象」と思われます。けれども、それは「風の力」を実感したことのない人の考えで、風は生命を奪い、人の命を奪って活気付く何かの「霊」だとも云えます。人間の吐く息と風には何かの共通性があり、ギリシア語で「霊」は、pneuma, と云いますが、プネウマとはまさに「霊なる風」のことである訳です。
「風の神秘主義」には、実は無数の話題があり解釈や経験の次元があるとも云うべきです。風は「狂気」であり、また同時に「正気」であり、一切を奪う「死」であり、一切を甦らす「生」でもあると云えます。「聖なる風」、それは神の息吹であり、原初の力の発動であり、人間の一切の努力も智慧も風の力の前には敗北せざるを得ないとも云えるでしょう。ブラックウッドと云う幻想小説作家がおりますが、彼の傑作に、北米インディアンが崇拝する、風のなかに潜む恐るべき「精霊」の話があります。この精霊は人間を捕らえ、そして信じ難い速さで人間を強制的に走らせ、走りに走った人間は結局、精霊に命を奪われ死ぬのですが、走りに走る結果として、その両足が熱により燃えて黒焦げの棒のようになってしまうと云うエピローグになりますが、これは、風が人の心を走らせると同時に、肉体をも強制的に走らせると云う「力」の非常に生々しい具象的表現だと思います。
古代人はおそらく「風」のなかに、何かの「恐るべき霊」が存在すると信じ、実際にその霊の存在を身近に感じたのでしょうし、「命」「息」「魂」「霊」「風」と云う言葉は、しばしば色々な言語において、その語源を辿ると、共通の言葉に行き着くことが知られています。ギリシア語の霊・魂を意味するプネウマは、風ないし息の意味ですし、インド思想におけるアートマンも、風・息と云う意味が基本的にあったはずです。
貴方たちは、吹きすさぶ風が樹木の枝を揺らし、葉をざわめかせ、薄暮れの空のなかで透明な翼を羽ばたく感覚を抱いたことがあるでしょうか。ウィーン幻想派と呼ばれる幻想絵画の一派のなかに、何と云う名前だったのか、いま思い出せなくて困っているのですが、フックスやフッターと並んで、しかしまったく作風の異なる透明な青さと戦慄のイメージを描く画家がいました。この人は第二次世界大戦の悲惨を経験して、そこで独特の作風の幻想画を描いたのですが、『ウィーン』と云う名前の作品だったと思うのですが、翼が切り取られたと云うか、一羽の鳥に複数の翼が結ばれていると云うか、風のなかで、翼が幾枚も重なった鳥(鳥が何羽も切り刻まれ重なっているようにも見えます)が青い透明な空気の帯のなかに見え隠れすると云う不思議な絵がありました。
わたくしは風の吹くなか、樹木のざわめきの音を聞くたびに、自分自身が翼ある何かの存在となり、「永遠の自然の力なる風」の一部として、その「力の超自然的生命」のなかで、世界を宇宙を彷徨ってみたいと云う衝動または憧憬に幾度駆られたか知れないとも思います。風は生きた生命を奪い、風の叫びには死者たちの声が含まれ(レイ・ブラッドベリと云うアメリカの幻想SF作家の『十月の国』と云う短編集の中に『風』と云うタイトルの小説があります)、風は聖なる恐るべき「ルアハ」つまり霊であり、『風こそは神である』とも云えるのです。
風は自然であり力であり、霊であり死であり、生命であり「狂気」であり、宇宙・コスモスの根元的な力動の顕現であるのです。気紛れにして力に満ち、微風として人の心を和ませ、暴風となって、森の木々と戦い、敗北することを知らないのです。「風」に関わる「神秘主義」はおそらく無数にあることでしょう。わたくしの記した拙い詩に『風の詩』と云うものがあり、そこでは、かなり壮絶なことが記されていましたが、それらは青春における「風の力」とも云うべきことでしょう。またロシアにほぼ相当する架空の国・大地の世界を舞台にした『風の歌』と云う長編小説を構想したことがありましたが、この話は、「風の狂気」の話でした。そして我が若き日々は去り、人は去って行くでしょう。願えるならば、風の向こうに、風と共に、我が銀の翼が我を運び、わたくしは地上を遥かに眼下に見下ろし、『聖***』の導きにおいて、星辰の世界へと、銀河の風と共に、去って行くでしょう。……そう願い、夢見つつ、この地上に生きて土に埋もれる命であるとしてもです。
|
 Miranda ☆☆☆☆ 1996:1209:2325 Miranda ☆☆☆☆ 1996:1209:2325
 Miranda ☆☆☆☆ 2000:0123:2237 Miranda ☆☆☆☆ 2000:0123:2237
[TOP] [LIST] [HOME] [END] [THOUGHTS] [LITERARY] [MISCELLAN] [INFOR]
  [Mysteria Mirandae] [TOP] [Mysteria Mirandae] [TOP]
Mysterium Naturale # 4
Meditatio Lapidis
『石の瞑想』
カール・グスタフ・ユングの『自伝』を読みますと、そこで彼は幼年時代に、或る石と云うのか、何かの樹木の削った塊と云うのか、或る不思議な「象徴物」を大切に持っていたことが記されています。後年、世界中の当時未開文化と呼ばれていた様々な文化に直接触れ、それらの未開の人々における深層心理の意味について研究し思いをめぐらした時、カール・ユングは、突然に自分が幼年時代に大切にしていた、「石」または「木の彫刻」を思い出すのです。未開文化の人々にとって、このような「石」または「彫刻物」は、一種の護符であり、それはまた、悪と死から自らを守る、自己の「第二の自己」、あるいは霊の力ある魔術の「象徴結晶」であることをユングは知り、このような第二の自己の「魂」の象徴物が、実は文化普遍的な事態であると悟るのです。
さて、わたくしにもまた、このような「石」 Lapis, を持っていた記憶があり、それは見かけ上、何の変哲もない石ではあったのですが、そこに何かの「意味」があるように思え、それをあたかも生き物のごとく、何かの神秘な力を持つ「象徴結晶」のごとく扱っていた記憶があるのです。『石の瞑想』と云う言葉で喚起されるテーマには膨大なエピソードと象徴意味がおそらくまとわりつき、例えばシュティフターには『石さまざま』と云う短編集があり、そのなかの『水晶』と云う話のなかには、夜のしじまの氷河の洞窟から見上げた満天の星界の海で繰り広げられる、霊妙なる『神秘の模様』の展開が記されています。
わたくし自身は、何時頃からか、多分、若かりし頃より、七宝のペンダントを一つ持っていました。ペンダントであると云うことに意味があるのではなく、実は、この七宝の石に意味があるのです。それは緑と青の混じり合った微妙な色彩で、花びらのパターンが構成されていたのです。その七宝の石を持っていた頃、わたくしはスリーヤントラを描き、また自分のマンダラ図と云うものを描いてみました。マンダラ図は複雑なものを設計しようとすれば幾らでも設計できるのですし、モデルとしては、ボーリンゲン・シリーズのユング選集の中の第9巻第Ⅰ部の『原型と集合的無意識』の本に、様々な例示が載っており、非常に美しいとも云えるものがあります(9巻第Ⅱ部は『アイオーン』です)。
そこで、わたくしは「自分の心のマンダラ図」を描いたのですが、最初の設計では、もっと色を多数使い、かなり華麗な神秘的なものにしようと考えていたのですが、描いてる裡に、ある処まで来ると、これ以上に色を加えるのは「よくない」と考えるようになりました。失敗を恐れていたのかも知れませんが、ともかくもシンプルな美しさで調和が取れていると思えたので、これで完成しているのではないかとも思ったのです。それは空白の多いマンダラ模様なのですが、色彩は緑と青で、丁度、あのペンダントの七宝の石と同じ模様と色になっていました。無論、このことは別に偶然の一致ではなく、七宝の石を選んだのはわたくしですし、マンダラ模様を描き水彩で着色したのもわたくしです。つまり、このような色とパターンがわたくしの『心の模様』であると云うことでしょう。
このマンダラ模様には「ある特徴」があるのですが、それは何故そうなのか、それについて語ることはないでしょう。七宝の石はいまでも持っていますが、考えてみれば、我が貧しき人生にあって、この七宝の青緑の花模様の石こそは、最大の宝飾であり、我が魂の結晶、我が「第二の自己」ではなかったのかと。フリードリッヒ・フォン・ハルデンベルクの作になる『ハインリッヒ・フォン・オフテルディンゲン』の最初の章は、主人公ハインリッヒの「夢」から始まり、この夢のなかで、ハインリッヒは一本のきわめて魅惑的な『青い花』を見るのであり、この作品は、つまる処、この『青い花』を探求しての物語となっています。
フリードリッヒ・フォン・ハルデンベルク、すなわちノヴァーリスが作品に描いたこの『青い花』とは何であるのか、『青い花』を求める探索の旅とは何であるのか。物語は未完のままに終わり、ノヴァーリスは、その地上の至上の愛の結晶たるゾフィー・フォン・キューンの後を追うかのように静かにこの世を去って行きました。『夜の讃歌』は一体、何を歌っていたのか、『青い花』の『献詩』において、何が歌われていたのか。
ルネ・マグリットの中空に浮かんだ巨大な岩とその上の小さな城の「意味」が、わたくしたちには定かに分からないと同様、ノヴァーリスの真の意図が何であったのか、ティークの報告によっても、それは定かでないとも云えるのです。石はまた『青い花』でもあり、それは「永遠の魂」「第二の自己」「達成すべき結晶」……アイオーンにおける『星の石』であるのでしょう。意味のないこれらの言葉において、何を浮上させようとしているのか。それはグノーシス主義の道にあっては、人は『秘密』を築かねばならず、『秘密』は、時に「石」に、時に「宝石」「水晶」に、時に「花の模様」に、時に「マンダラのパターン」に、永遠を刻んで結晶し、「時間において静止する」。デカルコマニーで築いた絶妙なるエルンストの『沈黙の目』のように、我らは『秘密』を、この『石 Lapis』に抱いて生死を過ぎ去る。
この天は過ぎ去り、次の天も過ぎ去る。我らは、人のあいだにあって何を求めんとするのか。みずからの『秘密』を刻んだ『石』を、みずからの第二の魂として、沈黙の永遠を結晶のメロディアに過ぎ行かんと。
以下に示す・さる未完の話の断片に述べられているごとく、人は愛し合いつつ孤独であり、求めるものは、永遠の沈黙の彼方の氷河の春に似た、『もう一人のわたし』であると云うのか。リュシア・セクレは青緑の神秘の眸で、ジョルジュ・ローズ・アルシノワールに『石』を与え、別の世界の別の時代で、一人の少年が『石』を手に入れ、一人の少女に向けて囁きかける。(死が定めであるとしても)(いいえ、ジョルジア、人は死ぬことがない。『永遠の結晶の石』・『銀のリング』が、貴方に代わり、『霊の故郷』へと還って行くでしょう)……
==================================
UNE SCENE DE L'HISTOIRE PERDUE
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
リュシアは、窓の外の僅かに萌黄色が生まれはじめてきた森の樹々に視線をむけて静かにこたえた。
「ひとの人生にはなにが生じるのか、わたしたち有限の者には、わからないわ。いまわたしたちは微笑を交わしあい、そして十分後にわたしかあなたの冷たい取り返しのつかない死が待ちうけているかもしれない――これが人生のありようであるわ。『この天はすぎ去り、次の天もすぎ去る』これは何の言葉だったでしょうか。ともあれ……ルーランはなおあなたを愛しているわ。ただ、ひとの〈愛〉は現実の口づけや愛撫や直接の交わりだけから造られているわけではないことも事実よ」
「けれども、リュシア……」
リュシアは薄い銀色のアイシャドーを塗ったまぶたを閉じると、歎息するように言った。
「世界には美しさが満ちているわ。黎明に鳴く小鳥たち、薔薇色から濃い茜色までの夜明けの空の色の神秘。そして、猥雑なひとびとの生活にも、それなりの〈美〉があるものよ。哲学的思索によって《真理》を求めて行く果てにひとは何をえるでしょうか、ジョルジア。ルーランにはその『限界』が垣間見えたのだとわたしはおもうわ」
「だから、ぼくに〈あの言葉〉をささやいたのですか?」
「わたしはいつでも〈言葉〉をかたるわ、ジョルジア。『この言葉の解釈を見いだすものは、死を味わわないだろう』たしかそう書いてあったわね。……ジョルジア・ローズ、わたしはあなたを愛しているのよ、そのことが分からないのですか?」
「かも知れない。けれどもぼくは貴女を愛してはいない」
「ひとがひとを愛するのに、その相手が男性であるか女性であるかは、何の関係もないことよ、ジョルジュ。ルーランはわたしを心から愛している。わたしたちの結婚は、偽装結婚なのではないのよ。そのことは最初からあなたにはわかってらしたことでしょう、ジョルジア。そしていま、ルーランがカトリックの信仰に目覚めようとしているのなら、それもまたひとの人生において〈あるべきステップ〉の一つでしかないわ」
リュシアは薄緑の瞳を開くとわたしをじっと見つめ、独特の謎めいた微笑を浮かべて言った。
「そしてわたしはルーランを愛し、同時にあなたを愛し、あなた自身はと云えば、ルーランを心から愛しつつ、実はこの〈わたし〉に対する《愛》をもまたいだいている」
わたしはリュシアの藤色の香水の馨りがするミルクの色の容貌と、薄緑の謎めいた眸を見つめた。
「わたしたちのこの〈愛〉は、永遠の暗黒の宇宙のなか、諸アイオーン〔永遠世界〕に亘って、《結晶の星座》として耀いていますよ、ジョルジア。そう〈結晶〉です」
そう云いつつ、リュシアは飾り机の上の宝石箱のなかから、何かキラキラ光る紫色の石を取り出してきた。
「はるかな古」とリュシアは言った。「グノーシス主義のある人々は、永遠の世界の破片が自分たちの霊のなかに埋め込まれているという《真実》を象徴的に表現するため、それぞれ自分で、この世のなかの材料をもとに、〈永遠の破片〉のこの世における模造をさがし求めあるいは造り出し、それを一生涯身につけたと云います。これはエジプトのある遺跡で見つかった、いまから千八百年ほど前のそのような象徴としての〈永遠の破片〉です。――ジョルジア、あなたにこれを譲りましょう。わたしがなぜこれをあなたに譲るのか、いつの日かあなたは理解するでしょう。お受け取りなさいな、ジョルジア」
わたしはリュシアのまだ若さを失っていない瑞々しい指先から、ペンダントの形に加工されたその紫の宝石を受け取った。リュシア、とその時わたしはおもった。ルーランはもうすぐ五十に近くなる。けれども貴女は三十歳になったばかりで、しかも貴女の若さは、二十代の始めの頃と少しも変わっていない。……
わたしは紫の宝石を手に握ると、リュシアの薄緑の眸を覗き込んだ。そこにはどこかおかしがっているような、不可解な表情があった。
「その石は」とリュシアは云った。「《宇宙の*》と呼ばれています。あなたはだから、宇宙の*をいま手に入れたのです、ジョルジア!」
………………… |
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
UNE SCENE DE L'HISTOIRE PERDUE
==================================
|
 Marie RA. S. et
Miranda Noice Marie RA. S. et
Miranda Noice ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ 1997:0308:0640 1997:0308:0640
 Marie RA. S. et Miranda Noice Marie RA. S. et Miranda Noice ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ 2000:0123:2314 2000:0123:2314
[TOP] [LIST] [HOME] [END] [THOUGHTS] [LITERARY] [MISCELLAN] [INFOR]
  [Mysteria Mirandae] [TOP] [Mysteria Mirandae] [TOP]
Mysterium Naturale # 5
Spiritus Arboris et Silva
『樹木の霊』
Partie I
|
「樹木の霊」と云っても、別にオカルティックな話ではありません。ここで念頭している樹木は一応「森」の樹木のことで、樹木単独でも森単独でも、神秘主義に関する話題は一杯あるような気がしますが、まずは簡単な話だけに限りたく思います。
都市に居住しておられる人は、樹木の鬱蒼と繁った森と云うものが、どういうものなのか、旅行などで時たま出会われることはあっても、日常的には、余り縁がないものと思えます。しかし、自然の樹木の林・森などに入って行きますと、何か爽やかな気分になり、心が明澄となると共に、心身の健康にとって快く良いと云う感覚は多くの人が抱きますし、これは、樹木が微量に発する一種の芳香物質が、森の中の空間には、かなりな密度で存在するためと云われており、実際に、心身の健康に良いと医学的な研究でも相応の答えが出ているようです。
また、樹木の繁る森の中と云いますと、まずそこは、普段の生活の場でないと云うこと(林業とか、果樹園の仕事をしている人などは別ですが)、そしてまた「静寂」があり、古く年老いた樹木などに囲まれていますと、その場が、自然のカデドラルのごとき荘厳な場所であるような気分になって来るのも事実です。昔、『森の女神は静寂を愛す』とか云うギリシア語の言葉があったような記憶がありますが、あれはわたくしが勝手に作文したものだったのかも知れません。
都市にしばしば設定されている公園の中の人工の森などは、いかにも人工と云う感じがしますが、それでも精神的な健康・心の平安には適しているとも思えます。しかし古来、何か精神的な修行をするとなると、または深く瞑想などをしようとした人は、深山幽谷と云うと大袈裟ですが、そのような場、つまり樹木の生い茂る森の奧へと入って行ったようにも思えます。
ニーチェの『ツァラトゥストラは、かく語れり』の冒頭も確か、ツァラトゥストラは深山かどこか山に一人で籠もり、瞑想・思索を続けたが、或る日遂に、昇る太陽を見て、と云う風に記述が始まっていたと思います。
日本でも、比叡山にしても高野山にしても、鬱蒼たる森林のただなかにあります(山岳信仰・修験道とは別に、普通の仏教でも山に籠もったようです。五山文学・哲学と云われるものも、山寺にいる仏僧たちの墨跡・思索の成果です。これは鎌倉仏教の特質かも知れませんが、その前の平安文学でも、何かと云うと出家して山に籠もるとか云う話が出てきます。源氏が若紫を見つけるのも山の中ですし、源氏自身、晩年は出家して山に籠もり亡くなったようですし、宇治編の八宮もまた、どこかの山寺で修行に励んでいて呆気なく世を去りました)。
山に入るとは、出家あるいは「世を棄てる」と云うような意味があったのでしょう。少なくとも、この日常世界とは別の次元の世界に我が身を置くと云う覚悟の表明であり、実践でもあったのでしょうか。中国では、周王朝に滅ぼされた有名な殷の忠臣二人が山に入り、隠棲し、蕨などを食べつつ、「周粟を食まず」とか云っていますと、山も周の領土であるとか主張され、二人は餓死したとか云う話がありますし、かの諸葛亮孔明も、田野と云うか、山に隠棲していたとも史実として伝わっています。山の中には、平時や戦乱の時に関係なく、山賊や逃亡農民や修行者や隠棲者や色々な人がいて、『水滸伝』では、さる山を本拠にして英雄豪傑が時の王朝に戦いを挑むと云う話です。また竹林の七賢などもいたと云われています。(中国はよく知りませんが、日本で竹林に苫屋を建てて住んでいたりしますと、百足は無論、藪蚊の襲撃で、どうにもならないでしょうね)。
どうも話がずれて行きますが、森と樹木の神聖さと云うものは、確かにあったようにも思えます。インドのウパニシャッドは、語源的には「身近で話すとか聞く・伝える」と云う意味だったように記憶しますが、「森林の書」とか云う意味もあったような記憶もあります(あれは、アーラヌヤカか何かだったでしょうか。手元に資料が出て来ませんので、記憶で記しています。略しますと、四ヴェーダ→ウパニシャッド→サーンキヤ綱要→ヨーガ教典→ブラフマ文献→ヴェーダーンタ文書、だったと思うのですが)。ウパニシャッドを師が弟子に伝える時、確か師弟で深山に入り、誰もいない場所で一対一での対話を行ったとも云われていたと思います。
これは、また聞きですが(本で読んだのではありません)、日本ヨーガの初期の普及者の方でO先生と云う方がおられますが(すでに故人ですが)、この方は、簡単な健康・美容ヨーガの著書もありますが、インドでグルについて本格的な修行をした人です。その話では(一時、師事していた、わたくしの昔の知り合いが聞いた話のまた聞きです)、何か特別な修行をすると云うので、兄弟子に連れられて、まったく方向もどこにいるのかも分からない深い森の中に導かれ、ふと気づくと、その兄弟子が、何時の間にかいなくなっていて、幾ら待っても現れないし、かと云って、戻る道も分からない状態になったそうです。当時のインドの森の奧には、虎は出るは大蛇は出るは毒蛇もいるわで、命賭けのことでもあったのですが、そこは慌てず、精神統一し、瞑想などをしておりますと、やがて大分経って、兄弟子が姿を現し、今日の修行は成功だ、とか云ったと云う話があります。兄弟子は、どこかの場所でキチンとコントロールしていた訳で、まったく未知の場所(特に、森)で一人で放置されると、どう云う心理になるか、それに対しどう振る舞い、心を統一するのかの修行であったらしいそうです。(下手に慌てて動き回ると、余計に道に迷ってしまうと云うことでもあるのでしょう)。
|
Continuee a la Partie II
 Marie RA. S. et
Miranda Noice Marie RA. S. et
Miranda Noice ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ 1997:0329:1700 1997:0329:1700
 Marie RA. S. et Miranda Noice Marie RA. S. et Miranda Noice ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ 2000:0124:0144 2000:0124:0144
[TOP] [LIST] [HOME] [END] [THOUGHTS] [LITERARY] [MISCELLAN] [INFOR]
  [Mysteria Mirandae] [TOP] [Mysteria Mirandae] [TOP]
Mysterium Naturale # 5
Spiritus Arboris et Silva
『樹木の霊』
Partie II
|
欧州については、わたくしは普通「欧州森の大陸」と云う言い方をしますが、それは、イタリア・フランス・ドイツなどの主要領域は、大体中世末期から近世にかけても、ほんとんど森に覆われていたのであり、大陸全体を覆う大樹海の中に孤島のように集落とか都市などが、森の勢力奪回の勢いと戦いつつ、森でない開拓空間を必死に維持していたと云うのが実情だからです。
現在、欧州の多くの住民はゲルマン族の子孫で、それに広義のローマ人つまりイタリア人などが混ざりあった人々ですが、元々のゲルマン族は、勢力衰退してしまったケルト族と共に、森の住民であり、森の文化を持っていました。ところで、キリスト教と云うのは、ヘレニク文化の混沌の坩堝から出現して来たものですが、本質的にユダヤ教の変形とも云え、砂漠のオアシス文化の特質が色々な教えや教義方針に刻まれています。遊牧民族の宗教とも云え、ユダヤ教またユダヤ人たちが、紫のカナアンの「約束の地」において、農耕文化の持ち主であったペリシテ人などと争い、ペリシテの農耕神バールとかアシュタルテなどを否定したことは、よく知られています。キリスト教が、カロリング・ルネッサンスや、それ以前のローマ帝国のゲルマン化とも云える過程において、徐々に森の大陸のゲルマン族などのあいだに広がって行った時、森林文化・狩猟農耕文化のゲルマン族やケルト族・ノルド族などを、どう懐柔し、またどう強行策に出たかなどは、以前に述べたと思います。
キリスト教(原始キリスト教)において、すでに森の文化的要素が実は入っているのですが、キリスト教に改宗した欧州森の大陸の住民たちは、当然自分たちの森の文化を、キリスト教に適合させようとしたのですし、キリスト教側でも似たようなことが行われました。その結果、ヘレニク文明のシンクレティズム宗教であったキリスト教は、更に森の文化の信仰ともシンクレティズムを起こし、現在の欧州にあるような複雑怪奇な宗教が出来挙がったと云うことです。
しかし、これは話の本筋からは少し逸脱したことで、元々の話は「樹木と森」なのです。少なくとも欧州森の大陸の住民たちであったゲルマン族などは、「樹木崇拝」を行っていたことが推定されます。キリスト教は、かようなことは否定する訳ですが、カエサルの『ガリア戦記』だったか、タキトゥスの『ゲルマーニア』だったか忘れましたが、ゲルマン族(と云っても、ローマ人は、そういう分け方はしていなかったようです。ケルトとゲルマンも区別していなかったようです。森に住む色々な蛮族が部族社会を構成していると云う認識でした。とまれゲルマン族)は、樹木を非常に神聖なものと考え、ある特別な樹に傷などを付けたり、枝を折ったりした者には重罰が課されたと記されていたように思います。また、この神聖な樹への冒涜だけではないと思いますが、「罰・死刑」の中でももっとも重いものは、この神聖な樹に、処刑される者の内臓の腸の一部を切り裂き引き出し、これを樹木の表皮に釘付けにして、罪人には、樹木のまわりをぐるぐる回らせて、こうして内臓が腹から引き出され、聖なる樹のまわりに腸がぐるぐる巻きになるようにし、かくて罪人を固定して、死ぬに任せたと云う記述があったと思います。
ゲルマン人やケルト人は、樹木には精霊あるいは霊が宿っていたと信じていたのでしょう。それはまた森林そのものが「神」であり「霊」であると云う信仰でもあったと思います。キリスト教の修道院も、大都市などに置かれるものは別に、一種人里を離れた森を切り開いて、そこに築かれることがあったはずです。封建領主の一種としての聖職封建領主である司教とか大修道院長などの支配する領域は、都市や平野部だったでしょうが、森林に植民された修道院と云うものは、やはり、森の神聖さと云うものに何がしかの敬意を払ったものでしょう。(フリードリッヒの有名な絵画に『山上の十字架』と云うものがあり、これは奇怪なことに、明らかに欧州・ドイツの森林と思える鬱蒼とした樹木に囲まれた山の上に、三本の十字架が立っていて、キリストが磔されていると云う絵ですが、これは一体、どういう思想を示しているのかとも思います)。
樹木の霊または精霊と云うことであれば、古代ギリシアには、ギリシア神話でお馴染みの「ニュンペー」と呼ばれる、精霊的存在が、至る処にいました。普通、英語読みして「ニンフ・精霊」と呼ばれているようですが、山とか森とか川とか泉とか、至る処にニュンペーは存在したようで、これは古代ギリシアの自然崇拝の名残とも云えますが、ここで、ニュンペーは人里にはいないと云うことを考えてください。と云いますか、紀元前5世紀かそれ以前のギリシアは、実は欧州森の大陸の一部で、ペロポネソス半島も、実は、いま見るようなオリーヴしか育たない荒涼とした、裸の土地ではなかったと云うことです。
古代ギリシアは「森の世界」であり、だからこそ、至る処の自然の精霊、と云うよりむしろ「森の精霊」と云ってよいニュンペーが存在したと云うことです。古代ギリシアには、では森の神は存在しないのかと云いますと、多分、オリュンポスの神のパンテオン設定において、古い神々は放逐された可能性が高いのです。女神アルテミスが存在しますが、この女神は「森の女神」であった可能性が高いと思います。人間にとって「聖なる森」「聖なる樹木」は、人が犯してはならない「処女存在」であったのですが、アルテミスは処女の神です。それと、パルラス・アテーネー女神も、智慧と戦の女神とされていますが、森の神の名残を持っていたのではないかとも想像します(聖なる森・聖なる樹木と云いますと、フレーザー卿の『金枝篇』が思い浮かぶのですが、それは今回措いておきます)。
明らかに樹木の霊と考えられるのは、樹木に変身した乙女の伝説に現れる乙女たちです(少年で花に変わっのはヒュアキントス・ナルキッソスですし、女性で星になっ
たのはプレイアデスとオリオンであるとか、「変身」の話がギリシア神話には多いですね)。とまれ一番有名なのは、無論、ダプネーですが、ポイボス・アポルローン神の求愛を嫌って、樹木になることをヅェウス神に願い、その身が変じて「月桂樹」に変身したと云われている乙女です。元々「ダプネー」Daphnee,と云うのは、ギリシア語の普通名詞で「月桂樹」と云う意味であって、ギリシア語で、この神話を書いて読んで見ると、幼児向けの話か、こじつけの語源解釈としか映りません。しかし、あるいは何か深い根拠があったのかも知れません。
樹木は新鮮な樹の芳香と、その緑の群葉で確かに心を和ませ、また平穏さと静かな心境をもたらすでしょう。そして森には、おそらく心を開けば、「霊・神」が存在しており、人間の魂・霊と何かの交流が行われるのかも知れません。森にあって瞑想し、木々の高みに星の姿を見、銀河の白いベルトを知る時、或る一つの「自覚洞察」が生じて来るでしょう。それが何であるかは、各人が試みられることでしょうが、「朝の森」「昼の森」「夕の森」、そして「夜の森」には、それぞれ、それを経験したことのある人にしか分からない神秘があるものです。
|
 Marie RA. S. et
Miranda Noice Marie RA. S. et
Miranda Noice ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ 1997:0329:1700 1997:0329:1700
 Marie RA. S. et Miranda Noice Marie RA. S. et Miranda Noice ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ 2000:0124:0200 2000:0124:0200
|
追記:
上で、次のように記しました:
◇ (少年で花に変わっのはヒュアキントス・ナルキッソスですし、女性で星に
◇ なったのはプレイアデスとオリオンであるとか、「変身」の話がギリシア神話
ところで、書き忘れてしまいました。つまり、「女性で星になったのはプレイアデス」と云うのはこれでいいのですけど、「オリオン」は男性の英雄です。ですから、本来文章は、以下のような:
◇ 女性で星になったのはプレイアデスで、
◇ 男性で星となったのはオリオンであるとか
こういうものでなければなりません。なお、プレイアデス Pleiades と云う名前は、実は、プレイアス Pleias と云う固有名詞の複数形で、プレイアスとは、七姉妹の裡の一人を指す言葉で、七人の娘全体を総称して、「プレイアデス」と呼びます。プレイアデスは、アポルローンに追いかけられて月桂樹に変身したダプネーとよく似て、先のオリオンによって求愛され追われて、結局、天に昇って星になったとされています。
天文学で、プレイアデスは散光星雲であり、中心に複数の若い星が存在し、周囲の星間ガスを輝かせていたのだと思います。人間の肉眼では、大体プレイアデス星雲は、七個の星の集まりに見えます。目がよい人は9個見えるとか、もっと見えるとか云う人もおりますし、4個しか見えないと云う人もいます。
|
 Miranda ☆☆☆☆ 1997:0329:1825 Miranda ☆☆☆☆ 1997:0329:1825
 Miranda ☆☆☆☆ 2000:0124:1325 Miranda ☆☆☆☆ 2000:0124:1325
[TOP] [LIST] [HOME] [END] [THOUGHTS] [LITERARY] [MISCELLAN] [INFOR]
  [Mysteria Mirandae] [TOP] [Mysteria Mirandae] [TOP]
Mysterium Naturale # 6
Mysteria Silvae
『森の神秘』
ところで、わたくしの家で昔飼っておりました、愛犬の話をしようとも思ってい
たのですが、その前に、先の「樹木の霊」についての補足を少し記しましょう。
この文書自体が更なる補足を必要とする文章かもしれませんが、ともかく簡単に述べてみたく思います。それは、「森」と云うものが持つ、人間の心・精神に対する「意味」のことです。
「樹木の霊」で様々なことを記しましたが、「森」が持つ「暗黒性」と云う面には余り触れませんでした。では、森の持つ「暗黒性」とは何かと云いますと、これは、人工の手の入った森しか知らない人には、恐らく想像が付かないことかも知れません。
わたくしは欧州について、「欧州森の大陸」としばしば呼びます。実は、この日本についても、「日本-海洋と森の列島」とでも呼べばよいのですが、日本の歴史における「森の有意味期間」と云うのは信じがたいほど長く、それは歴史の記憶の遥か向こうに忘れ去られて久しいとも云えるのです。
|
-----------------------------------
日本については、わたくしはスケッチとしての文章で、「日本文化の源流」として、四つの文化が最低関係していることを以前に述べたことがあると思います。どなたかが、「日本」は「和の思想」の世界で、異文化との接触や摩擦について基本的に「幼稚」であると云う意味に通じる発言をなさっておりましたが、これは間違いだと思います。つまり、日本文化ほど異質な種々雑多な文化の坩堝であった文化は実は珍しいのではないのかとも思うからです。
詳しいことは省きますが、日本には異常に長い「縄文時代」と呼ばれる時代があります。実はこの期間が問題であり、日本における「和の思想」と云うものは、異文化のあいだの対立を何とか宥和するため、目には目を、歯には歯をと云う、いわゆる「議論文化=訴訟文化定式」の存在様態では、問題は解決しないと云うことを悟った、日本古来の「智慧」の顕現ではないかとも思うのです。
アメリカには自由がありますが、正確に云いますと「公平な法的判定」がありません。ないし稀薄です(弁護士の数や技量、また陪審人の個人信念で有罪が無罪になったり、その逆が正式に認められると云うのは、公平な判定とは云えないと思います)。訴訟とか裁判は「無法」であるが故に、または無法な人間達だからこそ、それを当然のことと考えているのではないのか・と云う視点が欠けているとも思える訳です。訴訟が極端に多い国の代表はアメリカとも云うべきでしょう。そのアメリカの文化とは、実は、非常に若く幼稚なものではないのかと云う反省が起こるべきだとも云えます。
当然のことですが、訴訟に対し訴訟で応じていては、ねずみ算のように訴訟が増えて行くだけで、「現実的な解決・社会文化の和解」と云う発想は起こって来ません。自己が絶対に正しいと考える欧州キリスト教文化も中近東イスラム文化も似た処があります。
------------------------------------
|
少し話が脱線しましたが、日本は非常に古い「森の文化」と「海洋文化」の両方を備えていた場であったと云うことです。海・海洋・太洋のことはとまれ措いておくとしまして、元の主題である「森・シルウァ」に話を戻しましょう。
「欧州森の大陸」の中心部、と云うことは大体、現在のフランス・ドイツ・オーストリアを中核としてその周辺のイタリア・ポーランド・ギリシア・チェコ・スロヴァキアなどを考えている訳ですが、これらの地域が、ごく最近に至るまで、非常に密生した森に覆われていたことは記しました。
欧州森の大陸にケルト族が移入して来た、またゲルマン族が移入して来た、と云う時、それは北米の大草原を大規模な集団が移動して来たのではないのです。森の中を少しづつ開拓し、樹木を伐採して、空間を切り開き・耕地を確保しながら少しずつ進んで行ったと云うのが実情です。
ローマ帝国が紀元前後にゲルマン族やケルト族と接触した時の状況はどうであったのかと云いますと、ゲルマン・ケルトに属する諸部族が、色々な意味で立地に便宜ある場所の樹木を伐採し、ある空間を耕地などとして確保して、そこに、四周を完全に森に囲繞された、小さな文化の場を構成して居住していたと云うのが実情です。これは中規模な居留空間で、大規模な居留空間、例えば現在のパリに当たる場所には、かなりな空間が開拓されていて、そこは諸文化の物々交換かもう少し進んだレヴェルでの通商交流の交差点でもあったのです。
しかし多くの人々は、中規模居住空間の近くに、もっと小規模な居住空間を、広大で踏み入り難い「森の空間」に周囲を囲まれて、何とか維持していたと云う状況です。しかも、この森は、再侵略し、奪われた土地を奪回しに執拗に訪れる何かであり、小規模な居住空間も中規模空間も、人が不断の戦いを森と行い、森の侵略を食い止めない場合、やがて森が勝利し、森の中に開かれた「空間」は、再び森の中に飲み込まれ尽くすと云う運命にもありました。
中世以前の欧州にあっては、森とは、心をフレッシュにする憩いの場などではなく、襲いかかって来る、もっとも執拗かつ敗北を認めることのない「敵」であったのです。
また「森」には、このような「侵略者」としての現実的イメージの他に、森の内部は人間が日常的に生きる空間ではなく、何か戦慄すべき「未知の世界」であると云う認識がありました。いわばイメージとして図を描いてみると、樹海と云う広大な暗黒の領域が欧州大陸全体を覆っており、その中にほそぼそと点在する形で、小さな光の領域=人間の開拓地=文化の光ある既知の世界があったとも云えます。
この「暗黒」の森の世界には、狼や熊や大猪や獰猛な野生の牛が存在し、しばしば人はその攻撃を受けましたし、森の中で道に迷うと云うことは、実は、道のない領域に入り込んでしまったと云うことで、現実的な危険性・生命の危険の他に、心理的な恐怖・危険性もあったと云うべきです。
森の「暗黒性」とはこのようなもので、それはいわば、無意識あるいは自然の無限の力と暗黒の現実的象徴であり、人間の自我意識とは、実は、この暗黒の樹海のあいだに辛うじてその存在を維持している、小さな光の開拓地でもあると云うことです。レヴィ=ブリュールが云っていたのだと思うのですが、未開人はたやすく自我を失い、広大な無意識に飲み込まれてしまうことがしばしばあり、その為、無意識に呑み込まれないよう、そして自我を維持するよう、様々な宗教的儀礼・儀式や呪術の類が生成されたと云う考えがあります。
こうして「森・シルウァ」と云う実体が持っている人間心理における意味は、人間の自我の光の場を呑み込む「暗黒」、そして「原始」の無意識の広大なる海、人間の自我がやがて滅びの果てに還るべき、あるいはその未知と暗黒の無限の空間へと吸い込まれる「始源の宇宙」でもあったと云うべきです。
「森」とは、暗黒・無意識・未知・恐怖、そして文化のささやかな光に対抗する原始の世界の雄大な象徴であったのです。象徴であるだけでなく、かつてはそれが現実であったのです。「森の神」は実に、名前にすることも恐ろしい何かであったとも云えます。
|
 Marie RA. S. et
Miranda Noice Marie RA. S. et
Miranda Noice ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ 1997:0330:1530 1997:0330:1530
 Marie RA. S. et Miranda Noice Marie RA. S. et Miranda Noice ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ 2000:0124:0222 2000:0124:0222
[TOP] [LIST] [HOME] [END] [THOUGHTS] [LITERARY] [MISCELLAN] [INFOR]
  [Mysteria Mirandae] [TOP] [Mysteria Mirandae] [TOP]
Mysterium Naturale # 7
Lumen de Lumine
『光・光明』
「光」「光明」と云うものを、「自然の神秘」として考えると、これは非常に哲学的神学的なものから、象徴的な意味、またもっと素朴な人々の受け取り方など非常に広範囲に亘るテーマとなります。
「物質的想像力」を提唱したガストン・バシュラールには、「水」「空」「火」「大地」をテーマにしたモノグラフ的著作があったと思いますが、これらのテーマにおいて、膨大な象徴解釈の議論などが行われております。従って、このシリーズ(NM)での随想的文書においても、ことは非常に複雑な訳ですが、その点につきましては、とりあえず簡潔な話としてまとめ、後に必要に応じて追加して行くと云うのが妥当でしょう。
「光は東方から」と云う言葉があり、これは、地球上のどこの地点であっても、(春分・秋分の南北の極地点と、白夜の状態の地域は、季節的に除外するとしまして)、太陽が東から昇って来るのであり、それ故、曙光もまた東の空に出現すると云うことでもあるでしょう。
西欧から眺める時、長い期間において、文明や知識や智慧は、みな、オリエント(東方世界)に存在したものであり、17世紀当時では、清朝中国の文明の高度さを西欧の知識人は称賛し認めていたとも云えます。また、ヴォルフガング・ゲーテは、東方世界には、自分が知らないだけで、おそらく卓越した芸術家や詩人が多数いたに違いなく、自分などは、そのような偉大な人物と比較すれば、光に対する蔭のようなものであると云う趣旨のことを述べていたとも云われます。
それはともかく、「光・光明」を「神」として捉える宗教は非常に多く、神の本体が光ではないとしても、神が光・圧倒的絶対的な光と光明を備えており、その本質属性の一つが光であると云うことは多く認められています。
例えば、キリスト教の長文ヴァージョンの『使徒信経』のなかには、次のようなラテン語の言葉があります。少し長いですが、一部を切り取ります:
 RF RF Credo in unum deum. .... Et in unum dominum Jesum Christum, Credo in unum deum. .... Et in unum dominum Jesum Christum,
 RF RF filium dei unigenitum. .... Deum de deo, lumen de lumine, deum filium dei unigenitum. .... Deum de deo, lumen de lumine, deum
 RF RF verum de deo vero. .... verum de deo vero. ....
これは長文で文章が切れていますが、すべて最初の「Credo in」と云う表現に続いています。つまり「我は信じる……を」と云う文章形式で、「……」部分が延々と続いている訳です。上の文章断片は次のような意味です:
 RF RF 我は信ず・唯一の御神。……そして神の御独り子・息なりし唯一の主 我は信ず・唯一の御神。……そして神の御独り子・息なりし唯一の主
 RF RF イエズス・キリストを。……神よりの神、光よりの光、まこと(真実)の神より イエズス・キリストを。……神よりの神、光よりの光、まこと(真実)の神より
 RF RF のまことの(真実の)神[である処のイエズスを信じ奉る]。…… のまことの(真実の)神[である処のイエズスを信じ奉る]。……
イエズスは、「神よりの神 deus de deo」「光よりの光 lumen de lumine」と呼ばれています。こういう形容の起源は、『新約聖書』『ヨハネス福音書』における「世の光たるイエズス=ロゴス」と云う規定から来ているもので、この教義文に従えば、御神もまた「光」であり、その根源の光より、この世(コスモス)に訪れたのがイエズス=ソーテール・ロゴスであると云うことになります。
キリスト教だけではなく、宗教において、「光」を神とする教えは非常に多く流布しており、代表的なものはイランのゾロアスター教でしょう。この宗教では、光明神にして善の神アフラ・マズダと、暗黒と悪の神アングラ・マイユのあいだでの宇宙的闘争があることとなっており、最終的には、「光明」が暗黒に打ち勝つのですが。光(ポース)が暗黒(スコティアー)に打ち勝ったと云う表現は、『ヨハネス福音書』冒頭にも出て来ます(1:05)。また、光と闇の二元論は、仏陀、ゾロアスター、イエズスを継承する第四の預言者=救済者だと自称したマニのマニ教にもありました。
また古代エジプトの紀元前14世紀におけるエジプト神王であったイク・エン・アトン(旧王名アメン・ホテップⅣ世。在位紀元前1350―1334年)は、アマルナ革命と呼ばれる宗教的精神的変革を唱え、実行し、現在テル・エル・アマルナと呼ばれている地(イク・エン・アトンの神聖命名では、「アケト・アトン=アトンの地平」)に、新たな王都を建造し、自ら「唯一神にして太陽=光」の神である「アトン」に対する讃歌を記し、これを帝国の色々な場所に掲示(つまり岩石の表に刻んだ)したと云われています。この「アトン讃歌」の讃美表現と、ユダヤ教での『ユダヤ聖典=旧約聖書』の『詩篇』における神の讃美表現で、余りに似ているものがあること、またモーセと云う名にはエジプト語の痕跡が想定できること、『旧約聖書』に記されている、ユダヤ人たちがエジプトに居住し、遂に奴隷的状態に陥っていた時代と云うのが、このイク・エン・アトンのアマルナ革命の時期と、丁度重なっているらしいことから、「ユダヤ教一神論信仰」の起源は、このイク・エン・アトンの「アトン唯一太陽神信仰」からインスピレーションを受けたのではないかとも云われていますが、多分そうなのだと思います(「アトン讃歌」のある部分と『詩篇』の中のある詩句を較べてみますと、実にそっくりです)。
「光」が新たな世界の復活であり、創造であり、悪の暗黒に対する勝利の象徴であり、更に「意識の覚醒」の象徴でもあることは、色々な文化で知られています。『旧約聖書』において、神が最初に述べたのが「光あれ」だったと云うのはともかくとして、ユングの『自伝』で紹介されている話では、アスワンかどこかのアフリカ奥地(ナイル源流地域)にいる猿の類は、太陽が昇って来て、世界に光が満ち溢れるのを崖の上で待ち望むのだそうです。日本で「御来光」と呼んでいるものは、猿類もまた実行していると云うことです。
また、暗黒の支配する夜の闇のなかには、悪霊や妖怪や、それぞれ得体の知れぬ恐怖と悪の存在が世界に瀰漫するが、しかし夜明けの曙光と共に、それらの妖怪たちは姿を消すと云う考えは、例証は上げませんが、世界の文化で普遍的に信じられていたことです。『禿げ山の一夜』だったか『火の鳥』であったか、ストラヴィンスキーの作曲であったか、資料が手元に見つからないので断言できませんが、この曲は、そのように朝が訪れ、教会の鳴らす鐘の音と共に、悪霊などが姿を消して行くと云う情景が音楽となっていました。
また、少し話の位相が変わりますが、光の物質的実体は何かと云うことについては、古来からの経験的波動説と、アイザック・ニュートン卿が提示した粒子説のあいだで、かなり長く争われて来ました。しかし、マックスウェル・ヘルツの方程式記述よりして、光の実体は電磁場の振動であると云うことで(偏光現象がこれで説明されます)、波動説がやはり正しかったのだと確信したとほぼ同時に、19世紀末から20世紀初頭にあって、マックス・プランクの量子仮説や、アインシュタインの光量子説が出現し、それは、結局、初期量子論を通じて、やがて量子力学の体系にあって、「光」は粒子でもあれば波動でもある、と云う結論となりました。
「光」とは何か、物理学的にも実は、定かに分かっていません。実体は電磁場振動であり、また、電磁力の交換力粒子だと分かっても、分かっているのはそこまでで、宇宙の物理的構造解明が永遠に解けない可能性が無限に高いのと同様に、光は光であるとしか云えません。
そして「光」は外部にだけあるものではなく、内部にもあるものだと云うことを知らねばならないでしょう。「内部の光」、これこそ神秘主義の求める何かであるのです。それは、魂に潜む「光明の智慧」とも云える何かでしょう。
|
 Marie RA. S. et Miranda Noice Marie RA. S. et Miranda Noice ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ 1997:0331:1605 1997:0331:1605
 Marie RA. S. et Miranda Noice Marie RA. S. et Miranda Noice ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ 2000:0124:0300 2000:0124:0300
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ HAGIAI SANCTAE HAGIAI SANCTAE
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ HAGIAI SANCTAE HAGIAI SANCTAE
 Miranda et Marie RA. 1997:0331:1605 Miranda et Marie RA. 1997:0331:1605
 Miranda et Marie RA. 2000:0124:1325 Miranda et Marie RA. 2000:0124:1325
 Miranda et Marie RA. 2005:0118:0727 Miranda et Marie RA. 2005:0118:0727
[TOP] [LIST] [HOME] [THOUGHTS] [LITERARY] [MISCELLAN] [INFOR]
|