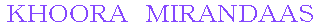
|
神秘主義とグノーシス VII |
![]()
![]() 【Gnosis Mirandaas】 【LINK】 「人は死んでどこへ行くのか?」
【Gnosis Mirandaas】 【LINK】 「人は死んでどこへ行くのか?」
![]()
![]() 【Gnosis Mirandaas】 【LINK】 「沈黙について」
【Gnosis Mirandaas】 【LINK】 「沈黙について」
![]()
![]() 【Gnosis Mirandaas】 【LINK】 「Sacrifice, あるいは世界の戦慄」
【Gnosis Mirandaas】 【LINK】 「Sacrifice, あるいは世界の戦慄」
![]()
![]() 【Gnosis Mirandaas】 【LINK】 「光と闇」 ― Sacrifice, あるいは世界の戦慄 II ―
【Gnosis Mirandaas】 【LINK】 「光と闇」 ― Sacrifice, あるいは世界の戦慄 II ―
|
|||||||||||||||||
[LIST] [HOME] [END] [THOUGHTS] [LITERARY] [MISCELLAN] [INFOR]![]()
![]() 【Gnosis Mirandaas】 [TOP]
【Gnosis Mirandaas】 [TOP]
|
Where does
Human Go after Death ?
『人は死んでどこへ行くのか?』
タイトルが「 人は死んでどこへ行くのか? 」ですが、以下の文章内
容は必ずしも、そういう話題だけに限定されていません。
とまれ、「人は死んでどこへ行くのか?」 この問いは、「人はどこから来たのか?」……つまり、誕生の前、 あるいは受精の前か、または受精卵の発生展開のどこかの過程でか、「人=わた しの意識」は、どこかから来たのか、またはどこからも来 ないで、大脳等の発生過程・展開生成過程において、構成されたものなのか、事態 は一体何であったのか、と云うことの問いです。 そういう意味からすれば、「人は死んでどこへ行くのか?」と云う問いは、「意 識」が、「構成された物質実体上の構造体」であるなら、物質実体の構造基盤が、 肉体・大脳等の分解・腐敗・解体等により、分解・解体するものだと云う答えもあ ると云うことになります。 * * * *
ここで問われていること、或いは、問うていることは、つまり、「人」とは何か
または「わたし」「わたしの主体意識」「意識」とは「何か」と云う問いに置き換
えることもできることになります。このような置き換えをした上で、その「答え」
の上で、その答えの展望において、「何処へ行くのか」「何処から来たのか」と云
う問いの「答え」が展望されると云う構造になっているとも云えます。
人間の「意識」とは何か、「主体意識」とは何か、と云う問いは、遥かな歴史の 往古から尋ねられ続けて来たものでしょう。それに対し、大まかに、呪術・宗教・ 哲学・神秘主義・科学などにおいて、「解答の試み」「モデルの構成」が試みられ て来たとも云えるでしょう。 人間の思考における「把握」において、解答・認識の展望把握と云うのは、結局 「意識における広義モデル構成」であると云うのは、実は当然のことなのですが、 こういうことも、一つの「哲学的展望・把握」なのかも知れません。他の考え方・ 立場もありえるのですが、わたしは少なくとも、他の立場とはどういうものか、納 得する理解がありませんし、構想しにくいので、このような「モデル構成」解釈で 考えるのです。 * * * *
「意識」「主体意識」「わたしである意識・主体」とは何か、と云う問いに対し
て、自然科学的なアプローチが、近年になってかなり多く試みられていると云うの
は、考慮せねばならないことでしょう。それらのアプローチについては、目下、わ
たくしは、理解するための準備をして
いると云う段階で、まだ何かのコメントを出すには至っていません。しかし、「意
識」の背景実体として、大脳内部に構成される「電磁場」をそのモデルとする解釈
は、わたくし自身も考えて来たものであり、問題は、どういう風に電磁場の物理現
象を、構造的に組み立て・モデル化して、これを、主体認識乃至経験としての「主
体意識」の構造と、どう対応させるかと云う問題になるでしょう。
私たちの意識は、複合した知覚の構造を、或る時間の幅である「このいま」にお いて、「全体として」把握する能力または現象を経験している訳で、これは、古典 的には、意識の「統覚機能」と呼ばれるものです。この「統覚」をどのように、物 理学的モデルにおける電磁場=意識のモデル化において、構成対応を提示するかと 云うことが、問題の一つの重要な焦点でしょう。 大脳における、機能局在と云うのは、一面の真理であり、例えば、言語に関係 すると考えられる大脳領野は、幾つか知られている訳ですし、記憶に関係する領野 や、知覚や運動に関係する領野、情動に関係する領野もまた知られていると云えま す。しかし、機能局在論だけでは不充分であることは、大脳生理学的にも認められ た事実です。 つまり、例えば、言語機能については、言語関係領野が、何かの理由で機能喪失 に陥った場合、その喪失の規模と様態にもよりますが、左右の大脳の片方に局在し ている機能領野が、反対側の大脳半球において、補助的に再生されると云う事実が 知られています。これは、言語機能が、大脳全体或いは少なくとも、言語関連領野 と認められた領野だけに関係するのではなく、大脳のかなり広範な領野に機能展開 されており、「専門機能領野」が機能喪失を起こした場合、代理専門機能領野が、 全体的機構によって、補償的に構成されると云う事実を示しているからです。 * * * *
大脳の機能局在論と全体論の議論は、すでに決着が付いているようで、未だに明
確には答えの分かっていない問題です。つまり、「専門機能担当性」と云うものが
どこまでのレヴェルで云われているかによって、この話は、また違った様相を呈し
て来るからです。
と云うような話は、すでに行われている一般的議論であるのですが、基本的な問 題は、やはり、「意識・わたしの主体意識」が、物質実体構造の構成の反映構成で あるのか、または独立実体であるのか、あるいは、こういう二実体構成ではなく、 物質−意識における、混合実体構成を意識現象は取っているのかと云う問題です。 これは、現在では、各人の個人的展望に依拠している訳で、「分からない」と云 う立場も当然あり得る訳で、実は、圧倒的に「分からない」と云う立場の人が多い 問題なのかも知れません。わたくし自身も、正確な処、よくよく反省してみれば、 「分からない」立場だとも云えます。……「分かっている」と云う立場なら、最初 の質問である、「人は死んだらどこへ行くのか」と云う問いに対する「答え」もす でに出ていると云うことになります。単 純に、四つに類型分離して考えてみると、次のようになります : 1) 物質実体一元論 2) 精神実体一元論 3) 物質−精神二元論 4) 物質−精神混合一元論 仏教などは、4) の類型に入る考え方をしているとも云えます。また、「物質」 とか「精神」と云うのは西欧哲学の概念カテゴリーだと云う問題もあります。「西 洋哲学」の概念カテゴリーは、そして時代によって違い、思索した哲学者ごとでも 違っていると云うことになります。 一般的には、4) の考えが基本的な出発点で、1) 2) はその極論であり、3) は、1) 2) を前提にした上で4)の立場を整理して表現した立場とも云えます。 ……わたしは「実体」と云う言葉・概念を使っていますが、4) の立場では、或いは 広義の4) の立場では、「実体」概念と云うものは使用する必要がなく、別の概念 カテゴリー、つまり、世界のモデル・カテゴリーが要請されているのかも知れませ ん。 ☆ ☆☆ ☆
そういうものとして、例えば、1) の立場でも、2) の立場でも、「階層」と云
う概念が西欧においては、存在したのだとも思えます(「階層」と云うのは、わた
しがここで云っているので、それぞれの思索においては、それぞれの用語や概念カ
テゴリーが使用されていたでしょうが、それをわたしは「階層」と云う概念カテゴ
リーで代表する、またはモデル化すると云うことです)。
1) の立場では、「意識・精神」の現象は、物質の構造における派生現象の「構 成階層」であると云うことになります。しかし、こういうモデルは、かなり洗練され たもので、この前に、「意識の世界 把握」は、「すべて意識のモデル把握である」と云う「事実原理」乃至「現象原理 事実」が認識されます。これは、インマニュエル・カントの主観の概念提唱に相当 に丁寧に表現された考えですが、こういう「現象原理事実」の存在認識は、カント 以前から無論あった訳です。 ただ、「もの自体は認識できない」と云うカントの命題は、我々の認識の一切は 外界の事象の「意識によるモデル構成・モデル把握」であると云うことの表明に他 ありません。「モデル構成・把握」と云うのは、近代科学の構造パラディグマから こういう表現になっているので、無論、こういう概念カテゴリーは、明確には二十 世紀に入ってから成立したものでしょう。 それで、こういうことを述べて、何を云いたいのか、と云うことになりますが、 それは、問題は、単純なものではない、と云う確認を、こういう形で行っていると云う ことになります。しかし、以上の散漫な話のなかで、一貫して述べていることは、 「世界把握は意識現象のモデル把握・モデル構成」 「と思える」と云う命題です。 これは、哲学の基本問題であるともわたくしは思いますし、この「命題」に対し 異議を唱える人の存在もまた想定できます。また、この「基本命題」から、「誰の 意識現象」における「把握」かと云う問題も起こって来るのであり、個人の「意識 構成」における、《同型構造性》、或いは、何故、人は相互にコミュニケー ションが可能であるのか、実は、コミュニケーションをしていると思って、そう錯 覚しているのではないのか、と云う問題が派生して来ますし、また「普遍ロゴス」或いは「超越ロゴス」と云うような概念カテゴリーが指示している実体が、 世界には、「あるのかないのか」と云う問題にまで派生して行きます。 繰り返し、問題は反復される訳で、異なる言葉・表現で、または定義形態の異な る概念カテゴリーによって、問題が、別の形に見えるような形で提起され、それに ついての思索=モデル構成が試みられると云う事態になります。 * * * *
例えば、この文章の見出しである、「 人は死んでどこへ行くのか 」
と云う問いに
対する答えは、モデル構成として、それぞれの人の世界把握の基本的態度(その類
型として、例えば、上に上げた四つの類型を採用してもよいのですし、あれとはま
た異なる「態度類型 ・ 把握類型」と云うものも可能なのです)に従って、「分から
ない」と云いつつも、かようにも構想される・モデル構成できると云う風に、或る
イメージ乃至論理構造命題が提示されることになります。
例えば、「意識・わたしの主体意識」は、世界の「物質構造構成」とは、相当な 独立性を有しているが故に、「肉体構造の機能喪失とその物質的解体・分解である 死」によっては、「わたしの主体意識」は完全には消滅しないし、解体もしない、 その結果、「孤独なる精神の世界で、永遠的なときを過ごすことになる」と云う答 えもあれば、「死後に精神主体は、〈別の世界〉に行く、その世界は、精神実体乃 至精神要素で構成されており、そこには、色々な構造があり、天国や地獄などがあ る、或いはそんなものはなく、ただ、光に満ちる〈意識の構想〉に応じた形象生 成における〈意識世界〉があるのである、と云う答えもあれば、または、様々な意 識と純粋な死後の交わりの世界に入って行き、そこには、天使や高級意識霊や、神 とも云える、精神主体があり、交わりにおいて様々な知識を得て、意識主体として の成長が継続する、などと云うモデル構成も可能なのです。 こういうモデル構成は、「空想」の類にも聞こえますが、空想か空想でないかは そのモデル構成の「実証性」に関わっていると云うことを主張したとしても、「実 証性」とは何かと云う問題があります。これも、世界のモデル構成における概念カ テゴリーであり、モデル構成に、まさに他ならないからです。 科学のパラダイムとその実証性と云う問題は、結局、「永遠に検証される仮説と しての科学」と云うモデル像を提示した訳で、「永遠の真理」などは、科学は提示 しないと云うことですし、また、科学の真偽パラダイムでは掬いとれないが、「生 きる現実・生の実存」においては、意識主体にとっては「存在が明白な事象・現象」 と云うものは無数にある訳で、反対に、光は速度上限を持っていると云う科学の暫 定真理命題などは、日常の世界把握では、出てこないモデル真理です。 * * * *
「何も分からない」と云うのが結論だ、と云う訳でもありません。
混沌の世界のなかで、無数の構造可能性のなかで、人は、自分の基本的把握態度 に適合した構造モデル真理を信奉して、その結果、無数の互いに相容れない世界把 握があり、人は互いに、sound and fury, わいわいが やがやと、自分では意味があ ると考えている命題を主張して、その全体像は、「群盲象を撫でる」と云う状態よ りも、もっとひどいものであると云うのが、世界の真実なのかも知れない、とも云 えそうですが、それは、わたしの基本的世界把握態度として、認めがたいと云うこ とです。 ロゴスの《普遍性》をどのように見積もるか、或いは、「ロゴス」では なく、「自明の理」の存在をどこまで認めるのか、と云っても構いません。私たち は、互いに、 有意味な話をしているのか、実は分からないのですし、自分自身が思考している内 容、モデル構成している事象そのものについても、一体、一貫性があるのか、また は出鱈目なのか、それさえも、「分からない」と云う可能性があると云うことで す。(後者については、まさに、そうとしか思えない人々が、或る種の場での 議論を見ていると、存在するとしか思えないので、そこからモデル構成すると「わ たくし」も、また誰も彼も、「程度の差」であって、云っていることは、出鱈目 そのものである可能性が、構想されるのです)。 「分からない」と云う可能性が分かっている、と云うことになるのですが、この こと自体も懐疑に晒されるのです。デカルトの懐疑に似ていますが、デカルトは、 彼の世界把握パラダイムのなかの或る把握態度にあった訳で、わたくしは別の存在 者であり、別の把握態度・把握パラダイムにあるとも云えます。……わたくしとし ては、答えの可能性をわたしなりに考え、構想して来たつもりです が、それは、「分からない」と云う根本認識が、また根柢にあり、到底「信念」な どともなりようがないものです。 「グノーシス (叡智・真知), Gnosis」 と 云うものは、一つの解答への飛翔的構想であるのですが、この方向に、わたくしはなお 可能性を認めるものです。 |
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ HAGIAI SANCTAE
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ HAGIAI SANCTAE
Miranda et Marie RA. 1999:0223:2344
Miranda et Marie RA. 2001:1012:2354
[TOP] [LIST] [HOME] [END] [THOUGHTS] [LITERARY] [MISCELLAN] [INFOR]![]()
![]() 【Gnosis Mirandaas】 [TOP]
【Gnosis Mirandaas】 [TOP]
|
Concernant
Le Silence
『沈黙について』
遠藤周作氏の作品に『沈黙』と云う傑作があります。新潮文庫に入っていたよう
に思えますから、未読の方は一度、読んでみてください。
これは、どういう話かと云うことは、作品を読まれると分かるのですが、取りあ えず、何故「沈黙」と云うタイトルが付いているのかの説明をします。 この作品は、日本へのキリスト教伝道の過程で起こった、或る仮想の出来事(史 実をベースにして、遠藤氏が独自に構想したストーリーです)を舞台にしており、 そこでは、初期徳川幕府によるキリスト教弾圧の姿と、弾圧される民衆、そして、 勇敢にも、死を賭して日本への宣教を試みようとした宣教師のストーリーが描写さ れます。 宣教師は、徳川幕府の政策による、日本人キリスト教信徒の「虐殺=殉教」を目 の当たりに見るのです。しかし、「殉教」は、あたかも天地も神も天使も聖なる霊も 存在しないかのように、まるで、日常的な自然のできごとであって、神や天使が関 与する必要もない、些事であるかのように進行し、生起して終わります。そこに、 何の「殉教の榮光」も、それを称える「神の祝福の言葉」も、「天使の合唱」もな い、それこそ、天地宇宙には、実は「神などは存在しないのではないか」と「疑わ せる」ような静けさ・日常性のなかで進行します。 遠藤周作氏の問題意識は、「神の不在の疑惑」と云う問題にだけ焦点があるので はありませんが、カトリック信仰者としての遠藤氏の意識において、この「神の沈 黙」と云うものは、一つの大きな主題であったのは間違いないと思います。 ☆ ☆☆ ☆
我々は翻って考えるに、「超越的存在者の沈黙」、「死者の沈黙」、「他者の沈
黙」と云う事実を知っています。例えば、最初のものの例としては、何も、キリス
ト教的な全能の人格神を念頭しなくともよい訳で、人間よりも高次な存在、「この
卑小なる我が心の苦しみを知り給い、嘉し給う何ものか」の存在だけでも充分な訳
です。ウィリアム・ジェイムズの研究の結果は、人々は、超越的な神ではなく、人
間よりも、「僅かに高次な何ものか」の存在だけで、信仰は満たされると云うこと
でした。 例えば、眼前に見る「赤」の色があるなら、この「赤」の色は、「わたし以外の 他者」には、どのように見えているのか、このことを尋ねると、答えが「ない」こ とに気づきます。「心理的反応」の類似性から、他者も、わたしが見ている「赤の 色」と「同じ色」を見ている「可能性」が高く思えるのですが、決定的には、何も 云えません。そこで、「超越的に」確認できないのであろうか、とわたくしが考え る時、そこに、「超越的存在」の存在についての疑問が生じるのです。 リルケの『ドゥイノの悲歌』の冒頭に、沈黙せる天使への呼びかけ、あるいはそ れに対する言及のラインがあったと思いますが、「超越的存在者たち」は、みな、 求める時、「沈黙」を守り、応答してくれないのであれば、「超越的存在者」と云 うもの自体が、仮構のものではないのかと云う疑問が生じてきます。 先の「赤い色」の他者とわたくしのあいだでの一致についての「超越的存在者の 保証の欠如」と云う事態は、「我々は、自己の自我の内側に、ついに閉じ込められ た存在であるのか否か」と云う問いに対し、「閉ざされた孤独の存在である」と云 う答えを確認していることにもなります。 ☆ ☆☆ ☆
これは一種の「独我論的陥穽」であるのかも知れません。勿論、「我と汝」と云
う構造性が、主観の超越論的構造機制として刻まれていますから、独我論的主張の妥
当性には、当然、懐疑があるのですが、しかし、「汝=他者」の存在の保証が超越
論的に刻まれていると云うことは、超越論的な証拠が、ここにある、そこにあると
云うような事態でもないのです。
わたしたちは、「理解者」或いは「存在の超越了解者」のいない「孤独の宇宙」 に生きてあるのか、あるいは、「超越的理解」とは、あまりにも「自然」であるが 故に、我々が「それ」を、それとして意識できないと云うだけであるのか、ここに も「謎」がある訳であり、我々は、あるいは「わたし」は、「この謎」を超越でき ないと云う事態が現前しているとも思えるのです。 「超越的存在」など仮定しなくとも、生きて行くことはできる、或いは「死者の 死後存在」など仮定しなくとも、生きて行くことはできる、と云うことも一面で云 えるのではないかとも思います。しかし、第一が、「超越的存在者」、第二が「死 者」、そして第三に「他者」を置いたように、ここで、「沈黙の事態の意味」を問 うているのは、「わたし」における「普遍的根拠基盤」と云うものに対す る懐疑が生まれるからです。 わたしの他者が生者であるなら、わたしこそは死者であるのか。 他者こそ神であれば、わたしは人間たるわたしを見出すであろう。 だが、他者が人間であるならば、わたしとは、神であるのか? そのような意味において、わたしが神であるのか。 神ともなりえる我々の存在であることは真理である。 人は、時に他者にとって、その希望、その生きる意味である。 時に恐怖、戦慄、自己の存在の意味の否定の具現でもある。 精神病理学的に、こういうことは確かに云えるし、宗教学的にもそうである。 つまる処、「根源の根拠」言い換えれば「普遍ロゴス」を、 このような問いは、求めていることになるのではないのか?
「死者たちの沈黙」と云う現象的事実あるいは、懐疑は、また別の問題の項目と
なるのでしょうが、「超越者たち」は沈黙している。貴方も、そして沈黙している
時、「わたし」は誰であり、何であるのか?
『クオ・ヴァデス』と云う小説があったと思いますが、あの作品の最後は、迫害 の嵐吹き荒れるローマを去ろうと脱出して来たペトロが、キリストの幻影を見ると 云う情景であったと思います。ペトロは確か云ったのだと思います。 「クオー・ウァーデース、ドミネ? Quo vades, Domine ?」 (主よ、いずこに、行こうとしておられるのですか?) これに対し、キリスト・イエズスの幻影は答えるのです。 「ローマへ」 我々において問題なのは、いかなる幻影もヴィジョンも、我々の前に出現せず、 また、我々の問いかけ: 「いずこに行こうとされているのか?」 と云う問いに対す る返答が、「沈黙」でしかないと云う事態でしょう。 これは、人類の文明の課題・主題とも関係しますが、答えが「沈黙」では、それ が「答え」とは、我々には思えないのではないかと云う問題です。 智慧は、喧噪のなかにはない。 智慧は、静けさと、深い心の思い、反省のなかにある。 騒がしく議論したり、断言したりしている人の側を、智慧は去る。 智慧は、荒野に住まわり、風のなかで、その智慧の言葉を語る。 智慧に出逢うことは難しく、智慧の言葉を聞くことは、もっと難しい。 それは、智慧の言葉は、それとしては聞こえないからである。 我が子よ、父の教えに耳を傾けよ。 私も、我が父にとっては、一人の子であった。 智慧の言葉は、このように、風の声に耳傾ける者の耳に聞こえ また、喧噪を離れ、沈黙の意味を荒野に知ろうとする者に聞こえる。 わたしは、こうしてタトであり、おまえもまた、タトである。 |
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ HAGIAI SANCTAE
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ HAGIAI SANCTAE
Miranda et Marie RA. 1999:0311:1108
Miranda et Marie RA. 2001:1012:2354
[TOP] [LIST] [HOME] [END] [THOUGHTS] [LITERARY] [MISCELLAN] [INFOR]![]()
![]() 【Gnosis Mirandaas】 [TOP]
【Gnosis Mirandaas】 [TOP]
|
"Sacrifice" or the Shudder in the World
『Sacrifice, あるいは世界の戦慄』 ☆☆ ☆ ☆ ☆☆
『サクリファイス, Sacrifice』と云うのは、故アンドレイ・タルコフ
スキー監督
の最後の作品で、これは一応英語タイトルであって、製作主体は、ストックホルム
のスウェーデン映画協会とパリのアルゴスフィルムですから、原題は、無論、サク
リファイス= Sacrifice, ではありません。しかし、とにかく日本語タイトルは、
このようになっています。 タルコフスキーは「悠久のロシア」をテーマにした、私映画監督とも云える不思 議な作風の人だったのですが、その監督作品の中で、ただ一つ、この「サクリファ イス」だけは、ロシアを主題にしているとは思えません。では、何を主題にしてい るかと云いますと、悠久のロシアの拡張としての「悠久の人類の故郷」が主題であ ったと思えます。この「悠久の人類の故郷」と云う主題は、スタニスラフ・レム原 作の『ソラリス』においても、已に、その基本的な形は提示されていたのであり、 またストルガツキー兄弟が脚本製作に協力した『スタルケル』においても、同様の 主題が現れます。 基本的な「主題」とは、「悠久の人類の故郷」と、「人類の魂の救済」です。 このように云ってしまうと、まことに陳腐に響くのでしょうが、タルコフスキー は、このような主題を、彼以外に誰もしなかったような方法で表現した映画監督だ と云えます。また、このような壮麗な主題を描き出すバランス能力を持っていた希 有な監督だったとも云えます。 ☆☆ ☆☆
映画『サクリファイス』の冒頭では、レオナルド・ダ・ヴィンチの絵画がスクリ
ーン一杯に現れ、ヨハン・セバスティアン・バッハの『マタイ受難曲』の中の旋回
形式のアリア(第47曲)が歌われます。
そこで、わたくしは何を云いたいのかと云うことです。 *******、*********************ですが、わたく しは些かの、或いは大いなる怒りを覚えると云うことがあります。または、怒り と云うよりも、むしろ苛立ちとでも云えばよいのかとも思います。 話の脈絡を、この文書では整合させないこととします。そこで、唐突に述べるこ とは、考えてみるに、わたくしの乏しい日本史の知識において、日本歴代の天皇の 中にあって、その首を切られ、または切って崩御した天皇はいたのか、または、死 後その遺骸にあって首を切られた天皇はおられたのかと云う疑問です。歴史的に存 在が確定しているように思えるぎりぎりの処で、一人だけ、このような条件に適合 する天皇がいるように思えます。或いはわたくしの認識間違いで、別にも、この ような条件で「死」を迎えた天皇がいたのかも知れませんが。 この天皇は弘文天皇と呼ばれます。明治以前の時代には、こういう名の天皇はい ませんでした。天皇ではなく、大友皇子と云う名で知られる人物が存在し、天智が 築いた大津朝の支配者として、その叔父大海人皇子と戦って破れ、その死に際し、 自ら首を切った、或いは死後に首を切らせた、或いは、首を切られて、その首 級は、大海人=天武の検分に供せられたと歴史に記されていたように記憶します。 或いは記憶間違いかも知れませんが。 ところで、十六世紀のイングランドは、テュードル朝の支配下にあり、この王朝 最後の女王エリザベス・テュードルは、その晩年に至り、縁戚に当たる、元スコッ トランド女王メアリー・ステュアートの処刑を命じた後、その処刑が執行された知 らせを受けて、激しく動揺を示し、廷臣たちをメアリー処刑を止めなかったが故を もって詰問します。 カトリック教徒メアリー・ステュアートは、彼女が、カトリック側により殉教者 に仕立て上げられることを恐れた、イングランド国教会首長・女王エリザベス・テュ ードルの 命令で、殉教者の榮光を剥奪されて、あらゆる記念品は奪われ、歴史の上から、そ の存在の証を奪うための方策によって、処刑人の鋭利な斧によって首を斬り落とさ れた後、遺骸は他の誰の眼にも触れないように、素早く片づけられ、用意された巨 大な鉛の棺に、落とされた首共々納められ、直ちに密封されて隠されました。 処刑されたメアリーと処刑を命じたエリザベスの二人の女王の遺骸が、奇しくも イギリス国教会の象徴的教会・王家の教会にして墓所たるウェストミンスターの地 下墳墓に納められて、墓地と地下の冷却の中で数世紀を過ぎ去って行ったのです。 ウェストミンスターの正面より向かって右手奧の内陣の地下墳墓にメアリーの首の 斬られた遺体が収まる鉛の棺が納められ、左手奧の内陣地下には、エリザベスの遺 骸を納めた棺が安置されています。二十世紀初頭に行われた地下墳墓調査で、これ らのことは判明していますが、メアリー・ステュアートの首を斬られた遺骸が収ま る鉛の棺は、十六世紀末に彼女が処刑されてすぐに納められて後、誰も鉛の密封を 破って、中を確認したものはいません。 ☆☆ ☆☆
これらが、わたくしが記す「 Sacrifice 」の物語の破片です。
人を刃物で殺そうとする時、もっとも簡単な方法は、わたくしが思うに、頸動脈 を切り開くことです。確実に素早く人の命を奪うことができます。首を切り落とす と云うのは、かなり面倒なことです。非常に鋭利で重みのある剣で、安定した状態 で一気に切り落とさなければ、通常は斬首は失敗します。 しかし人類の歴史で眺めてみると、「首を切る」と云うことに多くの文化や社会 が、明らかに拘泥したと思われる、歴然とした証拠があります。或いは「首を斬らない」ことに拘泥しました。 歴史的事実か否か知りようもなく、おそらく創作と思えるのですが、弘文の最後 を描いたある創作者は(里中満智子『天上の虹』)、最後まで忠実に付き従ってい た舎人頭に対し、自分の自死の後、その遺骸より首を切り落とし、叔父大海人(天 武)の元へと届けよと、弘文に語らせます。舎人頭は驚愕して、述べたと : 「我が 君、首を切り落とせば、再び、この世に生まれて来ることがないと云われておりま す」。弘文はそれに対し答えたと : 「朕は、再び、この世に生を受けたくない と思う」。 「人の死」、その死よりも過酷な「何かの運命」が、首を斬ることによって齎さ れるとは、いかなる意味であるのかです。クロマニヨン人たちにおいて、首だけを 特別に埋葬していた例があり、のみならず、首を集めて礼拝所とおぼしき位置に積 み上げ、礼拝していた可能性さえあるのです。 首を斬ることによって、何かの「力」が生み出され、どこからか引き出されるの でしょう。斬られた首は、単なる遺骸以上の何かになるとも云えるでしょう。「誰 にとって」の「何であるの」か、その答えを誰が知っているのかです。 自らの首を差し出すことが究極の サクリファイス であるなら、他人の 首を斬るこ とは何なのか。エリザベス・テュードルがメアリー・ステュアートから、カトリッ ク教徒としての榮光の一切を剥奪しようと意図したことと類比的に考えれば、他者 の首を斬ることは、「他者の存在の総体の意味」、その「世界総体」を剥奪し、奪 取することに他ならないでしょう。 首を斬るか斬られるかの戦いを行うとは、生と死を賭けると云う以上に、「世界 の総体」を奪い合うと云う象徴的意味がそこにあるとも云うべきでしょう。 ☆☆ ☆☆
「悠久の人類の故郷」=「我らが総体世界」よ、我らの魂を救済し、悠久の故郷
へと帰還させたまえ。我らは、「奪われた・失われた世界総体」の「回復」のため
に、我らのこの存在を sacrifice, とするものである。世界の戦慄にあって。
愚劣なる者たちの sound and fury, を棄て、 「 この言葉 」 の解釈を見出すべし。
― Marie RA. S. et
Mirandaris ―
|
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ HAGIAI SANCTAE
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ HAGIAI SANCTAE
Miranda et Marie RA. 2050:0713:1250
Miranda et Marie RA. 2001:1012:2354
[TOP] [LIST] [HOME] [END] [THOUGHTS] [LITERARY] [MISCELLAN] [INFOR]![]()
![]() 【Gnosis Mirandaas】 [TOP]
【Gnosis Mirandaas】 [TOP]
Light and Darkness
『光 と 闇』 ☆☆ ☆ ☆ ☆☆
本日の新聞を見ますと、酒鬼薔薇の名前で殺人等を行った容疑者と目されている
少年の手記に、何やら意味不明の神の名前が記されていて、その神との関係におけ
る「聖なる儀式」として、被害者少年の殺害及び遺体損傷等を行ったと云うことが
窺えると記されていました。
最初に記事を読んだ時は、些か考え込んだのですが、暫くして、別に大したこと ではないと判断しました。大したことでないと云うのは、思春期において(あるい は人間は、その一生を通じてと云うことかも知れませんが)、仮想の宇宙秩序や、 その秩序の原理などを構想・空想して、これを「現実認識」と織り交ぜると云うこ とはしばしば見られる現象だからです。純粋に自分一人の発明で、相当高度な、架 空秩序原理を考え出すことは難しいと思いますが、思春期ともなりますと、文字情 報他色々な情報がありますから、それらをモデルに、自分なりの架空秩序を構想す ることは、そんなに難しいことでもなく、また珍しいことでもありません。 モンゴメリーの小説に『赤毛のアン』("Anne of Greengables")と云うものがあ りますが、この小説の主人公アン・シャーリーは、10歳以前から、相当な自己の 内部仮想世界を構築しており、このような設定が多くの読者に歓迎をもって受け容 れられたのは、やはり共鳴する処があった為でしょう。アン・シャーリーは架空の 人物ですが、アンあるいは、作者であるモンゴメリーの少女期のような「夢見る少 女」「夢見る少年」と云うのは非常に一般的な存在だとも云えます。 アン・シャーリーの例と酒鬼薔薇容疑者少年の場合では、まったく事情が異なっ ていると云うことも云えますが、ここで述べようとしていることは、仮想秩序を思 春期の少年少女が内面において築くことは、それほど珍しくないと云うことです。 容疑者少年の場合、今日の新聞報道に従えば、少年殺害の前の複数少女の殺傷もま た、その架空秩序・何とか神への祈りと、その神との連携の証としての行為であっ たと云うことです。構想し想像すると云うのと、その構想・仮想を「現実世界」で 「現実に実行」すると云うことが、非常に大きな差異である訳です。 なお新聞記事によりますと、このような実験を行って、人間は壊れにくい存在で あるとかを日記に記していることが、「人間を生き物と考えていない」冷血心理の 証左であるなどと主張していますが、これは些かおかしい判断・決めつけだと思い ます。容疑者少年は、人に対し殺傷行為を行う前に、猫などを殺していたそうです から、これは明らかに、「生き物を生き物として認識していた」と云うことです。 ただ、わたくしが思うに、「肉体としての生き物または人間」と、「精神・意識と しての人間存在」とのあいだに乖離感があり、「透明な自己」と云うような表現に は、離人症的な傾向が見られ、自分自身についても、肉体的存在・社会的存在・精 神的存在=自我意識が、それぞれにうまく調和対応していなかったことが想定でき ると云うことです。そして、このことは思春期の少年少女においては、それほど珍 しい事態でも、またないと云えます。 ところで、長々と前置きを記しましたが、 KN さんの見解についての応答は、こ こから始まります。 ◇ し、それぞれのご意見を述べておられますが、そのほとんどが、現象的解釈に ◇ 終始しているように感じられます。私が奇異に思うのは、この事件に関して、宗 ◇ 教者からの発言がほとんど聞かれないということです。 ◇ エックハルト的な解釈でいけば、この世界は闇と光との対立で成り立っている、 ◇ であるから、今回の事件もそんな闇の勢力の一つの噴出である……ということ ◇ にでもなるのでしょうか。 [原文 par KN] わたくしは別に「宗教者」などではないと思いますが、ここで少し意見を述べて みたく思います。(エックハルトが、「この世界は闇と光との対立で成り立ってい る」と主張したかどうか、よく知りませんが[こういう考えは、カトリックでの標 準的な考え方です。神と悪魔が対立しているのがこの世界であって、人間は悪魔の 罠や悪魔が唆した原罪から解き放たれて、キリストの助けにおいて、神の救済の恩 寵に与れるよう努力すると云うのがキリスト教の考えです]、「闇と光の対立」を 特に中心軸に置く宗教と云いますと、ゾロアスター教やマニ教、そしてグノーシス 主義がそうなります)。 ところで、わたくしは、先の文書『Sacrifice, あるいは世界の戦慄』の最後に記したことですが、以下のように述べました : % 「悠久の人類の故郷」=「我らが総体世界」よ、我らの魂を救済し、悠久の故 % 郷へと帰還させたまえ。我らは、「奪われた・失われた世界総体」の「回復」のた % めに、我らのこの存在を sacrifice, とするものである。世界の戦慄にあって。 % 愚劣なる者たちの sound and fury, を棄て、「この言葉」の解釈を見出すべし。 ここで、『「この言葉」の解釈を見出すべし』と云う表現は、実は、グノーシス 主義的文書である『トマス福音書』冒頭の言葉の転用です。そして、その上の3行 で記していることは、明確ではないですが、実は、グノーシス主義的二元論に従っ て、「真の神・救済者」「我らの真の故郷を求め、故郷を見出すため、努力し、献 身せよ」と云う意味で記しているものです。 この文書『Sacrifice, あるいは世界の戦慄』には、酒鬼薔薇聖斗なる名前は全く出て来ませんが、明らか にこの事件を念頭して記していることは明らかであり、ここで、どういう扱いをし ているかと云いますと、「死よりも恐るべきものがある」と云うことで、その一つ がどうも「人間の首を切る」と云うことであるらしいと云う結論となっています。 「死より恐るべきもの・事態」と云うのは、これは、明瞭に宗教的次元での話であ り、または哲学的には形而上学的な主題と云うことになります。 我々が生きる「この世界」は、基本的に「二元論」の世界であり、「光と闇・善 と悪・真の神と偽の神=悪魔」が対立して精神的・超精神的な戦いを展開している 場であると云うのがグノーシス主義の基本的な把握です。(キリスト教も同じ様な 構想ですが、違いは、キリスト教は人間の原罪と云うものを設定しており、「人間 が光と闇のこの世に落下した」のは、「人祖アダムとヘーヴァが犯した罪の故」で あり、アダムとヘーヴァの子孫である全人類は、この罪を負っており、この罪は消 しようがなかったものを、救世主イエズス・クリストスが、神でありながら人間と して生まれ、苦しみを受け十字架上で死を味わうことにより、全人類を原罪より救 済してくださったと云う教義がある点で根本的に違って来るのです。グノーシス主 義にも救世者はいますが、しかし「人間の原罪」は認めていないと云うべきです。 人間は「根拠なく悪の世界である此の世に落下した」のであり、「真の神」が、こ のような人間を救済するために「真智=霊智=グノーシス」を開示していると云う のが、グノーシス主義です)。 「世界の戦慄」とは、酒鬼薔薇事件の背後には、日常的判断・意識では了解でき ない(形而下的世界把握では把握し難い)何かの戦慄要素があり、この事件につい て、容疑者少年の環境状況とか、生育事情・ライフヒストリーとか、生得的な何か の異常性(例えば、皮相にも、サイコパスであるなどと云う、陳腐なトートロジー 的説明)などを論じても、出来事の「本質的戦慄事態」には迫れないだろうと云う ことです。 ☆☆ ☆ ☆ ☆☆
この世が、真の神と悪魔=偽の神、あるいは善と悪の拮抗する場であると考える
時、酒鬼薔薇事件には、ナチスの所行や、スターリン・毛沢東の所行同様に、「悪
魔的位相」がどこかにあると云うことです。通常の殺人事件などの際のバラバラ死
体とは、今回の場合は事態が異なると云うべきです。それが首を切り、それに対し
儀式的損傷を与え、学校の校門に晒す目的でか安置したと云う事態です。こういう
ことは、普通は、ないのです。殺人事件と云うのは数は少なさそうに思えますが、
実際は案外あり触れているものでもあるのです。カッとなって思わず包丁を持ち出
して来て相手を刺し殺したと云うのは、それほど異常性が大きなものではありませ
ん。計画的殺人にしても、似たようなことが云えます。「単に人を殺す」こと「以
上の何か」が、この事件にはあったと云うことが、問題でしょう。そして、それが
「世界の戦慄」であると云うことです。
この酒鬼薔薇と名乗る人物(複数かも知れません)が首を切って晒したことにつ いて、「悪魔主義」と云う考えが出されていますが、「悪魔主義」とは何なのか、 キチンと考えているのかと云うことです。人を殺すことが「悪」であるとは誰が決 めているのかです。殺人にも、「善い殺人」と「悪い殺人」があると云う考え方は できないでしょうか。例えば、国家の名において、死刑と云う刑罰が現実に執行さ れていますが、これは国家が行っている、または許諾している「殺人」ではありま せんか。そして殺人者は、結局、刑の執行を実施した刑務所内の死刑執行者たちで あると云うことは自明のことのはずです。 悪魔主義は、「悪を認め推進する超越的存在」を、自分たちの神として崇拝しよ うと云う宗教でしょうが、純粋な悪魔主義は、その信仰する神=悪魔が、信者を裏 切り悲惨な目に会わすと云うことが論理的には出て来ますから、これは一種のマゾ ヒズムかニヒリズムであると云うことになります(絶望主義とでも呼べばよい意味 でのニヒリズムと、もっと強靱な哲学的ニヒリズムの両方において)。俗流の悪魔 主義は、悪を為すことで、より力ある超越存在である悪魔=神の恩寵を得られると 云うことで、これは悪魔にそのような誠実性を求めていると云う矛盾を除外して考 えると、充分筋が通っている考えだと思います。しかし、結局の処、わたくしとし ては、悪魔主義には矛盾があり、なおこれを信奉しようとする人々は、マゾヒズム かニヒリズムであり、更に、「真の悪魔」の謀略に惑わされている可能性があると 思います。悪魔主義も、心理分析や、いい加減なライフヒストリー分析などでは解 明し難い、「世界の戦慄」がその裡に含まれていることが考えられます。 そこで酒鬼薔薇犯罪者については、色々な状況的事情があったとしても、その行 為、特に儀式的行為(本日の新聞で知った処では、猫を殺したこと、少女たちを殺 傷したことなども、すべて儀式の予備段階と解釈できるので、これも儀式に含める ことができるでしょう)については、世界の戦慄の要素がわたくしには感受できる と云うことです。ナチズムが何故、旧ドイツ第三帝国で人々に受け容れられたかに ついては、エーリッヒ・フロムの精神分析的な分析がありますが、「自由からの逃 避」とすれば、人々をして「自己責任」を放棄させたものは何であったのかと云う 疑問が起こります。宗教的次元で考えれば、これこそ、人間の魂に潜む悪魔の要素 の発現であり、また「実体としての悪魔の勢力」の人類の歴史と社会への干渉が存 在したとも云えるでしょう。 「実体としての悪魔」とは、一体どのようなものなのか分からないのですが、そ れが実体として存在し、聖トマスが云うように、「善の欠落」が「悪」であると云 うような消極的現象的発現ではないことは明らかだと思います。「悪魔」が、それ ぞれの人の心・精神に内在していることは、これは間違いのないことで、問題は、 このような内在する悪魔の現実世界での発現の様式でしょう。政治家や官僚や企業 の経営者などの行動に、この内在する悪魔の発現が存在することは明らかなように も思えます(また一般大衆・庶民の心にも、この内在する悪魔が作用しており、色 々と理不尽で非合理的な行為を唆しているとも云えます)。 それでは、酒鬼薔薇事件において、「悪魔」の活動はどのように顕現し作用して いたのかと考えて見ますと、恐らく一般に云われているように、現代の日本の社会 の様態や、義務教育の中での子供の置かれている立場、子供や教師や大人たちの描 き出す錯綜した行動と心理の模様の中に悪魔の作用と発現があったことは否めない と思います。容疑者少年の内面心理について云うなら、悪魔を信奉していたと云う より、悪魔に「憑依」されていたと云うのが、ことの真相のような気もします。そ して、このような「悪魔の憑依」と云うのは、ある意味でありふれた・普遍的な現 象だと云うことも忘れてはならないと思います。 つまる処、この世に悪魔が存在し作用していると云うのは、宗教的には事実であ り、悪魔が単一で、複数いたとしても互いに秩序を構成していると云う証拠もあり ません。つまり、この世は複数の悪魔の勢力と、あるいは複数かも知れない神の勢 力、真なる神の相争そう、混沌とした戦いの場であると云うのが正解であるように も思えます。 容疑者少年は、思春期における世界構想の中で、善なる神の存在を充分に知るこ とも受け容れることもない状態で、或る悪魔の勢力に精神を憑依されたと云うこと が、ことの宗教的(グノーシス主義的)解釈でしょう。この場合、容疑者少年の心 の中では、まさに、この世が複数の善や悪が相争そう場、または悪の複数勢力が相 争そう場であると云う認識があったようにも思えます。 「存在の総体・世界総体」を奪い合うとは、このような事態であり、弘文は歴史 的に見れば、ほぼ間違いなく天皇位に即位しているはずが、自己の内乱を正当化し ようとする勝利者天武、またはその皇后讃良=持統天皇の意志により、天皇である 本質を剥奪され、逆に、弘文に首を切らせた天武側は、弘文及び大津朝の存在総体 の意味を剥奪し無化しようとしたとも云えるのです。十六世紀のイングランドにお いては、斬首刑と云うものは決して珍しいものではなかったのですが、イングラン ド王位を要求したカトリック教徒メアリー・ステュアートの首を切った後、その遺 体を密封し、一切の記念物を残すことも禁じ、更にはメアリーが住み、そこで斬首 された城を、数年後には解体して消し去り、記念として残ることさえ許さなかった エリザベス・テュードルの行ったことは、イングランド国教会の首長にして女王た る自己の「世界総体」を維持し、同時に、カトリック的世界を代表したイングラン ド王位継承権主張者メアリー・ステュアートの「カトリック的世界総体」を奪取し 剥奪し、これを無化すると云うことを意味したのでしょう。 首を切り、切った首の頭蓋骨で酒杯を造ると云うことは、世界の色々な文化で行 われていますが、これは呪物としての乾し首などと同様に、相手の「存在の意味・ 世界総体」を剥奪すると同時に、剥奪した世界総体の持つ「霊的エネルギー」を我 がものとしようと意図したことではないでしょうか。 ☆☆ ☆ ☆ ☆☆
酒鬼薔薇事件の容疑者少年の記したとされる文章を信じるとすれば、容疑者少年
は離人症的であり、「自己の世界の不在感」を感じていたことになります。このよ
うな「世界=自己総体の不在感・非在感」を補うものとして、今日新聞が報道して
いた、仮想の神の恩寵が望まれ計画され、他者人間の生命を奪うことで、またその
首を切り、損傷を意図的に与えることで、自己の「存在世界総体」の不全感を補完
したと考えるのが妥当ではないでしょうか。猫の虐殺辺りから始まって、少女たち
の殺傷、そして年下の(恐らく「劣る者の象徴」としての・存在意味を当然奪って
よい対象としての)少年の殺害と遺体損傷において、容疑者少年は、相手の「存在
世界・存在意味」を剥奪し、自己のものに加え、首を切ることにおいて、ほぼ全体
的な被害者の「存在世界総体」の剥奪に成功したとも云えるでしょう。この首を晒
したこと、犯行声明文を残し・送ったことについて、自分の行為を自慢しようとし
たと云う解釈があるようですが、行為ではなく、被害者の存在世界を奪うことによ
って自己の存在世界が豊かになり、仮想の悪魔である神に対する義務が遂行された
ことを誇示・明示しようとしたのではないでしょうか。「透明な自己」云々の文書
送付の動機としては、「自己の存在世界の充実・補完(進行途上であり、完全には
成功していないのですが)」を声明し、捜査陣の誤解を解くためであったと考える
のが妥当と思えます。
わたくしが、「Sacrifice」で述べようとしたことは、悪魔が相争そう「此の世」 における「存在世界総体」の奪い合いにのみ眼を向けるのではなく、起こっている ことが、「存在の意味世界・実存世界」の剥奪の戦い、または相互疎外化の事態に 対し、悪魔の作用と悪魔の憑依を自覚し、自己の内部の悪魔をも自覚して、「人類 の悠久の故郷」への帰還を可能にする「真智=グノーシス」を、いまこそ知るべき であると云うことです。外部の悪魔の作用や憑依を見分けると云うことがグノーシ ス(智慧)であり、更に重要なことは、私たち内部の悪魔の存在を痛切に自覚する と云うことが、また本質的なグノーシスであるのです。 酒鬼薔薇聖斗なる者は、余所事ではなく、私たちの存在の根元・実存において、 私たちの精神の内部にも潜む者であると云うことの自覚が必要でしょう。どこかの 社会不適応のサイコパス・ソシオパスか何かの異常欠陥人間が、異常な事件を起こ した、と云うような事態の把握では不可であると云うことです。容疑者少年の脆弱 なる精神などと云ってみても、その前に自己の精神の脆弱さをこそ、反省すべきで しょう。学校教育荒廃論や現代日本社会破綻論や、共同体論への問題の還元も、根 源的反省なければ、単なるその場しのぎのたわごとでしょう。 酒鬼薔薇がではなく、私たちが、そして私が、どうこの世界にあって生きて行け るか、生きるかが、問われていると考えるべきでしょう。この世界は戦慄に満ちて いるのです。そして、私たちは、この「戦慄の世界」のただ中に生きて実存してい るのです。私たちは謙虚になって、「グノーシス(霊智)の真の神」に対し、私た ち自身を、「Sacrifice」として捧げ(それはつまり、この悪の諸勢力の相争そう此 の世において、私たちを此の戦いにあって捧げると云うことを意味します)、自ら と、この共同世界=広義人類世界の隣人たる処の人々の・「人類の悠久の故郷」へ の帰還をもたらすよう努力すべきでしょう。 アンドレイ・タルコフスキーは、悠久のロシアの現実の歴史が、悪魔と悪魔が相 争うがごとき、恐るべき残酷なものであったことをよく理解していました。しかし 戦慄的な悪の跳梁跋扈するロシアにおいて、タルコフスキーは、その自然の美にお いて、あるいは同じことなのでしょうが、「異教的な救済」において、「希望」を 抱くと云うことを信じていたのだと思います。 映画『Sacrifice』において、タルコフスキーは、核戦争の起こってしまった世 界の中で、無神論者であった主人公の・元シェイクスピア劇俳優だった男をして、 世界を救うため、自分を犠牲にしますので、神よ、世界をお救いくださいと云う、 切実な祈りを捧げさせます。この時、男は、顔を上に向け、中空のある一点に、恰 もその「神」がいるかのように必死に祈るですが、タルコフスキーはここでカメラ の場所を特別な位置に設定します。つまり、男が祈っている対象の神がいると想定 されている空間の或る点に、実にカメラを置いて、男を上から見下ろす形で画面に 映しだし、男の祈りの姿を示します。 この時、実は映画を見ている観客が、男の祈っている対象の「神」の位置に来る ことになり、カメラとスクリーンを通して、男は、映画の観客すべてに、世界の救 済の祈りを捧げている形になります。よく考えてください。男は、あるいはタルコ フスキーは、結局、映画を見ている観客、すなわちすべての人々に向け祈りを捧げ ている訳で、このことは、人間個人が、その心・精神の中に含む「善の神の破片」 に向けて祈っていることを意味します。人間の心の中には、多様な相矛盾する悪魔 と、善なる神の破片が存在するのであり(エックハルトが「心の火花」Funken der Seele とも呼んだ)、タルコフスキーは、「世界の救済」のためには、貴方たちの 心の「神なる火花」で、世界の事態を反省しなければならない、と訴えているのだ と思います(このメッセージは、『サクリファイス』の前の映画『ノスタルジア』 においても、或る狂人の主張として広場で述べられています)。 私たちは、悪のこの世界にあって、悪魔が自己の内外に存在することを自覚し、 しかし真の神の救済をこそ信じ、我々を「sacrifice」として、この善と悪の戦いに あって捧げねばならないと云うことです。酒鬼薔薇事件において、「自己の責任」 を感じた人がどれだけいるでしょうか。自分に関係のない異常人間がやったことで あるとか、自分にも状況次第で、ああいうことが起こったかも知れないが、ともか く他人事であると云う考えの人が多くはないでしょうか。教育の頽廃だとか、社会 の堕落だとか、体裁のよい、もっともらしいことは幾らでも云えるでしょう。 ☆☆ ☆☆
この世界は、「戦慄の世界」であるのです。無論、善美なるものも多数存在しま
す。けれども、「透明な自己」とか、世界からの疎外とか、自分に恩寵を与えてく
れる仮想の神の存在とは、「世界の戦慄」として、まさにわたくしたち自身の課題
に他ならないでしょう。善と悪の交錯するこの世界にあって、自己の「存在世界総
体」は、これは真なる神において築いて行くものですし、満たされない人々には、
むしろ救済のための「犠牲」にこそ、我らはなるべきでしょう。脅迫と迫害の前、
屈したとしても、『神』は、赦しを与えてくださる『真の神』であるでしょう。
縱令、僅かなことであっても、自己満足や他者への顕示以外の場面で、私たちは自ら
を「sacrifice」として捧げるべきであると云うことです。
― Marie RA. S. et
Mirandaris ―
|
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ HAGIAI SANCTAE
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ HAGIAI SANCTAE
Miranda et Marie RA. 2050:0719:2325
Miranda et Marie RA. 2001:1013:0151
[TOP] [LIST] [HOME] [PROFILE] [THOUGHTS] [LITERARY] [MISCELLAN] [INFOR]![]()