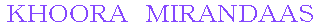
|
グノーシスとキリスト教 |
|
|
| グノーシス主義とキリスト教 II |
[LIST] [HOME] [END] [THOUGHTS] [LITERARY] [MISCELLAN] [INFOR]![]()
|
|
Fancies
of Religions and Gnosis Veritas

『宗教の妄想とグノーシスの真理』
『宗教の妄想とグノーシスの真理』
Partie I
|
― 前文 ―
本文書の起草においては、様々な状況やときの符合が背景にあるとも言える。長年にわたり、私たちの考え観察し、判断して来たところでは、「人格唯一絶対神」を世界や人間の創造者とする「ユダヤ教・キリスト教・イスラーム教・エホバの証人」等は、「妄想誘発的宗教」と言えのではないかとも思える。また「思える」のではなく、歴史的・思想的に確認できる「事実」であるとも言明できるのではないかと考える。 これに対し、「仏教・儒教」等は、むしろ「正気の覚醒」または「社会倫理の常識的理解・実践」を目指す宗教であるとも思える。キリスト教等について、「妄想誘発性」は「事実」ではないかと述べたが、無論、キリスト教やイスラーム教の信徒は、「妄想誘発的宗教」という名指しに対し、率直には同意しないであろう。しかし、ここ最近、「キリスト教」を否定するサイトの文章と、非常に強い論調で、キリスト教の信仰論を肯定するサイトの文章を読み、前者の「否定論」があまりにも皮相的であり、「宗教の真理の叡智結晶」を無視しているように思える他方、後者の「キリスト教讃美文章」のあまりな妄想性というか、非論理性に驚いたと云うこともあるのである。 以下の文書では、「宗教の妄想」とは何かを論じたく思うが、ここではキリスト教の教義構造の私的な考察を通じて、妄想的教義とはどのようなものか、吟味を試みてみたく思う。「グノーシスの真理」については、最後の段階で「正気」とは何かの試行的な考察と共に述べたく考える。 I 人間尊厳の曙光思想の成立と展開 宗教はもとより「論理性」ではなく、「信仰(Pistis)」をその教えや生活の基底に置いており、共同体の構成原理つまり「共同体規範(ノモス, Nomos)」が、同時に、「世俗慣習・法」と「宗教的慣習・法」の両方の意味を、古代社会そして中世社会においては、持っていたという事実がある。そのことは、『新約聖書』において、ヘブライ語の「トーラー(律法)」に対する訳語として、「共同体規範」を意味するギリシア語「ノモス」が使われていることからも分かるのである。「宗教」は、その発生と展開、そして人類社会における機能的意味としては、比較文明論的には、共同体の構成と存立、維持そして展開の「基盤規範原理」と密接な関係を持っているものである。 「宗教の真理」とは、「人が人であること」の無限に果てしない「希望と理想」のイデアルにおいて、螺旋的進化上昇して行くところに、その「真実の結晶」が開在するのである。「人」と「神あるいは超越者」の関係は、垂直的絶対的「超絶超越」関係にあるのではなく、人は「神性あるいは超越性」の「余韻」をその魂に持つ者として、地上の物象と上天の超越の中間に、ニーチェがイロニカルに暗示したように、「宙吊り」になっている存在である。この「宙吊り」状態を、救済に与ることのできる「希望的可能性」として見るか、「超越者」から無限の距離を隔てた中空に、立脚する足場なしに「空しく」ある「神経症的絶望性」として見るかで、「宗教の真理性」と「妄想性」のあいだの埋めようのない懸隔が生じるのだとも思える。 古代ギリシアの文明は、野蛮状態より展開して、高度な論理性や芸術的創造性に到達したのだが、それでも、「人間の理解」をめぐって、古典ギリシアはなお「野蛮」に留まっていたとも云える。古代ローマの文明は、高潔な共同体の理想と個人の克己の精神を育成する高度な文化へと成熟して行ったとも云えるが、しかし、紀元の最初の数世紀においては、それは古典ギリシア同様、「人間の存在意味」に対し野蛮状態にあったとしか云えない。他方、キリスト教は、歴史的に省みれば、ヘレニク文化のシュンクレティズムのなかにあって、「人間の尊厳と平等」を説いた「新しい時代の思想」を教義的に継承した「世界宗教の一つ」として、ヘレニク文明の後を襲った西欧文明の文明基盤宗教として勝利したとも言える。 「人間の尊厳と平等」を説いた「人類史の画期的曙光思想」は、紀元前後において、ユーラシア大陸の東西にあって、平行して出現し、このような思想原理を共同体規範原理とする社会・文明が展開している。ヘレニク文明は、西方キリスト教において、西欧文明にこの人間の尊厳の原理思想を伝え、他方、東方キリスト教において、ビザンティン文明・ロシア文明へと、この曙光思想を伝えた。 インド亜大陸においては、仏教、ジャイナ教が、人間尊厳の思想へと到達し、アショーカ王は、人間の存在の尊厳と平等の教えを帝国の統治の根底原理であると声明した。ヘレニク文明は、東西の文明交流を促進し、中央アジアから西域に広がった(グノーシス宗教)マニ教は、砂漠の民の「人間家畜説」という過酷かつ野蛮な文化原理を啓蒙して、人間性の尊重の原理へと導いた。イスラームの自称「平和の教え」は、マニ教が啓蒙し教化し善導した文化基盤の上に、その帝国の「専制宗教」を広範囲に流布させたので、マニ教は、キリスト教とイスラーム教の成功の谷間で、歴史的にその果たした榮光を忘却されたが、文明史の事実として、マニ教が歴史に果たした成果は、今日再認識されつつある。 中国大陸においては、諸子百家の時代を経過して、儒教、墨家、楊家、老荘思想において、人間性の尊厳があらためて確認反省されたのであるが、更に、道教と、道教の延長上にシュンクレティスムとして受容された大乗仏教諸派が、「人間の尊厳の曙光思想」の啓蒙において大いに意味を有したとも云える。正統キリスト教教会の教義制定闘争と共に、追放されたネストリウス派等は、西アジアからインドを越え、中国にまで伝道を行い、マニ教は、イベリア半島から西域・中国にまで亘って、その「聖なる教え」を説き、ミトラス教は、ブリタニアから、地中海世界、西アジア、更に仏教の一形態を取ってインドへ布教し(あるいは、原始仏教は、ミトラス教とのシュンクレティスムで、小乗・大乗という新しい展開を果たしたのだとも思える)、そしてパミール高原を抜け、西域を越えて、中国の大乗仏教としての「弥勒信仰」となる。 紀元の前後にあって、その思想の萌芽を生成晶化させた、この「人間の尊厳と平等の曙光原理」は、およそ五乃至六世紀の経過において、ユーラシアの西と東の果てまで、その光明思想原理を展開し流布し、一つの熟成の頂点を達成する。キリスト教の救世主イエズス・クリストスの誕生年を元起とする「西暦」の「始源時間点」は、決して、西欧キリスト教の「紀元第一世紀の始まり」ではなく、東西の諸文明にとっての「紀元の開始世紀」だとも云えるのである。人類の「人間の尊厳原理」の文明的画期は、いずれにしても、西暦の紀元とシュンクロナイズしているはずである。 II シュンクレティスムとしてのキリスト教の成立 さて、私たちは、このように萌芽生成し広大なユーラシアの諸領域にその救済の光明思想を伝播させた「人間の尊厳の曙光思想」の宗教全体の歴史や、それぞれの共同体内部での相互的な機能意味を考察する余地は目下のところないため、代表的に Case Study 的な位相から、西欧社会の共同体基盤原理ともなった「西方キリスト教」の宗教としての「真理」と「妄想」の生成と展開の様態について考察を試みてみたく思惟する。 キリスト教の文明論的成立状況とその「教義」生成と展開の歴史について考えるとき、そこには、三つの主要な文明の共同体ノモス原理が関係していたことが明らかである。第一は、西アジアの「人間家畜説」文明のなかにあって、「契約と義」の人格的絶対唯一神を信奉したヘブライ文明のユダヤ教の宗教基盤がそれであり、第二には、人間の尊厳を、野蛮的文化の迷妄より「四界同胞的」平等思想へと錬成した古典ギリシア・古代ローマの文明的到達の成果、つまり、ギリシア・ローマ哲学とペルシア・インド神話の出逢い・思想的混成の所産としてのヘレニク・シュンクレティスム宗教原理基盤がそれであるということになる。しかし第三に考えねばならないのは、古代ローマ黎明期にあったと似たような「森の文化共同体」を森林のなかの散在する集落に築いていた、後の西欧文明の中核となる人々とその共同体文明倫理基盤がそれだと言うことである。 後に西欧文明の文明基盤原理思想となる「キリスト教」の宗教的真理の結晶化の生成起源は、西暦一世紀乃至二世紀において、地中海世界にあって(主にパレスティナ及びシリア、アナトリア半島にあって)存在したと考えられる「原始キリスト教団(原始エクレシア)」にあると考えられる。これらは、ある幅を持った多様な人々の構成するエクレシア(会衆・教会, ekklesia)であり、彼等は「救済の教義(救済原理と規範ノモス)」と「人間の尊厳の曙光思想」、そして救済の原理規定に基づく「原始祭儀」を持っていたと考えられる。ここからキリスト教は始まっているのであり、このような原始キリスト教団の起源問題を尋ねると、彼等キリスト教会衆が持っていた、二つの大きな「起源神話」に遡行するとも云える。 二つの大きな「起源神話」とは、簡略に言えば、一つは、「キリストの贖罪としての十字架刑と死と、そして死よりの甦りにおいて、復活と新生の救済」を唱えたとされる「聖パウロス神学」であり、いま一つは、聖パウロスが「人として死に、神として復活し、永遠の命と神の愛をその身をもって立証した」と宣明した「救世主キリスト」の「人間的言行」についての「イエズス神学」である。パウロスの説く救済の神学、人間性の尊厳原理は、イエズス神学における救済の教えとその人間尊厳原理とは、微妙に食い違いがあるのであり、それは、原始キリスト教団内部にあっても、整合的な統一が困難であるほどの大きな溝のある食い違いであったと考えられる。 「イエズス神学」は、「ナザレのイエズス」と原始キリスト教団が呼んだ、「救世主たる人」の謎に満ちた言行から導かれる「宗教的真理の教え」である。他方、「パウロス神学」は、イエズスはキリストが地上で取った仮の姿に他ならず、人が自己を犠牲として共同体(人類共同体)の個々人の救済のため死するとき、「死」は超越され、復活のイエズスこそは、神なるキリストであり、人は自己犠牲を通じて共同体の個々人の救済原理を開示でき、その最高の見本がキリストに他ならないという思想である。キリストは死を超越して復活し、すべての人がまた同様に、「死」を超越して復活の「永遠の命」に与れることの「保証」として「歴史的証拠」として、その「神話的できごと」は成立し展開したと聖パウロスは説いた。 イエズスは、人間の尊厳の曙光思想を説いた、偉大な人類の教師の一人だったのであるが、パウロスの神学においては、イエズスは人として生まれ、その自己犠牲において、人類に救いの道を示し、みずから、最初に復活の榮光を実現し、「神となった」キリストに他ならないのである。歴史的に考えれば、人間イエズスが、犠牲の死において「霊的に復活」し、神キリストになったということなのだが、パウロスの神学は、「復活の救済者・神なるキリスト」の福音の恵みから、その宗教的教えが始まっており、パウロス神学では、「神キリスト」が人間イエズスの姿を取って、復活と愛と永遠の命の真実を身をもって実践し証明したことになる。 従って、キリスト教の「復活思想・贖罪教義・永遠の救済と命の教え」はパウロス神学に主要な起源があるとも云える。しかし、ここで最初に、キリスト教は、紀元一世紀乃至二世紀に存在した「キリスト教会衆のエクレシア」がその源起であったという事実を振り返る必要がある。「パウロス神学」の「復活の神なるキリスト」は、二つの機軸神話の一方の極なのである。そしてもう一方の極には、パウロスの個性豊かな教牧書翰の数々に明確に概念的に表明されている「救済の原理思想」とは、また異質な、それだけに言語化や教義化の困難な信仰神話があったと言うべきである。これが、「人間イエズス神話」とも呼べる何かである。 III キリスト教における二つの矛盾する信仰原理 「人間イエズス」が歴史的に実在したのかどうか、なお明らかであるとは云えない。聖パウロスについては、教牧書翰の作者は歴史的に実在したのであり、それは、福音書記者たちが歴史的に実在したのと同じぐらいに確実だとも云える。しかし、歴史的な「人間イエズス」の存在については、前世紀より今世紀にかけてのあらゆる史的イエズス解明の試みにも拘わらず、それは今日にあって、反対に、ますます不確かになって行ったとも云えるのである。とはいえ、原始キリスト教団が持っていた、「教え」の二つの起源神話の一方が、「イエズス神話」であったことも事実であり、イエズス神話は、原始教会の宗教儀礼を根拠付ける一方の源泉でもあったのである。 パウロスの神学は、人間の尊厳の平等性の曙光思想を表明していたと云えるが、理論的であったパウロスに対し、神話のイエズスは、その神話的言行を通じて、聖パウロスの「人間尊厳思想」の更に高みを開示する「教え」を内含させていたとも云える。原始キリスト教会は、「日常的・常識的な経験真理開示としてイエズス神話」を持っていたと言え、他方、「理論的抽象的な救済思想としてパウロス神話=神学」をもまた持っていたと考えられるのである。どちらが先行するのか判断し難いとも云える。それは、イエズス神話におそらく非常に長い、悲惨の経験・実存の経緯が先行したことが想定できると同様に、パウロスの理念的神学にも、パウロスに先行する救済思想原理の長い歴史があったと考えられるからである。 キリスト教の濫觴にあった「原始キリスト教団・エクレシア」の信仰は、以上のような二つの「神話」にその教義の基盤を依拠していたのだということが重要である。パウロス神学の復活の神キリストと、永遠の命と福音の教義からは、次の第一の教義構成が出てくると考えられる。他方、「苦しむ義人、世のため自己を犠牲にした人間イエズスの神話」からは、同様、次の第二の教義構成が出てくるのだと考えられるのである。
パウロスの神学では、キリストの処刑の「意味」は、超越者たる神に対する人間の「原罪」の「贖罪」であり、また、十字架での苦しみにおいて死を迎えたればこそ、キリストは「復活のキリスト」として甦り、永遠の命の存在をみずから立証したのだとされる。イエズス神話においては、イエズスは具体的な個々人の生活の苦しみや矛盾に対し、救済を実現し、或いは祈る存在としてあり、イエズスの十字架での刑死は、この世に人間の尊厳を説く教えを実現し、それがかなわなくとも、自己の命の犠牲を通じて、教えを宣明することが目的であったと云える。パウロスもイエズスも、それぞれの「真理の教え」を福音伝道するように弟子達に命じるが、パウロスの福音を受け容れない者は、永遠の命に与れることなく無に落下する。他方、イエズスの福音に従わない者は、人間尊厳の原理を受け容れない者であり、「人は人にとって狼である(Homo lupus homini)」という野蛮思想の水準に留まるのであり、彼等のあいだに、「天国=神の国(Basileia Theou)」は実現しないのである。 原始キリスト教エクレシアには、パウロス神話神学とイエズス神話神学が並立して、シュンクレティスムとして存在したとも言え、その原始エクレシアの「救済の教え」は、二つの主要な神学のあいだで、揺れ動きがあったとも、両方の神学要素を含む故に、教えに「矛盾」があったとも云える。合理性的に反省すれば、パウロス神学とイエズス神話神学のあいだの教えの亀裂は、埋めがたい矛盾なのだが、エクレシアの「信仰(ピスティス, Pistis)」にあっては、祝福と救済の祭儀が、両者を非言語的・非論理的次元で、一つに宥和していたとも言え、あるいは、パウロスが述べたような理論的神学を、その「教え」としては定式化していなかったのだとも考えられる。 原始キリスト教エクレシアの「教え」が含む、大きな二つの対立的様相を持つ矛盾、つまりパウロス神学とイエズス神話は、紀元一世紀後半乃至二世紀になって、彼等が「グノーシス異端」と称した、新しい宗教運動が活発となり、原始キリスト教団の「神話神学」を、彼等の「教義神話枠」として援用することによって、原始キリスト教団のエクレシア教義の理論的曖昧さが摘剔されたことで、初めて矛盾として意識されたのだとも考えられる。原始キリスト教エクレシアは、祭儀と祈りにおいて、パウロス神学とイエズス神話を象徴実践的に統合していたのであり、それら両者が論理的矛盾状態にあるとは明確に意識していなかったのだとも思える。 IV キリスト教における『福音書の成立』と内部矛盾 原始キリスト教エクレシア(または、その一部の諸派)は、紀元一世紀中葉より後葉にかけて、イエズス神話を系統的に記述し、首尾一貫した神話とするため、『福音書』の文書記録化を進める。こうして、『マルコ』、『マタイ』、『ルカ』の三福音書が構成されたと考えられるが、何故、福音書を造る必要があったのか、また各福音書における「イエズスの生涯」記述の極端な偏り、つまり、イエズスの「公生活」と呼ばれる僅か二年ほどの期間の言行が神話的、比喩的に語られるだけで、イエズスの一生の伝記としては、明らかに不完全なものを作成した理由は、どこにあったのかという疑問が起こる(また何故『福音書』は、コイネーギリシア語で書かれ、ヘブライ語やアラム語では書かれなかったのか、という疑問もある [*] )。これに対し、『Q』が「公生活」における言行しか記録していなかったとのだという資料的制限があったかも知れないが、では、『Q』はどこから来たのかと言えば、これは、原始キリスト教エクレシアの祭儀の根拠神話資料であったとも想定されるのである。 原始キリスト教エクレシアの人々は、イエズスという神話的人物について、歴史的存在者としての事実資料を持っていなかったか、元々必要とせず、イエズスはあくまで神話的人間であったという可能性がある。歴史的にイエズスが存在したのかどうか、かつて『ナザレのイエズス』という文章で(本サイトの『 Religio et Verum 宗教と真理 II 』に所収の文書「ナザレのイエズス」)、「人間イエズスの歴史のなかでの結晶生成」ということを述べたが、仮に事態がそうでなかったとしても、歴史的人間イエズスを原始キリスト教エクレシアは必要としなかったのだとも云える。『Q』は、イエズス神話の一つの根幹にある「イエズス神話神学」の教義書であり、イエズスの神話伝記を記した福音書記者たちは、すべて『Q』を当然のごとく前提したのだと云える。 「福音書」の成立は、しかし、イエズス神話神学だけに依拠する訳には行かず、パウロス神学へと連続し、パウロス神学の真理性を予めに立証・預言するものでなければならなかったとも云える。ここに、『福音書』内部の記述の矛盾や、『福音書』相互のあいだの記述の食い違いが生成し、かつそれらが容認された事情があるというべきである(内容に食い違いのある四つの「福音書」が何故最終的に「正典」として認められたのか、その根拠は、パウロス神学とイエズス神話の混成という事実にあるのだとも云える)。イエズスは、人間の尊厳を説き、人の平等と地上での神の王国の実現を語ったのであるが(それが「イエズス神話」の教えだったのである)、パウロス神学の人間の原罪と、神キリストによる贖罪という教えとの調和を図るとき、『福音書』のなかにおいて、イエズスは、人間として描かれる他方、神としても描かれるという齟齬が発生したのだと云える。 すべてを「赦そうとした」イエズスに対し、「罪の追求」を語り、天国(神の王国)への救済の条件を語るイエズスは、場面ごとでの意味の違いを指摘しても、同一人間の言行としては一貫しておらず、十字架刑を前にしたイエズスの恐怖と人間的弱さの描写は、イエズスがキリストであり不死の神であるなら、神またはキリストは人間をペテンにかけているのか、という疑いになるが、イエズスの弱さは、「イエズス神話」の本来の姿であり、他方、「復活のキリスト」は、「パウロス神学」からの挿入要素であるとすれば、矛盾は生じないのである。 「パウロスの書翰」を軸に、もう一つの軸に、「福音書・使徒行傳」を置いた原始キリスト教エクレシアは、明文化され、思想が鮮明となったが故、思想解釈において、論争を始めたのだとも云える。元々、パウロス神学とイエズス神話には相容れない矛盾があり、原始エクレシアは祭儀と祈りにおいて、「救済」を求めていたのであるが、グノーシス主義思想を初めとして、対抗救済宗教との対決を前にして、またローマ帝国の迫害を直視して、教義の矛盾を止揚し、「合理的教義」への統一的な教義化の必要があったのだと云える(それはまた、キリスト教がローマ帝国の「国教」となったこととも密接に関係している)。紀元四世紀のニカイア公会議(CE325年)、それに続くコンスタンティノープル公会議(CE381年)、エペソス公会議(CE431年)、カルケドン公会議(CE451年)等、相次ぐ公会議で問題となったのは、例えば、ニカイア公会議では、「イエズスは人か、神か」という問題があり、アタナシオスの説と、アレイオスが代表する「イエズス人間説」が対立するが、パウロス神学からすればキリストは神であり、イエズス神話からすれば、イエズスは人であるという矛盾を、教義的論理的に整合決定したのだとも云える。 このようにして、紀元4世紀から5世紀にかけ、キリスト教がローマ帝国の国教の地位を獲得するのとほぼ同時に、「公会議」という形を持った、教義公開決定集会が複数行われ、敗れた者を「異端」として追放するという原始カトリック教団の方針が決まる。 原始キリスト教エクレシアは、この時代より原始カトリック教会へと「権威」を持って組織構成されるのであるが、この後の中世初期での西欧文明の擡頭と、キリスト教の受容、更に、中世における幾段階もの教会組織の再編成や、十二世紀から十三世紀にかけてのアリストテレス・ルネッサンスによる、「教義」の精緻な構築や、ネオプラトン・ルネッサンス、宗教改革を通じてのキリスト教の多様な展開と内容の深化は、いま取りあえず措いておくとして、キリスト教エクレシアの基本教義における、「矛盾」と「非合理性」の根拠を、二つの起源神話、つまり、「パウロス神学」と「イエズス神話」に、以上求めて、概観してみたのである。もとより、パウロス神学内部においても矛盾が存在し、イエズス神話は、それ自体、伝説の面が強く、祭儀の根拠付けのために話が捏造もされており、必ずしも合理的一貫なものではない。しかし、この二つの起源神話のあいだの解離が、僭越にも、「宗教の妄想性」と呼んだ、「キリスト教の妄想信仰神学」の源泉にも当たるのである。
V 宗教・信仰の非合理的教義の共同体的存立根拠 「不合理故に我信ず」と云ったのは、中世のニコラウス・クザーヌスだとも云われているが、これは元々聖アウグスティヌスの著書のなかの言葉、またはテルトゥリアヌスの文章中の類似した表現から生まれたとされる。キリスト教の「信仰項目・教義」は、合理的には納得できないが故に、「我はこれを信じる」という意味に通常理解されているが、キリスト教信仰ではより積極的な意味を込め、「神への信仰に自己を賭ける」つまり、そもそも人間理性では理解できない森羅万象の不可能的な謎と、人間実存の根柢的な暗さ・矛盾から、実存の企投として、非合理的信仰にみずからを投げ込むという「決意行為と思想」を象徴した言葉とも解釈される。 しかし「不合理故に我信ず」とは、あくまでキリスト教の「非合理的教義」に対する実存の企投の意味であって、道端で出逢った野良猫がキリストであり神である可能性も、不可能なことではなく、そのようなことは信じがたい・不合理なことだと思えても、実存の企投として、野良猫の前に平伏し、猫を祈祷し崇めるような行為を推奨し、信仰根拠を与えるようなものではないのは無論のことである。「ナンセンスな行為・思考」と、「キリスト教的な実存の賭けの対象となる神秘的不合理性」はどこで分かれるのかという問題も起こる。これについては、先に述べた二つの「神話的信仰原理」の矛盾のキリスト教的止揚として規定された、「正統教義」に準拠する「理性的不合理命題」に対し、キリスト教徒は自己の実存を賭ける・企投するのだと言えるであろう。 「不合理故に我信ず」ではなく、「伝統的教義であるが故、不合理であっても、信仰する」という言表がより妥当とも言える。このキリスト教徒の実存企投は、慣習化されるにつれ機械的なものとなって行き、パウロスの書翰には明白に読みとれた「死と無を賭けて、キリストに信を寄せる」という実存の最高次の企投、生と死、永遠のいのちと滅びの賭けの緊張感は喪失されて行ったことになる(無論、死を前にしたキリスト教徒の最後の神への祈りにおいて、この実存の緊張は、ひととき生彩を帯びるとも云えるが)。こうして、「実存の企投の真剣さ・賭としての自覚の緊張」がなくなったとき、キリスト教の非合理的・神秘主義的信仰や教義は、「正統教義であるが故に、異議を差し挟めない教義」、文字通り「不合理故に、教会権力の支配の基盤にとって重要な神秘主義的教義」とも化したのだと考えられる。通常の理性では理解できないことを、どう納得すればよいのか、ここには「実存の本来性の希求における限界状況的な企投」の側面は失われ、「通常の理性」で「理解できない」からこそ、「キリストの聖なる福音」なのだという詭弁的な合理化が行われているとも言える。 人間の理性にとって理解できないことは、「神の叡智」の次元の話である。この話は、理性の限界の象徴暗示として理解できる。しかし、何が「神の叡智」の命題で、何が「道端の猫は神でない」という判断の規準なのか、キリスト教が社会の文化慣習(ノモス, nomos)として定着したとき、キリスト教教義の多数の非合理的・神秘主義的命題は、「文化の自明前提」として、思考すること、疑問を抱くことさえ、「無意識的抑圧」の対象ともなったと考えられる。これは、どの文化、どの社会、どの宗教でも起こり得ることで、宗教とは元々、質問を許されない、謎の自明命題体系だとも言えるのである。それは「何故、人間は死ぬのか」とか「世界の存在の根拠は何か」というような、理性的に回答できない問いに対する、文化的社会的な「既定回答」のシステムで、これが弱き個人と、共同体の脆弱性を補完する文化社会の「紐帯原理」だとも言えるのである。 VI キリスト教信仰の非合理性と妄想誘発性教義 キリスト教徒にとっては「公理的真理」あるいは、無前提な「信仰真理」として受け取られる基本教義において、非キリスト教者からすれば、端的に評価すれば、妄想か非合理的信念または神秘主義思考としか考えられない「教義的真理」が存在する。これらは、初期キリスト教の諸公会議で教義論争として問題になったものも含め、キリスト教内部では、「相対的説明」が行われ、新規入信の信徒や入信希望者を、暫定的に説得するが、最終的に「神秘・秘蹟(mysteria)」に留まり、これらの非合理的教義が真実のところ、何を意味しているのか、理性では最後まで整合的な見通しが得られない。 また、このような「非合理的信仰」を教義の根柢に置き、信徒への無条件の帰依を要請するとき、信徒一般において、「迷妄・妄想」に対する理性的判断力の明らかな低下を招来するとも考えられる。「奇蹟」を公然と認めるキリスト教では、日常生活のなかでも、何が奇蹟で、何が奇蹟の錯覚か迷妄か妄想か、一般の人には判断が付かないのであり、聖職者が、伝統やその場の社会的政治的状況を背景に、「奇蹟」の真贋を決定するが、このような宗教が優勢して文化の基盤となっている社会では、一般の人の「理性的批判力」の低下が齎されると云っても差し支えないのである。以下に、キリスト教の「基本的教義」または基本的思想であって、妄想思考か、神秘主義思考の産物としか通常は理解できないものを列挙して、何が妄想で非合理的かを試論的に考えてみる。キリスト教は、かような教義を無前提真理公理とする限り、「妄想誘発性宗教」という限界にあるというべきであろう。なお、これらの教義・基本思想は、それぞれ密接に関連し合っていて、一つを不思議でないと判断し受容すると、他のものも、同じように妥当と思えるような構造を持っている。
[1]「三位一体教義」 「神・キリスト・聖霊」が、本質(ousia, substantia)を一つとする「唯一の神」でありながら、位格またはペルソナにおいて、三体に分かれてあるという教義であるが、「唯一の神の三つのペルソナ」である以上、「三体に分かれている」という表現も不適切であろう。しかし、この教義は、いかに理性的・合理的に考えても、意味が不明であるというか、理解を超えている。しかし、以下に述べる、やはり「妄想的教義」を真理とすると、この教義に対し、疑似合理性が出てくる。
[2]「キリスト贖罪論」 A)イエズス・キリストは人か神か キリスト教を、ユダヤ教やイスラーム教から明確に区別するのは、先の「三位一体教義」と、この「キリスト贖罪論」教義である。イスラーム教においては、イエズス(キリスト)は、「偉大な預言者」ではあるが、「唯一神」の位格の一つではなく、のみならず「唯一神」であるともなっていない。またユダヤ教においては、イエズスは「偉大な預言者」とも見做されるが、最終的には「偽メシア」であって、神の御子でも、神自身の分身的存在でもない。イエズス・キリストはあくまで「人」である。キリスト教においては、かくして、解決すべき諸問題が起こる。キリストは人であるとすると、どのような位格の人か、神ならばいかなる意味で神か、人と神の中間または両在ならば、キリストの本質は何なのか、これは初期公会議の主題であり、初期異端論争の中心主題でもあった。 キリストが人か神かが問題になるのは、先に述べたように、キリスト教に固有の問題であり、キリスト教の妄想思考の原型がここにあると云ってもよい。最初の頃に述べたように、「パウロス神学」と「イエズス神話」の原始シュンクレティスムにおいては、キリストは神であるのか人であるのか曖昧であった。「神であるキリスト」と「人であるイエズス」が存在し、イエズスの自己犠牲において、イエズスは「神キリスト(theos Khristos)」となり、ついには「神の息子(Hyios Theou)」、そして「神自身(Theos Autos)」と見做されたのだという解釈も可能である。『新約聖書』を見るとき、イエズス・キリストは人として、神として登場し、更に、三位一体の聖霊もまた、それが「何であるか」は、『福音書』の記述では、或る程度輪郭の合理的に理解できる何かだと了解できる(とはいえ『新約聖書』の記述からは、聖霊が三位一体の一位格で、神と同質な存在であるとは、「直接には」出てこない)。 しかし、「福音書」の記述をまとめ、キリスト教の信仰を体系的なものとしようと試みたとき、「パウロス神学」と「イエズス神話」のあいだの調和をどう求めるかは大きな問題となった。パウロス神学とイエズス神話そのものが内部的に矛盾した位相を持つので、益々、この調和を確立するという課題は困難なものとなる。パウロス神学によれば、キリストは「律法」を棄て、「愛」をもって神を説き、みずから人類への愛のため、十字架上で苦しみを受けで殉教し、それによって「復活」の初子となり、人類を「罪の棘=死」より解放する道を開いた救世主であるということになる。 B)キリスト・イエズスの受難は何であったのか 他方、「イエズス神話」はキリスト・イエズスの受難は伝えるが、イエズスは対立するユダヤの勢力のあいだで翻弄され、罠に嵌って弟子ユダの裏切りに出逢い、十字架刑で殉教する。しかし、ゲッセマネの園でのイエズスの祈りは、「死と拷問への直面に恐怖し苦悶する弱き人間」の姿を活写しており、このイエズスの姿は、後の「雄々しいキリスト教殉教者」の姿と比べれば、信仰に揺れた挙げ句、やむを得ず殉教を選ぶ、「情けない信徒」の姿にも映じる。十二使徒の頭ペトロスがイエズスを三回否認することには、歴史的に納得の行く説明が与えられているが、イエズス自身のこのゲッセマネの園での苦悩・苦悶については、矛盾あるいは不整合を指摘する声はあまり聞かない。 イエズス・キリストがどれだけ深い肉体的苦悩に出逢ったか、精神的実存的苦悶に直面したか、その感動的な情景描写として語られている。しかし、天の父に「この苦しみの杯」を遠ざけてくださいと祈っているのは、人間イエズスではなく、神の子キリストなのだと考えると、ゲッセマネの祈りも、十字架での磔刑の苦悶も死も、すべて茶番にも見えて来る。多くのグノーシス諸派が採用した「キリスト仮幻説(Docetism)」がむしろ理性的な考え方に思える。ゲッセマネの園の前あたりで、人間イエズスから神の子キリスト(神の霊)が分離し、人間イエズスは苦悶し、十字架上で受難したが、神の子キリストはその受難に同伴はしていたが、「受難しなかった」では、「イエズス神話」と「パウロス神学」が分離したままであり、キリスト教として成立しておらず、そのため『福音書』は「分離はなかった」という前提で記されているように見える。 パウロス神学では、キリストの受難によって、「罪の棘」より人間が救済される可能性が生まれたのであり、それは「罪=原罪」よりの救済の可能性をキリストの受難がもたらしたという主張である。パウロス神学に沿えば、キリストは本来、神の子であり、世界が生まれる前から存在した人間を越えた霊で、あらゆる霊的存在(諸天使)よりも高い位置にあり、それはキリストが十字架上での受難により、人間の罪を愛において赦す道を開いたためだとなる。パウロスはキリストは神と同一存在であるとは述べていない。グノーシス文書とも言える『ヨハネ福音書』が、キリストは「先在のロゴス」であり、万物はキリストによって成立し、ロゴスが原初、神の傍らにいたと述べているが、「神」は定冠詞の付いた「ho Theos」であるに対し、ロゴスは定冠詞のない「theos」で、両者が同じ存在であるとは明示的には主張していない。 つまり、「三位一体」は『新約聖書』の記述からは直接には導かれない。しかし、三位一体を暗示する表現が複数あるのであり、福音書記者たちは、三位一体を可能的前提として聖書の文言を記しているようにも見える。 C)受難によって何が「贖われた」のか……贖罪論(1) さて、何故このように、イエズスが人であるか、神であるかが問題となるかと云えば、キリスト教の神学・救済論は、パウロス神学に準拠すれば、「キリストが十字架で受難した結果、キリストは復活の初子となり、人間は罪の棘から解放され救済され、復活する希望が生まれた」とされるためである。「罪の棘」とは「死」であり、ユダヤ人であり、ユダヤ教の教養に満ちていたパウロスにとって、キリストの受難で、人が「死から復活」する救済の可能性が生まれたことは、人間の創造、アダムとヘーヴァの創造以来の大事件なのである。 何故なら、人間が「死ぬこと」となったのは、アダムとヘーヴァが神の命令に逆らって、智慧の樹の実を食べたからであり、神はこの「罪」に対する報いとして、アダムとヘーヴァに「死を定めた」からである。パウロスは「復活の初子(ういご)」としてキリストは死から甦って復活し、更に、自分パウロスも、間もなく黄泉にくだり、その後、キリストに続いて「復活」するであろうと云う期待または信仰・信念を持って、教牧書翰の一つを記している。パウロスはまた「生ける神の手中にあることは恐ろしい」ことであるとも述べているが、パウロスがキリスト・イエズスを救済者として宣明し、命を賭けて宣教に生涯を費やしたのは、アダムとヘーヴァの「罪の贖い」がキリストによって行われたという「福音」を世界に伝えるのが目的であった。 人間が地上において「死」の定めにあることは、『旧約聖書』的、従ってユダヤ教的・神話的には、アダムとヘーヴァの初原の「罪」に淵源があった。ユダヤ教は、人間の「死」をこのように神話了解したが、「死後の生」や「天国での甦り」は基本的にはユダヤ教の思想にはなかった。人を「死から甦らすの」は、神御自身か、神が選んだその特別な代理人=預言者だけであった。『旧約聖書』のエリヤとエリシャが、この例外的な代理人で、エリヤは『旧約聖書』の記述では、火の戦車に乗って、生きたまま「天に昇った」ともされている。 しかし、パウロスの伝えた福音は、「誰でも」キリスト・イエズスを信じる者は、キリストの愛によって、「復活の秘蹟」に与れるというものであった。ここから出てくる「合理的」結論は、キリストは「恒久的な神の代理人」であり、従来の預言者とはまた別の特殊な存在であるということである。過去のイスラエルの預言者で殉教した者はいたが、誰もキリストのような偉大な奇蹟を行った者はいなかった。奇蹟とは、「死」から人間を解放し、アダムの「罪」を帳消しにしたということである。 D)受難によって何が「贖われた」のか……贖罪論(2) パウロスの神学が述べているのはここまでの筈である。キリスト教の「贖罪論」と「三位一体論」からは、なお相当な距離があると言える。さて、『旧約聖書』を読めば分かるが、ユダヤ人は伝統的に、何かの罪を犯したとき、その罪に対する報い、或いは罪の解消のため、ある種の罪については、「犠牲の動物」を神に献げて、いわば神と「取り引き」する形で、「犠牲の動物(多く、子羊であった)」を殺して、その「血」を神に献げ、ときに自分たちの食用にはしないということを示すため、犠牲の動物を火で焼き尽くして、「罪の贖い」とした(この犠牲動物を焼き尽くして神に献げることを「燔祭」と云った)。 このユダヤ人の文化儀礼としての「犠牲動物」を殺して神に献げ、「罪の赦し」を得るという意味の「贖罪」概念をパウロスの教えたキリストの十字架刑と、その結果の「死の罪からの解放」に当て嵌めてみると、キリストが犠牲の動物で、キリストが殺されることにより、人間の「罪の解放=贖罪」が成立したのだとも解釈できる。キリスト・イエズスが「世の罪を除き給う神の子羊(Agnus Dei, qui tollis peccata mundi)」と呼ばれるのは、キリストが「犠牲の子羊」だという解釈を裏付けるのだという考え方が可能である。 しかし、重要なことは、キリスト・イエズスがユダヤ人の伝統の「犠牲の動物」に該当するのかどうかではないはずである。(このように、何かに対し犯した罪を解消するのに、物品、生物、貴重品を提供するというのは、世界中の文化で存在する罪のあがないである。神に対し、その怒りを宥めたり、人間の犯した罪を償うため、動物の犠牲を捧げるというのは、何もユダヤ人だけの慣習ではない)。ここで重要なことは、「死」が人間にとって「普遍的事態」であるという認識と、その死を「罪の棘」として、神話的解釈されていた「人間の罪」を、キリストが「愛による自己犠牲」で、結果的に解消し、贖罪を行ったということである。パウロスが「原罪」を明確に述べているかどうか確かには分からないが、「すべての人の復活」の可能性=救済を、キリストの愛の犠牲の結果として福音したことは事実である。 しかし、パウロスが小アジアにある諸都市の教会に向けて精力的に手紙を送り、反論していることは、パウロスが説いたような「復活の救済者」は小アジアやギリシアの太母神信仰の地では、非常に一般的に存在し、エレウシスやキュベレーの「秘儀」に与れば、「永遠の命・復活の命」がまた得られるという信仰であった。つまり、ユダヤ教の伝統では、「死後の甦り」は大いなる奇蹟であったが、地中海の森の文化と太母神の信仰世界では、それは新規な教えではなかったのである。パウロスのこのような、キリストの愛の犠牲による、「死の罪の解消」と云う思想そのものが起源を、ギリシアや小アジア、パレスティナの太母神信仰に負っている可能性もある。 パウロスはアダムとヘーヴァの犯した罪が、「死」をもたらしたのだと、神話的に「原罪」を暗示してはいても、キリスト教における「原罪」の教義規定までも踏み込んでキリストの贖罪を述べているとは考えられない。キリスト教の教義では、受難によって、「人類の原罪」が贖われたことになるが、「原罪」の観念はどこから起源したのか、パウロス神学には、明白には含まれていなかったと思える。
[3]「原罪」 A)原罪の起源 それでは「原罪」の概念はどこから起源したのか。私たちには目下、明確な答えがない。というよりも、この観念こそキリスト教固有の「妄想観念」にも思えるからである。どこかで飛躍と、神秘主義的思考または妄想的思考が入っているとしか思えない。「原罪」とは、「私たちは皆罪深い存在である」というような軽々しい気分的概念ではない。また、自己の「罪深さ」を自覚してキリスト教に入信したというのも、そもそもキリストが十字架で受難した結果、人類の「原罪は贖罪」されているので、論理的には整合性がない。 キリスト教の「原罪論」は「贖罪論」とセットになっており、これはまた「三位一体教義」とセットになっている。アダムとヘーヴァは神の命令に背き罪を犯した。これはユダヤの神話規定である。アダムとヘーヴァが犯した罪は、「全人類の罪」となり継承され、その罪は「神に対する裏切りの罪」であった。贖罪を取り引きとする考えからすれば、「罪が大きければ大きいほど、贖罪の犠牲は大きなものでなければならない」。小さな罪なら、鳩を犠牲にすればよい。しかしもっと大きな罪なら、子羊や子牛を犠牲にしなければならないであろうし、更に大きな殺人の罪などだと、成熟した雄牛を十頭とか相手に贈り、贖罪を願わないと釣り合わないであろう。 アダムとヘーヴァの犯した罪は、「神に対する裏切りの罪」であったが故に、この世のいかなる物資・財産・貴重品をもってしても、「贖罪」の犠牲としては不十分なのである。そもそもこの世のすべての生物も物質もすべて神が創造した神の所有物であり、アダムとヘーヴァの生命も神の与えたものであった。「人の原罪」に対する「贖罪」は、この世の何をもってしても、それが「神への裏切り」である以上、釣り合うものはない。ただ一つ「釣り合うもの」は、「神御自身」である。償い難い「人の原罪」を贖うことができるのは、ただ神のみであるとも云える。しかし、罪を犯したのは、人であって神ではないのである。 B)無限の原罪と贖罪の至高性 「人の原罪」を赦し、贖うためには、それが神に対する罪である以上、神かそれに対等なものが罪を購うか、またはみずから贖罪の犠牲とならねばならない。しかし、この存在世界で神に匹敵するものは存在しない(神は「唯一神」であるが故に)。にも拘わらず、キリストの愛による犠牲によって、「人の原罪」は贖われた。逆に言えば、キリストは神と対等な者であり、神御自身であったと考えれば、神に対する至高の原罪が、至高の神がみずから贖罪の犠牲となって十字架上で苦悶したことにより、まさに「人の原罪」は赦され、贖罪は成立したことになる。以上に比喩も含めて簡単に、人の犯した「最大・最悪の罪」を贖えるものは、もし贖罪の犠牲で罪を贖うならば、「最高・最善の犠牲」が要請され、それは「この世の限界を越えた」神御自身か、それに匹敵する位階の犠牲者であらねばならないと述べたのである。これがキリスト教の贖罪教義の「筋道」であるが、ここには合理性的に考えて越えがたい飛躍の思想・妄想か、神秘の思考があると云わざるを得ない。 しかし、この「至高・最悪・最善」の飛躍思想において、キリストは神であり、神と同格の存在であるという要請が出てくるのであり、またこの要請の「疑似合理論理」が組み立てられるのだとも云える。他方、ユダヤの伝統的存在原理では、神は「唯一の神」であるので、もしキリストが神と同格の神であるなら、キリストもまた「唯一の神」であって、その限りない「無限の愛」の故に、人間を苦しみと罪(原罪)から救済するため、みずから「人間の肉の身」に生まれ、人間として生きて、人間として、「人間を代表して」十字架上で受難を受けたと云うことになる。 『新約聖書』の記述においては、イエズス・キリストは、人であるのか神であるのか、いずれとも決め難い姿で現れていることを先に述べた。人であるとして記述されている文脈と、神として記述されている文脈が混在し、両者が繋がっている場合もまたあるのである。イエズスは「福音書」において、神を「父(Abba, Pater)」と普通呼ぶ。他方、それに相応するように、キリストの称号は、「神の息子(Hyios Theou)」であり、「神の御独り子(Monogenes Theou, Unigentis Dei)」とキリスト・イエズスは福音書記者によって呼ばれている。『新約聖書』においては、キリスト・イエズスは、「人」と「神」の二つのテクストで表現され、更に、「神御自身」であるかどうかは不明なまま、「神の息子・御独り子」として、神に準じる「神性」を備えた者としてテキスト的に記述されてもいる。 C)キリスト・イエズスの本質 キリスト・イエズスは一体何であったのか。何であるのか。その本質(ousia, substantia)は何なのか。『新約聖書』は複数の解釈を許容するのであり、キリスト教エクレシアは、4世紀から5世紀にかけての複数の重要な公会議において、懸案のキリストの「本質」の議論を行ったとも、議論の結果としての「公同教義」の宣言を行ったとも云える。ニカイア公会議で宣言され、コンスタンティノープル公会議でその「真理性」が保証された「三位一体教義」は、キリストの本質を教義宣言すると同時に、「超歴史的な人間の原罪」の措定と、神御自身の位格としての神キリストの贖罪の犠牲死において、「至高・最悪」の人間の原罪を、神御自身がその「至高・最善の意図」において、自己自身に対し、自己が人に代わって贖罪することで、人間の原罪よりの解放を実現したのだ、と云う公同教義であった。 この「原罪」をめぐる救済の論理は、自分の尾を噛むウーロボロスの蛇のような構造を持っており、のみならず、この蛇は自分の尾を飲み込んで行き、やがて蛇自身を蛇が飲み込んで、蛇の存在は消えるというような不可解な、または神秘主義的な論理(または疑似論理)構造だとも云える。しかし、このようなウーロボロスの原初的永遠的な円環の疑似論理において、「三位一体」教義は意味が明らかとなり、「原罪」の規定と、救世主キリストの自己犠牲=贖罪と、イエズスが「イエズス神話」で語ってはいたが、意味が曖昧であった「永遠の命(zoe aionios)」や「天国(神の王国, Basileia Theou)」が、ギリシア哲学の論理における形而上学的な「意味開示」として規定されることにもなったのである。こうして、キリスト教の「公同教義」が成立したと云える。 D)原罪の解消可能性と至福直観の福音 しかし「原罪」とは本来何であったのか。楽園におけるアダムとヘーヴァの存在は元々神話であったし、智慧の実を食べたが故に、「死の運命」を負う結果が齎されたというのは、典型的な「死の現象的事実性の根拠神話」である。哲学的には、「死の事実性」に対する「気づき=意識化」がアダムとヘーヴァに起こったことだとも云える。「智慧」とは自己反省思考でもあり、自己反省のないときには、死が事実として存在しても、それは意識にとっては「無」であり、人は「不死」である。しかし智慧の覚醒と共に、人は不死ではないという「現象的事実」の自覚・意識化が成立するのであり、アダムとヘーヴァの神話はこのように理解すべきものであり、ユダヤ人は実際にそのように理解していた。 他方、キリスト教の「神学」は、半面でギリシア哲学の思索を継承したキリスト教的哲学思索を持っていたのであり、この位相からは、「原罪」はまた別の実存的意味を持っていた。人は自己反省力を持つことで、動物や植物や、その他地上の万物とは別の存在者ともなる。自己が「死における存在」であるという自覚は、存在の了解と共時するのであり、このように「死と存在を了解する」者は、ギリシア哲学においても、オリエントの思想においても、或いはユダヤ教においても、人と神だけであった。人と神の違いは、人は「死すべき者(thnetos)」であるに対し、神は「不死なる者(athanatos)」であるという点にあった。 「原罪」は「死」を介して人と神を分離あるいは仲介するなら、キリストの贖罪の死において、神と人のあいだの懸隔=距離は解消されたともいえ、人は神との「原初の親密な関係」を再び回復したのだとも云える。あるいはキリスト教の実際の福音のありようから云えば、「回復への可能性の扉」が開かれたのであり、開いたのはキリスト・イエズスであり、神御自身でもあるキリストが、「愛(agape)」故に人と神のあいだの距離を架橋したのだとも云える。「原罪」は人と神とのあいだの超歴史的な断絶・実存的距離であったとすれば、原罪の完全な解消は、13世紀の聖トマスの「至福直観」がその到達の至高点となるのは論理的帰結だとも云える。神と人のあいだの「無限の距離」であった原罪は、キリストの贖罪死において、解消可能な実存の可能距離内部の事態となり、これがキリスト教の「救済」の真意であり、「福音」の開示する真実なのであるとも云える。 |
|
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ HAGIAI SANCTAE Miranda et Marie RA. 2004:0809:0044 |