以上の三つの項で述べてきたキリスト教における、「三位一体教義」、「贖罪教義」そして「原罪教義」は、以上の概観からも分かる通り、密接に関係し合っており、相互補完的とも、三つが一つとなってキリスト教の「真理=福音」の意味が織り出されているとも云える。どれか一つに欠落が生じれば、公同の教義は破綻するであろう。或いはキリスト教の教義体系は極めて微妙かつ精緻なガラス細工にも似た何かなのかも知れない。このように個々で見れば意味不明であるにも拘わらず、全体として補完的構造を持って「意味を織り出す教義」というものは、それ自体が驚くべき奇蹟だとも人間の叡智の結晶だとも表現できる。
しかし、自分で自分自身を、尾から初めて飲み込み、やがて消えるウーロボロスの蛇を比喩に出したように、以上のような構造がキリスト教の教義構造だとすれば、それは何か円環的に反復されている、「同義反復的」な誤謬(詭弁論法)の壮麗なシステムのようにも見える。見えるだけではなく、実質において、キリスト教の教義は、原罪・贖罪・三位一体という仮構の要素が「三位一体の車輪」を構成し、空中で回転しながら詭弁論法で自己自身を支えている妄想の体系ではないのかという疑いが起こって来る。
[1]「神の唯一性とは何か」
キリスト教の基本教義そのものの構成・組み立てにおいて、私たちは「妄想性」を見出すのであり、その典型的な思考のもつれを、キリスト・イエズスが「神であって人である」という三位一体教義の成立機構に垣間見ることができるのである。無論、キリストは「人ではない」「三位一体の神である」という教義公理の反論があるであろうが、『新約聖書』テクストはキリスト・イエズスが神であるか人であるか、概念的・明示的にはそれを示していないのであり、三位一体は、聖書的根拠を持つとも云えるが、同時に、聖書の記述構造は三位一体を否定しているとも云えるのである。肯定しつつ否定しているとも、肯定も否定もしていないとも、或る意味どうとでも解釈可能なような構造を持っている。最初に述べたように、「三位一体」は理性的理解を超えているのであり、それは「秘蹟・秘教(mysteria)」であるが、この秘蹟は神秘思考であるのみならず、妄想思考であるとも云えるのである。
キリストと神の三位一体教義を認めるとき、三位一体は神の「唯一性」を同時に主張している。神の唯一性は、キリスト教の場合に説かれているのではなく、ユダヤ教、イスラーム教においてもまたそれは「教義」構成されている。しかし「神の唯一性」とは何なのかが理性を越えた無前提思考(公理的真理)だとも云える。「この世界」では、「或る特定のもの」は唯一のもので、他には同じものがないと云う状況は、「固有物」の存在であると理解される。例えば、エジプト(Aigyptos)という国・地域は、地中海沿岸、北アフリカのエジプトしかないのであり、エジプトは固有なもの・土地・国の名称である。「個々の人間」もまた、固有な存在であり、ある人物はその人物として他に「同じ人」はいないのであり、これが「人間の実存」の顕著な指標性であるとも云える。
しかし、神が唯一だというのは、ヤハウェという「固有名」を持つ「固有の神」はヤハウェしかいないという意味なのであろうか。多神教における神々は、人間の集団において、複数の人のなかで特定固有の人が識別されるのと同じ論理で、個々特定の神が固有な「その神」として把握されるのだとも云える。多神教の多様な神々と比較するとき、ヤハウェは「特権的な神」であり、個々の神々の「固有性における唯一性」を越えて、「超越神」としての超越的固有性=神の唯一性を備えると理解されるのであろうか。人間の世界において、特権的固有人物、例えば「王のなかの王(シャシャーン)」は「唯一」であるというのと、同じ意味において、またはアナロギア(類比)において、神は唯一と属性確定されるのであろうか。存在世界の創造神は「ただ一柱のみ」であり「神は唯一」であるというのは、理性判断を越えた主張であり、臆断要請に過ぎないのではないのか。
神の唯一性がこのように理性の疑問の対象となるのは、この場合の神が、多神教の多様な機能神や固有神ではなく、この世界を創造した「超自然的な」神であるからである。歴史的に見れば、ユダヤ人の「一神教」は、紀元前15世紀のエジプト神王イク・エン・アトンの「アトン革命(アマルナ革命)」における「唯一太陽神アトン信仰」に起源があると考えられる。ユダヤ教においては、イスラエルの預言者が宗教哲学的な思索を、この「唯一神」との「人格的・実存的関わり」において錬金したとも云えるが、神話的族長アブラハムの神も、歴史的人物と云えるモーセの神も、「固有な人間実存」との関わりにおいて、「固有な契約の神」として姿を現成していると云える。多くの多様な個別的な神々のなかから、彼らは、彼らの実存の契約の神として、イスラエルの神ヤハウェを「主」として選び契約したのだと云える。ここでは「神の唯一性」は実存を生きる具体的「個人」の実存の本来性における「汝(Sy, Du)」としての「神の唯一固有性」であり、その唯一性の起源・根拠は、個々の人間実存の固有唯一性にあると云える。人が実存の存在として一回的固有な唯一者であるが故に、実存の「汝」が固有な唯一者として現成するのだとも云える。
しかし世界創造の唯一神は、この世界と万物を創造した神であり、その存在の位階は「世界超越的」であり超自然である。そして世界超越的とは、この世界をその構成論理ともどもに越えるという意味であり、「この世の論理」はこのような超越神には適用できないということを示しているのである。「父なる神・子なる神」における「父・子」とは、人間の世界における「父子関係」のアナロギア(類比)であり、本質的には超越関係であるというのは、人間世界の父と子の関係で、神の父と子を思考することの誤謬性を言明しているのであるが、しかし、それでは「父なる神・子なる神」の「父・子」とは何のことなのか。キリスト教はみずから紡ぎだした概念を、理性的解釈することを教義的に否定しつつ、無根拠に「信仰の真理」を導入する。「根拠」は本来存在したのであるが、モーセにとっての実存要請では、モーセの神にしかならない以上、これを超越する「概念神」として、超世界的に唯一神の措定をするとき、神の超越的唯一性は、あらゆる可能性を許容可能とし、同時に反転して、何をも「意味しなく」なるはずである[*]。「実存の対者としての神」と「世界超越の唯一神」のあいだには無限の距離があり、キリスト教の信仰は、意図的にこの質的超絶的差異を無視する反理性において成立しているとも云えるのである。
|
(* 註):「神の超越的唯一性」が、「あらゆる可能性を許容可能」とするとは、「可能性」とは私たち人間にとって経験できるものは、時間と空間、状況と様態の「この世界内部」での何らかの事象についての「可能性」なのである。「神の全能性」についても同じことが言えるのであるが、「この世界」を超越して、時間・空間・状況様態も超越して、なおかつ「唯一性」という「属性」を主張できる神は、端的に「人間の経験」を超越しているのである。それは当然なことだとも反論があるかも知れないが、人間の経験認識は、ここではカント的な「先天的認識」もまた実質的に内含した意味での経験である。
先天的認識は、経験的認識における統覚自我の「意味了解」を通じて概念的な把握に到達するのであり、「超越的な神の唯一性」が「先天的真理」として超越論的に規定されていると仮にしても、それは時間・空間・状況様態把握の「経験的現成自我」の意味了解においてはじめて「何であるか」が判明するのである。神の「超越的唯一性」が啓示を通じて示され、それに対応する先天的超越論的真理認識の基盤が人間の精神に仮にあったとしても、人はこのような超越的神の「属性(essentia)」については、「想像・想定」あるいは「空想」するしかないのであり、神の超越的唯一性が神学的につまり「神の論理了解(Theo-logia)」において主張可能だとするなら、神の属性について、例えばそれは「空虚」だとか、「悪」だとか、「鳩のようである」とか、何を想定しても、「そうではない」という神学的根拠がない以上、超越神の属性について理性は何とでも想定でき主張できるということは、「あらゆる可能性を許容する」という意味になる。
なお、ここで「神学的」と云ったのは、「神の論理的了解(テオ・ロギア)」の意味においてで、教義公理を前提に、キリスト教護教的に「聖なる教え(Sacra Doctrina)」を理性によって疑似論証するロギアの意味ではない。キリスト教の神の「超越的唯一性」はこのように実質の内容が空虚となる。グノーシス主義における超越的な「上なる神・父」はこのような意味での経験理性を越えた「超越神」ではなく、個々固有の人間の「実存の対者(汝)」としての超越的救済神であり、人間の自我統覚における「先天的超越論的な神の刻印」があるとすれば、このような「神の存在刻印」に対し、個別的状況において実存的に「汝」として対し、これによってその「超越性」が理性了解される超越神である。グノーシス主義の超越霊が「先在の父」とも呼ばれるのは、人間の超越論的実存構造において、経験的統覚自我に対し、「超越論的刻印」として「先在する」と経験されるが故であるとも言える。
|
[2]「神の全能性とは何か」
『新約聖書』において、神の偉大な権能は語られているが、「超越的全能性」は措定されているとは思えない。神が「全智全能」であるとは、キリスト教の神学的規定であり、「神の全能性」はユダヤ人の宗教経験と思索から齎されたものではなく、むしろギリシア哲学の観念思索の産物であるが、その「世界超越性」の構造より、神の唯一性が持ったと同質なアポリアに直面する。原始キリスト教より一千年後の中世スコラ哲学において、奇妙なパラドックス命題としてその超越のアポリアの問題は形を取る。例えば、「神は、自分でも持ち上げることの出来ないような重い岩を創造することができるのか否か」という設問では、明らかに「神の全能性」が吟味され問われているのだとも云える。この問いに対する回答は一見、人間理性の限界を示すようなパラドックスに帰着する。そのような岩の創造が可能としても、不可能としても、どちらであっても、神の全能性に対し矛盾が生じるからである[*]。
これは「嘘つきのパラドックス」に類似した構造を持つように思える(また、「仮定されるメタ理性」の超越精神的構造解析からすれば、おそらく同じ構造思考論理から導出されると考えられる)。しかし「嘘つきのパラドックス」は云ってみれば、「名指しの形式的命題操作の不完全さ・未完了性」から生まれ出るに対し、神の全能性をめぐるパラドックスは、神の問題を実在の問題と把握すれば、それは形式的な錯誤ではなく、実体的な決定不能性の問題だということが明らかになる。つまり、神はまさに全能であるが故に、「この世界」を創造することができたのであり、現に不断の創造を継続していると云える。神の全能性からは、神が「この世界とは異なる世界」を無数に、同時に創造し不断に創造を維持していることが当然の結果として出てくる。とはいえ、神は「この世界だけを創造した」とは断言できないのと同様に、神は「この世界とは別の世界を無数に創造した」ということも、「想定」できるだけで、実体的には、このような命題は確認できない。
確認できないにも拘わらず、神がこの世界とは異なる世界を無数に創造したという命題が何故「当然の結果として」出てくるのか。それは、「この世界」が現象的に実在するからであり、この世界の実在と共時的に神が全能性を持つならば、神の全能性とは、「この世界以外の別の世界を、同時に無数に創造できる、また創造している」能力という解釈しかできないからである。神は、世界の時間的・空間的様態を、すべてにおいて決定して世界を創造したはずである。これは広義の「運命論」であるが、世界の創造とは、世界の運命の創造でも同時にあらねば、全能の神の「創造」とは云えないのである。そうだとすれば、人間が神の全能性や能力について、思考したり問いを投げかけることが「可能」だという現象的事実は、すなわち神がそのような人間の「思考の自由度」に応じて、思考の「実体化」を行い得る存在であり、神の「可能能力」は神にあっては「すでに実現している」と考えざるを得ない以上、無数の異なる運命を持つ世界は、「実体的」に存在していなければならない。
しかし、以上の考察で、神の全能性の意味と人間の思考の自由度の存在が絡まって来たように、まさに「神の全能性」のような神学的規定は、人間の自由意志の問題と関係し、この世における「悪の存在」の問題、あるいは「人間の能力の有限性と責任負荷性の無限性のパラドックス」の問題へと端的に繋がって行くのである。「神の全能性」が真理であるとは、キリスト教の神学規定であるが、これはユダヤ教やイスラーム教もまたそうなのである。「神の全能性」を真理とすれば、理性において解き難い無数のパラドックスが産出されるのである。また極論すれば、あらゆる空想・妄想が実在的基盤を付与されてしまう。逆に言えば、何でも命題として成立し得る結果が出てくるのであり、神学的「推論」として任意の命題を導出可能であり、それは結局、何をも決定できないということと同義である。「教皇無誤謬の教義」のような妄想が何故成立するのか、それはキリスト教の神学の構造から必然的に「無限の妄想」に真理性が与えられるような神学的推論が成立するためだとしか云いようがない。いかなる命題でも出てくるという、この私たちの言明をキリスト教徒は認めないかも知れないが、神は全能であるのか、全能ではないのか、実はどちらでもなく、かつどちらでもあるというのが回答である。
|
(* 註):この「岩を持ち上げる」という問題について、スコラ哲学はどう答えていたのか、記憶にないかまたは認識にないが、ここでの説明の考え方で答えると次のようなことになる。まず、「岩」とか「持ち上げる」という事物概念また行為概念は、「この世内(in-der-Welt)的」事態であり概念であるということが重要なポイントである。神の全能性が超越的に肯定されるなら、無限の可能世界が神のイデアーの構想において潜勢的に存在していることになる。これらがデュナミス(潜勢態)ではなく顕勢態としての実在となっているかどうかは私たちには認識のしようがないが、神の精神のうちにあっては、それはデュナミスであったとしても、可能実在として存在している。
そこで、「岩」とか「持ち上げる」という広義の概念は、神の精神の構想のなかで「普遍性」を持つかと云えば、持たないという答えがむしろ出てくる。つまり、「岩」とか「岩を持ち上げる」というのは、「この世界・宇宙」に固有な概念だとも言えるのである。「この世界」というとき、地球のことを云っているのではなく、全物質の宇宙や更にその彼方に物理学的に展望される多元時空的宇宙など一切も含めて「この世界」である。つまり、それらは地球や銀河系宇宙の実在の延長上で私たちの認識にかかっているからである。神の構想における無限の可能世界とは、およそ人間の精神能力の構想可能性を超絶したものが無限にあるとも言えるのである。そしてこのような、「この世界内の精神・人格である私たち」の想像や構想を超絶した無限の世界では、「岩」とか「岩を持ち上げる」というような概念が「無意味」な世界が無数にあるとも考えられるのである。「持ち上げる」という概念を考えても、これは「重力」のある世界で成立する概念である。この宇宙内でも、重力について中和しているような領域や系、例えば、自由落下運動をする系では、「重力の作用はない」ので、「持ち上げる」という概念も成立しない。また「重さ」や「質量」もこの世界内での概念である。
この世界が神によって創造されたとき、神は諸事物や運動等との関係において、神はどのように「世界と関わるか」の形式を法則的に定めているはずである。それはもし「定めていない」場合は、世界は「不定条件」を含むことになり、人間の場合は「不定条件」は与えられた状況として可能であるが、「全智全能」の神においては「不定条件項」は存在し得ないのである。従って、神はこの世界を創造したとき、すでに「岩」を「持ち上げる」という行為等との「関わりの条件」を決定した上で世界創造を行っていると考えざるを得ないのである。これは、地球上あるいは宇宙上にある「すべての岩」を神は「持ち上げることができる」という決定関係かも知れず、或る惑星にある特別な岩は「持ち上げられない」という決定関係かも知れない。後者の場合は、「持ち上げられない」というよりも、神自身が「持ち上げない岩」としてかような岩を創造しているのである。
従って、この世界に神が持ち上げることのできない岩が存在しても、それも神の意志の創造であるなら、それは神の全能性には抵触しない。他方、「持ち上げることのできない岩を創造できるか」という問いについては、「関わりの条件」において、そのような岩の存在と創造を神がこの世界に設定している場合は、「持ち上げることのできない岩」を創造できるが、「持ち上げることができない」というのは、神が具体的な姿を持つ世界を創造するために設けた「関係条件」であって、これは神の全能性には抵触しないのである。神が「意志すれば」、そのような「この世界では持ち上げることのできない岩」を「持ち上げることができる」。しかし、このような形で神の全能性が発揮された場合、「この世界は消滅して無となる」のである。この世界は、「異なる関わりの条件」における別の世界に変化するのであり、それはこの世界が無となる、あるいは潜勢態となるというのと同義である。何か循環論法のように響くが、それは神の「超越的全能性」ということの意味が通常の思考では扱い慣れない不思議な何かだからである。
喩えれば、ワーテルローの戦いでナポレオンが勝利する世界は、神の精神の無限の構想のなかで存在し得る。現実の世界の歴史では、ナポレオンはワーテルローで敗北した。神の全能の意志において、ナポレオンの勝敗を左右することは自由であるとも言える。しかし、その場合、「現実」となった世界は実在世界に留まるが、他方の世界は実在となった世界側からは無あるいはデュナミス(潜勢態)となる。ナポレオンが勝利しかつ敗北しているような世界は、実在するこの世界としては現象しない。そのような世界は神の永遠の構想のなかでは実現しているかも知れず、現象実在としても神が意志すれば、存在するかも知れない。(神が「至高善」であり「至高真理」であるという本質は、神自身の意志で変えることができるのかと云えば、これはできない。こうして神の「善の意志秩序」において展開される世界における「意志の発動」は、「善の秩序の究極状態の完成」へと向かうのであり、このような過程は「必然」である。人間の自由意志もまた、神の善の意志の影像である以上、必然の意志の展開に準拠して行くのであり、ここからスピノザの「必然」と「自由」の一致はそれほど離れていない。しかし、神は「必然」という形で自己が至高善であることを否定できないのであり、これは実は「神の全能性」の否定論拠でもあるのである。ここから宇宙は「二元論世界」であるという展望が、より実在に則した見方として出てくる)。
|
[3]「神の人格性とは何か」
キリスト教、ユダヤ教、イスラーム教においては、神は「唯一神」で「全智全能」にして世界と人間を創造した「人格神」だとされる。「人格神」とは〈神が人間のような〉自我意識を持ち、自由意志を持ち、感情と判断力を持つ存在であるということであるが、キリスト教では事態は逆で、神の「人格性」が人間の創造において〈人間に分与された〉のだとされる。『旧約聖書・創世記』には、神が「人を我々に似せて創造しよう」と述べて人間・アダムを創造する神話が描写されている。この創造神は「エロヒーム(Elohim)」で、エロヒームは両性具有だとされる(エロヒームは、女性名詞「エロー, Eloh」に男性複数の語尾「-im」が付加されて成立しているとされる)。それ故に神エロヒームは「我々」と複数形で自分たちを呼ぶのであり、原アダムは両性具有の「完全な存在」であり、アダムより「肋骨」を象徴として、女=ヘーヴァが造られることで、アダムの両性性から女性要素がヘーヴァに移ったとも考えられる。
このように『創世記』神話では、人間は「神に似せて」創造されている。「人は神の似像である(Homo imago Dei)」。従って、人間の持つ自我や意識や理性、思考力・判断力、そして「意志の自由」は神の精神が本来持っていた特性であって、このように「霊的に」神に似せられて存在するのは、この世界では人間だけであり、「意志の自由」を持つのも人間だけである。植物や動物は「生命」は持つが、また局限された形の意識機能は持つが、人間のような「霊的自我」は持たない。人間はこうして特権生物であり、地上における神の霊的代理者・この世の管理者としての役割で神に創造されたとも云える。他の動物や植物が「霊の光」を持つかどうか、少なくともユダヤ教、キリスト教、イスラーム教の正統教義では、それは否定される。キリスト教では、西欧中世の聖フランチェスコのような自然の生物に霊的に親しかった聖人もいるが、聖フランチェスコは例外とも云え、彼は異端として断罪される可能性がむしろ高かったとも云える。また歴史的に、聖フランチェスコの信仰を継承するフランシスコ修道会は、ローマ教皇庁と思想的に対立するスタンスに立って来た。
ギリシア神話に登場する様々な神々は、人間同様に怒ったり、楽しんだり、愛したり、憎んだり、嫉妬したり悩んだりする、非常に「人間的な神々」の一面を備えている(「一面」というのは重要である。古代ギリシアの神々は、それでも「神」であり、恐るべき面・ヌミノーゼ的位相をまた備えているからである)。ギリシアの神々は、意志において、思考・判断において、感情において極めて人間に似ており、この理由としては、神々と人間は同じ性質を共有しているためだと云える。「神」と「人」は、「不死」であるか「可壊」で「死すべき者」かの違いが本質的である。死ぬことのない神々(athanatoi theoi)は、「恐るべき存在」の面を持つのである。ギリシアの神々における、この人間との「類似性」は、人間が自己の属性を神々に投射した結果だとも考えられる。神々は霊的とはいえ「肉体」を持つ存在であり、具象的なイメージを神々について描くとき、人間の性質が神々に付与され投射されたのだと考えられる。
これに対し、キリスト教の場合、神と人間の関係は、人間が人間である「霊的・知的・意志的」根拠は、神の本性に淵源する。人間は精神的に神々の似姿であったのみならず、姿においても神々の似姿であったとされる。しかしエロヒームは上に述べたように「両性具有」であり、どのような姿なのか想像ができない。またユダヤ教の神は、「偶像」を禁止する神であり、神について、いかなる具象的イメージも持つことを禁じている神だとも云える。キリスト教の中世哲学の神学では、神は「純粋形相」であるとされる。質料的要素を一切含まない「形相」の純粋形態が神であるとされる。従って、人間が神の似姿であるのは、その「知性・判断力・感情」そして「意志の自由」においてそうなのである。これらは質料的要素ではなく形相的要素である。経験論的に考えるなら、キリスト教、ユダヤ教の神の持つ精神属性もまた、人間のそれらの純化・理想化された投影だと言えそうであるが、神学は、神こそが「原像」であって、人間はその影像・似像・鏡像であると述べる。
『旧約聖書』の神ヤハウェは、「人間に対し怒り、裁き、罰を与える神」としてその「人格性」の特徴が描かれている。他方、『新約聖書』でイエズスが宣明する「天の父」である神は、「人間を愛し、恵みを与え、赦す神」として描かれているが、同時に、「怒り、裁き、罰する神」の像をまたイエズスは語っている。この神の人格性についての矛盾は、キリストは神か人かという問題と並行しているとも云える。聖パウロスは教牧書翰の一つで、「生ける神の手のなかにあることは恐るべきことである」と述懐している。神が人間のように「みずからの意志」を持ち、「判断力」を持ち、「公平と気まぐれ」を持つということは、人間の側が「千の信仰」を持っても、神がそれをどう「人格」として判断するかによって、それは神の前では、ときに「十の信仰」にもなれば、「神への悖逆」ともなり、或いは逆に「億の信仰」にもなるということであり、このような「気まぐれさ」を持つ神に、自己の運命の「すべてを委ねること」は戦慄する決断であるとパウロスは述べているのである。神は「愛の神」であるが故に、「不公平な神」でもある根拠付けがあるとも云える。
『旧約』の神の不合理さと身勝手さに対し、敬虔なユダヤ教徒である義人ヨブが、「貴方にこそ、罪があり矛盾があり、気まぐれ・非合理性がある」と批判・非難する内容となっている文書が、『旧約聖書・ヨブ記』である。神は信仰篤い義人ヨブに対し、懐疑の天使サーターンの使嗾に応じて、ヨブに根拠のない厄災をもたらす。この厄災に対しヨブの友人たちはすべて、ヨブに「神に対する何かの罪があった」からだと主張するが、ヨブはそのようなことはないと反論する。これは人間に襲いかかるこの世の様々な厄災・悪に対し、その「責任」は人にあるのか神にあるのかという問題にも実は通じている。ヨブは自分の正しさを確信して最後まで自己の「無罪」を主張するが、最後に神自身が風と嵐のなかに象徴的に顕現し、ヨブに対し「みずからの偉大さ」を誇示し、「我は全能の大いなる神である。その我に楯突く汝は何者か?」とヨブを糾弾する。ヨブは平伏し、「あなたは自分勝手な不合理な神であり、悪(非)はあなたにある」と述べ、「わたしはただ一度だけ述べます。二度とは述べません」と語り、神の裁きを待つ。『ヨブ記』はこの後、神がヨブの「義信」を認め、ヨブを祝福して、ヨブの殺された息子・娘に代わる、新しい息子・娘を多数ヨブに恵み、失われた夥しい家畜や財産もまた、ヨブに回復する、という終章に続く。しかし、一説では、『ヨブ記』はヨブと神の対決を最終場面としていたのであり、その後の神がヨブの義信を認め、ヨブに補償を行う話は存在しなかったともされる。
「終章」は後世の付加だと云うのがおそらく正しいと思える。「人の悪と責任」、それに対し「神の悪と責任」に関する、この世のありように対する根源的な疑問の議論より構成される『ヨブ記』においては、議論は決着がなかったというのが本来の姿に思える。人間の立場からヨブは疑問を提示しているが、それに対する回答が神からあるとは思えないからである。こうして『旧約聖書』において、すでに神の「人格性」における不合理性に対する疑問が提起されていたと言える。他方、ギリシアの神々のなかには、「正義(ディケー, Dike)」の女神が存在した。「正義」あるいは「義」は共同体において重要な概念あるいは共同体維持原理であり、「規範(ノモス)」に対する平衡の機構が「ディケー」において保証されていたとも言える。『旧約』の神は、自称「契約と義の神」である。しかし「旧約聖書」を眺めてみれば、神はむしろ「契約を破る神、義を裏切る不合理な神」として姿を現していると云うべきである。
イエズスとパウロスは、このような旧約の神とは異なる、新しい「愛の神・赦す神・恵みの神」を福音伝道したのだとされる。しかし、愛の神・赦しの神を説いたイエズスは十字架で刑死し、聖パウロスもまた記録が不確かであるが、ローマの迫害に遭って、悲惨な殉教死を遂げたとされる。イエズスは「わたしの福音に従う者は、十字架を担って従いなさい」とも述べているが、「愛と救済の神」を信仰することが、悲惨な迫害に通じるというのは、合理的には納得の行かないことである。従って、このイエズスの言葉はローマ帝国による迫害のさなかにある信徒を励まし勇気付けるために、イエズスの言葉として挿入されているのだとも想定されるが、イエズスの説く「愛の神」もまた、実際の歴史的な現象としては、その信徒に「厄災をもたらした」という結果になる。『ヨブ記』の終章とは異なり、ここでは「父なる愛の神」は、自己の「約束」についての違反を反省する言葉もない。また、キリスト教がローマの国教となり、更に世俗的権力の支持を得た後では、キリスト教は「愛の神」の名において、異端を弾劾し、異教を攻撃し、略奪・殺人・暴行・拷問、侵略や戦争などを夥しく遂行し、「神の名」において、自己の行動を「正当化」した。
イエズスは「父なる神」と「人」がきわめて親しい間柄にある、と述べている。子供が泣いているとき、これを無視する父がいるであろうか、子供が空腹だと訴えたとき、麺麭ではなく蛇を与える父があるであろうか、とイエズスは教えて語っている。ここでは「神の人格性」は、「神=父」と「子=人」のあいだの親しい愛の関係、家族愛にも類比されている。『新約聖書』でイエズスの福音する「父なる神」はこのような「具体的・家族愛的な人格性」を持って人と関わる神である。しかし、キリスト教の「神学」においては、この「親しい関係」は神学的類比=アナロギア(analogia)であると説明される。ギリシア人の神々に対する認識では、彼らは神々を極めて人間的なものとして把握・描写すると同時に、その「戦慄的な違い」もまた弁えていた。キリスト教の福音伝道において、果たして、神の持つこのような二重性、「神と人との親しい関係」は神学的には、云ってみれば「方便」であり、神と人のあいだには「超越的な距離」があり、これはキリストが十字架に昇り贖罪を行った後になってもなお、最終的に回復されていないという真実は伝えられていたのであろうか。
神の「唯一性」の神学規定は、この「唯一特権性」が、多神教における筆頭神としての優越性・特権性ではないとキリスト教神学は明確に否定するので、それは超越命題となり、すでに見たように、「唯一性教義」の具体的内実を考察すれば、それは無限の解釈に発散するか、または内容がヌルつまり空疎な概念となる。神の唯一性を基に、いかなる命題でも神学的主張でも可能となるとも言えるのである。他方、神の「全能性」の神学規定も、超越的命題で、この命題の超越性を超越として奉じるだけであれば、それは形而上学的思索であり神学命題であるが、キリスト教はこの神学規定より、具体的な歴史や社会における事象解釈と「介入」を行うのであり、過去そのように介入を実行してきたのである。「全能性の教義」もまた反理性的であり、内容が発散することを既に見た。こうして「神の人格性の教義」について更に検討を試みたのである。しかし、神の人格性の規定は、超越命題でありながら、具象的命題としてそれを扱う神学上の矛盾が存在し、更に、神学的に神の人格性を人間の人格性の「原像」とする考えは、『ヨブ記』が示している問題を通じて、その矛盾を明らかにしているとも言える。
人の思考や行動が、気まぐれで、不完全で、一貫性がときになく、無責任な場合があるということは現象として事実である。これは「人が人である根拠」でもあり、「人格性」とはこのような象面も含めての人格である。原像である人格神はではこのような「不完全さ」を備えるのか。神学は「神は完全」であるとも主張する。人間の行動や思考における欠陥、罪、不完全さは人間の不完全性であって、神にはその不完全性は遡行しないのである。しかし、「父なる神の愛」は原像より地上世界に反映し、「神の不完全性」はこれは否定され、地上における人間の限界であるというのは、「恣意的な切り取り」としか判断できない。キリスト教徒が「神の名において悪を犯す」なら、それはそのような人々の罪であろうが、同時に、そのような行為を許容している「神の罪・責任」ではないのか。キリスト教の神は、「愛の神」か「憎しみと復讐の神」なのか。神学的に「愛の神」であると規定しても、その「愛」は原像として超越的であり、それ故に、「愛の神の名」において憎しみや復讐の行為をキリスト教徒が実行することは、「神の責任」ではないと主張するなら、「神の愛・神の人格性」から、いかなる行為の正当化の根拠も導出可能となり、「愛の神の名」において犯罪や虐殺・侵略を行い、それが神学的にも倫理的にも正しいと確信することが許容されるなら、神の「超越的人格性」は、あらゆる種類の「妄想」を正当化する根拠ともなるであろう。またキリスト教の歴史は、このような妄想行為や妄想信念がその福音のすべての時代・場所において存在したことを、逆に歴史的事実として実証している。
論理的に「神の人格性」は、超越的な人格性であっても、具象的な人格性であっても、超越性の神学を前提にすれば反理性的で不合理である。いかなる行為の正当化の根拠でも導出できるなら、「妄想の教義」としか理解できないであろう。また、この神学的規定を基に、あらゆる種類の妄想的合理化が成立するなら、キリスト教の「人格神」の超越的教義は、妄想を誘発し、妄想を積極的に肯定し促進する宗教思想・原理であるとも言えるであろう。また、「人間の悪の可能性」や「有限の責任性、不完全性」の根拠を神の超越の人格原像に認めないキリスト教の神学は、そこからして「悪の起源」「人間の判断の有限性と有限の責任性」を認めない神学思想であり、「神の不完全性」が似像としての「人間の不完全性」に投射されるが故、反合理主義の宗教原理を持つとしか云いようがなく、形而上学的根拠付けにおいてさえ、顛倒している「妄想教義」だと断じるしかない。
VIII 神の完全性と不完全性をめぐるキリスト教のアポリア
こうして、キリスト教の成立における二つの「教義構成原理」のあいだの矛盾から、「三位一体教義」「贖罪論」「原罪論」の論理構成の非合理性と妄想的構想を述べ、それぞれが妄想誘発的な「思考」のモデルを提示していることを述べた。また「神の唯一性」「全能性」「人格性」をめぐり、キリスト教においては「超越規定」としての神学と具体的信仰行為の実践において矛盾的解離が生まれ、ここからやはり「妄想的思考」や「妄想的自己正当化」の疑似論理が構成される可能性を指摘した。
先の章の最後で、「悪の起源」と「人間の判断能力の有限性と責任性」の問題について言及した。楽園における神話的挿話としての神学原理として、アダムとヘーヴァの神への命令違反から生じた人間の失墜を述べた際にも示唆したが、そもそも、「人間の責任性」とは、どこまでの限界があるものなのか、という疑問がキリスト教に対しては出てくる。ヨブは「神の責任」を明言したのであるが、キリスト教の神学は、ヨブには与していない。キリスト・イエズスによって、「旧約の神」は乗り越えられたという信仰思想であるが、しかし、実体としての神が、歴史的にその「本性」を変化させるものなのかどうか、ここには疑問がある。「本質は普遍・不変」であるが歴史の現象的ステージの諸段階で、人間に映じる「神の把握像・把握イメージ」が変化するのであるというのは、螺旋的上昇するカトリック神学の自負・自己主張であるとして、あらゆる「救済の教え」において、このような「螺旋的反省的進化上昇」は要請される以上、これを否定する訳ではない。
「人間尊厳の曙光思想」の生成と自覚、展開の過程において、キリスト教もまた生成展開したのである。このような「人の実存」への救済を至高課題とする思索においては、歴史的な螺旋的上昇が存在することは当然なことであるとも私たち自身、最初に述べたのである。しかしキリスト教におけるカトリック神学を代表とする神学思想における「螺旋進化」は、「人間尊厳の思想原理」よりして果たして妥当なものと言えるのかという疑問がある。「完全な神」は、人間尊厳の思想原理からすれば、超越的に規定されない。「人間の尊厳」は、「宇宙の諸存在の尊厳」思想へと通じて行くのであり、「人間存在の他種の生物に対しての優越性や特権性」を最初から否定するモメントを備えている。キリスト教の場合、人間は「神の霊的似像」であり、特権的存在者であり、至高神の律する宇宙は、「一元論」的な「神の完全性」を前提とする世界でもあった。
しかし、「神の完全性」とは何であるのかという疑問もまた生じるのである。神はむしろ、それ自身、歴史のなかで進化し生成されるものではないのか、という思想は、「人間尊厳の曙光思想」においては、当然に前提される思索アスペクトだとも言える。この場合、「完全な神」の措定や超越的・形而上学的規定は、ディレンマに陥るはずである。カトリックの神父でもあったテイヤール・ド・シャルダンは、歴史における神の進化と生成を示唆したが(代表著作『現象としての人間』)、カトリック教会はテイヤールの思想を「異端的(グノーシス主義的)」としてその著書を禁書とした。カトリックの神学は、無限に螺旋的上昇するカトリック教会を教義規定しつつ、同時に、もっと根本的な部分で、「神の普遍的・不変的完全性」を前提としているからである。「完全なる神」は歴史や時間のなかで、当然に変容しない。超越的に神を「先取り」する場合、このような超越的神学規定が前提され原理とされることは当然なこととも言える。
しかし、キリスト教神学がその普遍性・超越性の根拠とするイスラエルの諸預言者の「預言」や、神の御子にして救世主、神御自身でもある「キリスト・イエズスの預言啓示」そのものが、歴史現象として、「この地上」に現象し生成され現成された事象である。イエズス神話にもパウロス神学にも、形而上学的超越性はないのであり、形而上学的超越性は、キリスト教神学が後に主張したのである。「完全な神」は形而上学的思索において超越的に想定できるが、そこから具体的な社会的・歴史的倫理規範や人の現象に対する解釈の回答が降下して来る訳ではない。むしろ、地上の歴史経過において、「存在の尊厳思想」において、「超越的圏界(Transcendent Sphere)」に、具体的人間実存が「超越の神とその原理」を、地上から投射しているというのが真実である。
従って、超越的圏界すなわち「上天」に、超越的な完全な神が存在するとするのは、人間の実存限界を逸脱した形而上学的・神学的規定であり、それは妄想的臆断であるということになる。「完全な神」はそれが人の実存の投射である以上、同時に「不完全な神」でもあり、上天の神は、完全性と不完全性のあいだで揺れ動いている像であり、完全性の措定において不完全が意識され、不完全性の止揚として完全性が垣間見られるのである。超越的な神が過ちを犯すか犯さないか、超越的な神学規定において、「神は完全であり無誤謬である」とするとき、そのような規定は、理論措定可能ではあっても「内容空疎」であり、そこからどのような意味でも、具体的な歴史的・社会的・実存的真理命題を導出することができない。逆に言えば、「完全な神」の神学的規定より、何らかの具体的規範命題を導出するなら、それは「妄想」の導入を公的に認めていることになる。
キリスト教神学は、「神の完全性」を神学的に超越的命題として真理決定しているが、その結果として数々の反理性的命題や妄想が産出され、また妄想的信念に対し「根拠」を提供する結果となっている。「神の完全性」は解き難い様々なアポリアとディレンマをもたらすのであるが、それに対し、「整合的説明」を与えるとき、そのような「整合的説明」そのものが妄想的思想となって来る。その代表的なアポリアは、「この世における悪の存在」と「人間の罪や責任における無限性」のアポリアまたは矛盾であるとも言える。
IX この世における悪の存在と人間の責任の根拠
[1]「悪は善の欠如である」
キリスト教の神学において、神は、「真、善にして一(Deus, Verum, Bonum et Unum)」であるとされる。神は超越的に「善(bonum)」であれば、この世における「悪(mala)」の存在はどのように説明されるのか、という問題が起こり、キリスト教信仰の影響の元にあった西欧の思想哲学は、「至高善」のイデアー的存在を前提とする姿勢にあった為、近代の経験主義哲学が、善と悪も経験的に導出されるという仮説を立てるまで、善は実体的・イデアー的な何かと考えられた。この世における「悪の存在」については、初期キリスト教最大の教父である、ヒッポの聖アウグスティヌスは、悪を実体として把握するグノーシス宗教マニ教に対する反駁より、現象としての悪しきことごとのこの世における存在は認めるが、「実体としての悪」は存在しないという結論を提示した。
では、「悪」は本質的に何なのか、という問いに対しては、それは「善の欠如(privatio boni)」であると聖アウグスティヌスは主張した。また何故「善の欠如の悪の現象」がこの世に存在するかの根拠・理由としては、神が世界を創造するとき、「固有の具体的世界」を創造する限りにおいて、世界の素材における善の分布には当然不均一が起こり、別の言い方をすれば、「善の現象」が成立する条件として、他の現象の成立においては、十分な善の配分がなく、善の欠如の結果、このような現象は「悪の現象」として主観的に映じるということになると答えた[*]。(つまり、キリスト教神学では、一切の存在者は至高善である神の被造物である以上すべて「善」であるが、善には審級があり、質料存在は最低限の善しか備えず、神の世界創造において、この世界が「具体的な姿」であるのは、世界の秩序形成において、善の審級次元で段階を持つ形相の付与が質料存在に分与され、より高次の善の形相に与る存在局面は、より低次審級の善の形相の分与を受ける存在局面に対し、「善において優越」し、低次審級の善の分与事象・事態は、相対的に「善の欠如」として認識されるのである)。
しかし、悪(mala)が実体ではなく、実体としての善(bonum)の欠如の現象的現れであり、しかもこのような「悪の成立」はこの世界の具体的個別的な存在成立の前提として存在するのだとする考えは、「悪を甘受すべき現象」とする倫理を根拠付ける。その他方で、悪を批判する「倫理の規範」を、キリスト教神学の教義規範への準拠と逸脱に求めるなら、キリスト教の教義に同意しない「異端」「異教」の教えは端的な「悪の現象」であるとなり、「ミラノ勅令(CE313年)」における「キリスト教寛容令」の精神とは逆に、思想・信仰の自由や多様性を、「悪の現象・善の欠如」としてキリスト教神学的な倫理問題あるいは存在論的超越的問題として断罪する可能性を開く。
そもそも、「神」が超越的に至高善であるとしても、三位一体教義やキリスト贖罪論は超越的な真理ではないはずである。また「超越的に善なる神」とは、「どの神」なのかという疑問も生じる。キリスト教の神がその神で、唯一にして全能、絶対にして善なる神であるというのは、キリスト教の内部での正統性議論・公理的主張であって、これを「絶対」とすれば、そこに絶対的善の保証における「悪の決定」と、逆に「悪の事態の甘受」の理論が生まれてくるはずである。それに対し、悪は実体(substantia)であるとすれば、実存にとって何が「実体としての悪」かという真摯な問いかけが生じるはずであり、悪の存在への直接で積極的な問いかけの契機が導出され、根源的な問いの成立が認められるであろう。アウグスティヌスを端緒とする、「善の欠如」としての「悪の現象」論は、キリスト教の神学教義が善を決定し、そもそもこの神学に反する考え、現象は悪であり、また、この神学に準拠している限り、個人実存にとっての悪は、見かけの善の欠如であって、甘受すべきものだという論理あるいは倫理規範へと通じて行く。
悪の存在を直視して人の生き方を尋ねたのは、仏教の思想がそうであり、古代ギリシアの哲学も、中国の諸思想も、悪の存在を実体か、実体的に把握するところに、その思想の基盤が成立するとも言える。言い換えれば、「実存にとっての悪の意味」の解明が、それらの信仰や思想を生成し展開させ、世界把握に豊かさを与える条件ともなった。しかし「悪は(実体的・真現象的に)存在しない」として、キリスト教神学が、何が「善の欠如事態」かを規定するとする思想では、世界の実存的構成要素である「悪」を直視することは否定され、正統神学に反すると教会が決定する異端・異教こそは端的な「悪」で、他方、世俗支配者の搾奪や暴力・残虐のもたらす悪等は、これらは庶民が甘受すべき善の欠如現象であるとして、正統教会やその神学的倫理はこれを容認するという結果に陥る。個々人の実存が「悪の存在」に戦慄することを契機として、善を求め、存在の「尊厳」の理想へと実存的飛躍を試行し思索するという方向性は否定され、「悪」は一方で、教義的に超越的に絶対規定される他方、具体的個人にとっては、相対化され、教会権力の「恣意」に従属することになる。キリスト教教会に誤謬がある場合、教会が、「絶対善」則ち「神」の名において、実際的な「悪」の行為を推奨し、「悪」を善だと欺瞞的に正当化する錯誤に陥る。
悪を「善の欠如」とすれば、「善悪二元論」を見かけ上越えたことになるが、善悪二元論とは、善と悪の双方に実体性を認める以上、善と悪の緊張が個人の実存において、世界に対する真実探求の課題をもたらすのである。善と悪の二元論は、「善でないものが悪」という概念規定ではないのである。もしそうなら、「善とは何か」を原理規定するか、概念把握すれば、自動的に「悪とは何か」も答えとして出てくる。これはキリスト教の神学規定がそうであり、このように善が何かが決まれば、悪が一元的に決まって来る場合、善と悪は、対立する原理として存在しているとは言えなくなる。善が善としてあれば、悪は悪としてあり、その中間のものと、善であって同時に悪である実体や、善と悪双方を超越しているように実存に迫って来るものが存在するのが、真の「二元論としての善悪」である。キリスト教の「善の欠如」が悪であるとする思想は、悪を無化し、世界を観念的・形式的に把握する妄想的世界把握を妥当とするのであり、平和のためと称して戦争を起こし、善のためと信じて殺人・放火・強奪・暴行・残虐・差別を繰り返すことを肯定するのみならず、積極的に教会が促進する妄想の倫理を強固に基礎付けるとも言える。
|
(* 註):悪は「善の欠如」であって実体ではないという解釈は、聖アウグスティヌスから中世スコラ哲学に至るまで踏襲されている。しかし、それでは天上で神と争い地上に失墜して堕天使となり、神の軍団と戦っている「悪魔」の存在は何なのか、という疑問が起こる。そのようなものは迷信だというのは、キリスト教の神学からは妥当ではない。カトリックでは、「超自然(supernaturalis)」は自然であるこの世界に介入して来るのであり、天使を通じての神の介入と、悪魔の介入の両方があると考えられる。カトリックは「奇蹟」の存在を認め、当然、悪魔の存在も認める。東方教会も教義的に認めているはずである。しかし、神の意志やその意志の元にある天使の軍団と、天上・地上の両世界において争う「悪魔」の存在は「悪の実体」ではないのかという疑問が起こる。それとも、「悪魔」は「善が欠如した天使」であり、それ故に堕天使であるのだろうか。
善にして真なる唯一超越人格神を考える限り、悪魔の存在はアポリアとなるはずであるが、しかしなおキリスト教の神学では、悪魔は確かに「善の欠如した天使」であり、天使位階に応じて「権能」をなお備えるので、神に反逆する勢力となりえるのだとされる。しかしこの説明は疑問が夥しく湧き出す問題であり、神の純粋形相意志の反映としての天使が何故「堕落」して神に反逆するのか、天使に自由意志があって、天使はそれぞれ自由意志に応じて神に従う天使と反逆する天使に分かれて争ったのだとしても、それは神学的にたいへん奇妙なことのはずである。悪魔や天使は一体何時頃から存在しているのか、それは一説では、創世の最初の日にすでに悪魔は存在しており、従って天使も存在したことになっている。少なくともエデンでヘーヴァを誘惑する「蛇」が悪魔の化身であるとすれば、人間の創造に先立って「堕天使=悪魔」は存在したことになる。
『ヨハネ黙示録』によれば、悪魔の勢力と天使の勢力は、世界の最後において「最終戦争」を行い烈しい戦いを展開するようであるが、勝利は「神」の側に既定されている(とされている)。ゾロアスター教の光と闇の戦いにおいては、光の神が闇をペテンにかけて、光が勝った瞬間を「宇宙の終焉」としようと約束したので、その結果、宇宙は終焉において光の勝利に終わる。しかしキリスト教の場合、悪魔の勢力は何を目的に戦うのであろうか。何故、神に反逆したのであろうか。カトリック聖庁は、奇蹟が真の奇蹟か、それとも錯覚なのかを教義的実践的に見極める機関を備えている。また同様に、悪魔祓いというのは、神学的に妥当性を持つ宗教儀式であって、迷信迷妄の類ではないのである。しかし様々に考えてみても、「悪魔」の存在とその勢力が神やその天使と争うというこの世界の事態は、「悪魔という姿」での「悪の実体」の存在を認めているのだと云うように思える。「悪の実体性」を否定し、善の一元論で神の秩序を構想しても、なお、「実体的悪」の権能をカトリック教会は認めざるを得なかったということで、もしこの世界が「善の神」の創造になるなら、「悪魔」は堕天使ではなく、異界から訪れた別の秩序存在実体の可能性が高い。
キリスト教の神学は、「悪」の扱いで見ると、グノーシス主義的二元論を部分的に採用していて、表層の形式教義で「悪は善の欠如」と説明しているようにも思える。またそれはグノーシス主義とは異なり、率直に超越的存在の属性を明示しないで、三位一体教義や原罪教義で、「神の悪」を隠蔽し虚偽合理化しているように見える。ヘレニズム的な「善の宇宙像」に対しグノーシス主義は宇宙観と価値観を「反転」させているが、キリスト教神学は、二重の反転を行い、更に「神の悪」を隠蔽して「善なる神」との矛盾一致を実現するため、様々な反理性的な神秘的・妄想的教義を構築したようにも判断される。
|
[2]「人間の行為の責任は無限であるのか」
キリスト教は、救済を宣明する宗教であるが、そのもたらす救済には条件が付いている。このような「条件」はあらゆる救済宗教が備えているものだとも言え、そもそも「宗教」は広義のノモス(律法・社会規範)への準拠を救済の前提に置いているとも言える。しかし、キリスト教については、キリスト教を信仰しない者は、救済に与ることができず、悲惨な運命へと落下する。具体的には、死後、魂の復活がなく、魂は「無」へと消え去る。そしてキリスト教の教義が「神経症的」なのは、いかに信仰しようとも、深く教えに帰依しようとも、救われる者を決めるのは神であり、神は選択する神で、人格神であり、誰が救われるのか、厳密には誰も保証がない、という真実である。
仏教もまた救済宗教であるが、仏教に帰依せず、あるいは仏教修行者となって修行しない場合、救済がなく悲惨な運命となるかと云えば、そもそも悲惨なのは本来的に「この世界」であって、仏教は、この世界の悲惨さを直視し、悲惨さの原因となっている世界の「無常さ」「諸行無常・諸法無我」の真理を覚り、この世の悲惨さを余裕ある心境で眺め、心の安らぎを得ることが、その「救済」であって、仏教に帰依しない者は、心の安らぎが得られず、この世の悲惨や苦しみのなかで、無明の苦しみと悲しみの人生を生き続けるというだけの話である。
キリスト教『新約聖書・福音書』には、イエズスが訪れる前には罪は罪ではなかったが、イエズスが訪れ、福音を説いた後では、罪は罪となり、赦されることはなくなった、という趣旨のイエズスの言葉がある。これは楽園のアダムとヘーヴァについて、二人が無自覚で智慧がなかったとき、死を知らず、無垢の幸福にあったが、自覚意識が生まれたとき、死の存在を自覚し、「死の定め」が罪として生まれた、という話と同じ構造を持っている。罪は、「規準」がないときには罪ではないが、規準がひとたび生まれると、罪が罪として顕現するという思想である。イエズスの「愛と赦し」の福音は、同時に、その教えに従わない者に対する「罪」となるという考えである。
このことは、次の仏教の考え方と比較するとき、対照的である。則ち仏教では、救いの真理は、みずから実存を反省し修行し、自分自身の努力で見出すもので、他人はこの真理発見のための環境的準備で間接的に修行を助けることはできても、救いの真理発見はどこまで行っても、当事者の実存の課題であり、仏陀といえども、個々人の救済・真理の覚知は、ただ「慈悲」でそれを暖かく見守ることしかできない、と教える。この世は本来的に、妄想が横行している世界であるというのが仏教の展望である。妄想を妄想と自覚することが仏教の救いであるが、自覚しなければ、妄想のなかで本来的に「悲惨な人生」に留まるだけであって、仏教の教えに従わなければ、何か悲惨な運命が新しく待っているというような論理はない(原始仏教の教えではこのような考えであった。大乗仏教になると、輪廻転生や輪廻に亘る因果応報の考えが出てくる)。
この世は本来的に悲惨で無常な世界であり、世界が悲惨で無常なのは、誰か人間が何かの過ちを犯した為ではない。それに対しキリスト教は、アダムとヘーヴァの「原罪」よりその救済の神学が始まっているとも云って過言ではない。人が「死の定め」にあることも、アダムの犯した原罪に起源すると云う。しかしイスラーム教は、人は自分の犯した罪には責任があるが、他人の犯した罪については、その個人には責任はない、と述べている。これはキリスト教の「原罪教義」に対する反論として述べられている。実際、何故、アダムとヘーヴァの過ちが、全人類の罪となるのか、合理的に考えればおかしいと云うべきである。また、全人類の「原罪」を贖うため、神御自身であるキリストが贖罪のため、十字架に昇って苦しみを受けたというのも、不合理に不合理を重ねるような疑似論理である。しかも、キリストの贖罪の結果、人類に救済が実現し、人は死ぬことがなくなったと云うならともかく、「可能性としての永遠の命・天国での復活」が齎されたということで、「救済の具体的内容」が不確かであり、しかもキリストが訪れたことで、それまでは罪ではなかったことも、名指しにおいて罪となるようになった、ということだと、キリストは救済ではなく、「呪い」をこの世にもたらすためこの世に訪れたのかという疑問さえ起こる。
(『福音書』においてイエズス自身が、わたしはこの世界に不和と諍いをもたらすために訪れたと述べている。これは社会的矛盾を糾弾し、従来の社会や家族のありようを新たなものに変革しようと云う主張において、既存社会体制・規範倫理との葛藤と争いが起こるという意味であると思えるが、他方、文字通りに「キリストの出現は災いだ」という意味にも受け取ることができる)。
キリスト教においても、救済は、個々人の信仰によって実現されるとする。しかし、救済に与ると云うことは、キリスト教の基本的な救済の図式である、「原罪=神との疎遠距離」という「人間の罪にある状態」の承認から始まるのであり、一旦この「疎遠距離」を信仰で認めると、その距離を「解消できる」のは、一つに信仰生活と信仰の心ではあるが、絶対的に救済を決める条件は、人格神で裁定・審判を行う「神の自由意志での判断」に依拠するということを認めることになる。どれだけ信仰すれば救済に与れるかという保証は、現世的には何一つとして確定しない。「信仰の深い」者が救済に与れる可能性が高いとは言えるが、しかし誰の信仰が深いのか、それを最終的に判断するのが、やはり「神」であるので、神の視点からどう見えるのか、どう判断されるのかと云う回答のない問題に、キリスト教信徒は、信仰に真摯であればあるほど直面することになる。
人間は「罪ある存在」つまり「神との距離ある存在」であるということは、合理的に認められる。仏教はこれを、悲惨な無常の世界に人が生きているという「事実」として教えた。しかし、何故人間の状況がこのようなものなのか、仏教は、個々人の行為や存在にその「責任」があるとは当然云わない。しかしキリスト教は、この「距離の存在」従って「罪の存在」が、個々人の「責任」だと教義的に超越措定している。「イエズス神話」のイエズスは「無条件の愛」「無条件の救い」を宣明したのではないかと思うが、キリスト教の教義は、そのようにはなっていない。
神への信仰の祈りにおいて、「個人の罪の赦し」を神に願うのは、個人が罪を犯した場合は合理的だと言える。しかし、「神との距離、神との離在」という人間の本来的なありようは、実存の状況ではあっても、個人に責任のある何かの事態ではないはずである。これが「神に対する裏切り」になるのだとしても、人が個人として裏切ったのではないはずであるし、人祖アダムの裏切りでもないはずである。人がこのような「実存状況」に存在しているのは、キリスト教的な世界観からすれば、創造において「神が人間を、このような存在に創造した」からではないのか。人間の「神との離在」「神と人間の距離」は、キリスト教的な考えを論理的に突き詰めれば、人間に責任あることではなく、責任は、創造者である神にあるというべきである[*]。
「原罪」の贖いを、キリストだけではなく、更に個々人に求めることは、不合理であり、このような救済の思想は妄想思考だと云っても過言ではない。人が「罪深い」存在であるというのは、そのように表現することも可能であるが、人がそのような「実存状況」にあるのは、本来、神がそのように人を創造し、世界をかくのごとく定めたからではないのか。個人は共同体のなかで、確かに他者に対し、何がしかの「責務」を負い、「責任」を負うというのは事実である。しかし、それは個人にその責務・責任が実際にある場合に問題となり、責任の重さは、人間が有限の存在である以上、「有限」でしかない。キリスト教の唱える「霊魂の救済」を実現するには、人は「無限の責任」を自己責任として負うしかないが、それは端的に妄想思考としか言いようがないのである。
|
(* 註):しかしなおキリスト教的人間観とその「自由意志」の考え方においては、神の「似像」としての人間には「自由意志」が存在し、「神との離在」を人間はその自由意志で選び取ったのであり、それが故に神との距離=原罪の責任はなお人間個々人の責任であるという論駁もあり得るであろう。同様に、人の日常生活における様々な「罪」……共同体の世俗法から規定される犯罪(虚言・窃盗・詐欺・強盗・誘拐・傷害・殺人等)に加え、宗教的慣習法や共同体の倫理ノモスよりしての罪についても、これを犯すのは、人間に自由意志がある以上、その「責任」は意志の自由ある個々人であるという論証も可能であろう。しかしこのような見解や主張は、護教的詭弁論法ではないかとも思える。
超越唯一神の「人格性」を原像として人の霊魂が造形され、人には「自由意志」が付与されているが故、人の意志の選択はその人の責任に端的になるとは、キリスト教的な「罪と責任」の関係の論理であるが、このような「自由意志」が神との「超越的離在」を可能として、永遠的に人間の運命を決定するというのは、妄想思考と呼ぶ以外にどう把握することができるのであろうか。「罪の概念」の起源は、本来、個人の生存への欲動と共同体集団の存続原理のあいだの矛盾から生じているはずである。「虚言・詐欺・窃盗・傷害・殺人」なども、共同体の様態において、その意味付けは多様であり、戦闘集団においては、このような「犯罪」が共同体の利益に有効である場合は、そのような犯罪者はむしろ英雄・賢者として尊敬を受ける。一般に、人が「罪を犯す」のは、個々人の「自由意志」における決定というより、共同体と個人の置かれた状況における回避し難い「選択肢」の決定結果であることが実際的には真実である。
人が自分で自分の行為や思想や、まして信仰を選択できる「自由」は、事実として驚くほど少ないのだとも言える。理論的理念的に「人の自由意志」を仮定することは可能であるが、人は歴然として有限の存在であり、かつ共同体の文化によって価値観も世界観も規定されている以上、個人の「自由意志選択」の余地はゼロではないにしても、ほとんどゼロにも等しいのである。共同体のなかで、隣人と共に共存する人間に対し「倫理的責務」が問われるとしても、それは共同体存立のための要請であって、倫理に厳しくあることは、自己を律する原理ではあっても、その限界を他者に対し適用するのは僭越というべきである。「自由意志」は共同体との調和における「個人の権利」「哲学的な人間の可能性原理」ではあっても、超越者である神の似像として人が担う「責任の根拠」原理ではないのである。人が現象状況的に、あるいは倫理良心的に自己を「罪深い」と自覚反省したとしても、それは超越的自由意志を根拠とする「責任負荷性の自覚」とはまったく別の事態である。
|
X 実存の救済とは本来何であったのか
「人間尊厳の曙光思想」についての序論的な話より初めて、キリスト教をケース主題として、「宗教の妄想性」について一つの展望を以上に記してきた。先の章では「仏教」の覚りを求める修行が、救済宗教として神経症的なキリスト教の「救済・神の赦し」に比べ、遙かに合理性的であり、納得が行く考えであることを述べた。原始キリスト教の教義の二つの起源から、その贖罪と原罪についての考え、「三位一体」の「唯一人格超越神」の意味するところが反合理的な妄想を産出することを概略的に述べてきた。
そして重要なことは、キリスト教の神学において垣間見られた、「妄想的教義」あるいは「妄想誘発性教義・神経症的救済原理」は、実は「唯一絶対人格神」を同様に要請するユダヤ教やイスラーム教においても共通して出現するということである。三位一体教義という巨大な妄想のシステムを、これらの宗教は持たないが、「絶対唯一神」という考え方が、実は妄想を誘導するのである。その根拠は非常に自明かつ簡単で、形而上学として「超越者」とその「救済原理」を展望することは、観照(テオーリア, theoria)としては問題はないが、具象的な共同体ノモスを規定する社会基盤宗教が「超越唯一神」を前提するとき、キリスト教について、神の「唯一性」「全能性」「人格性」を論じ批判したときと同様の批判論法が成立するのであり、信仰そのものが妄想性を持ち、その結果、世界と人間に対するヴィジョンにおいてもまた同様に、妄想的歪曲が生じて来るのである。
キリスト教やイスラーム教に比較するとき、仏教は「正気へと人を誘導する宗教」であるとも云え、儒教などは「世俗的常識の範囲で、人を正気に維持する宗教」であるとも言える。孔子は『論語』において、「怪力亂神を語らず」と述べ、また「未だ生を知らず、いずくんぞ死を知らん」とも述べている。儒教は葬送儀礼を非常に重視した宗教で、死後の魂魄の行方についてなにがしかの展望がなければ、そもそも葬送儀礼の重視などもないと言えるので、決して儒教は、「霊」について沈黙するという訳ではないが、しかし孔子の思想は、何よりも「経験主義的・合理主義的」だと言える。儒教は政治思想だとも言えるが、しかし同時に、万民の安寧と平和を祈願した宗教とも云え、社会実践において統治者のあるべき姿において、救済宗教の思想を唱えたとも考えられるのである。
中国における老荘思想とその継承展開としての道教においてもまた、人間の「平等と個人の尊厳」の原理が教えとして含まれているが、しかし、こちらは「怪力亂神」を語るのを得意とし、呪術的要素を多数残しているとも言える。しかし、呪術が救済宗教の人間尊厳原理思想にも介入して来ることは、どの宗教であっても同様で、もっとも原始的過酷で、「偶像崇拝の禁止」等を文字通りアラベスク模様の文化芸術にまで高めたイスラーム教においても、聖人崇拝は徐々に拡大して行き、聖地崇拝は、メッカを代表として、気づかれない形で、呪術信仰の次元へと後退しているとも言えるのである。ただ、「呪術信仰」の導入は必ずしも宗教としての「後退」ではないと云うこともまた指摘する必要がある。一つは、「呪術信仰」が迷妄だとは必ずしも言えないことと、呪術は、共同体のノモスとのあいで必要な調和を構成するための機能を担っているとも言えることである。またキリスト教神学の形而上学のように、高度な哲学的思索や理論を駆使した「呪術」と言えるものも存在する。原始仏教においても呪術は大きな要素であり、仏教がより展開・進化し、大乗仏教へと思想的広がりを高めると、更に深く呪術と混じり合うという結果になっている。
最初に、『「宗教の真理」とは、「人が人であること」の無限に果てしない「希望と理想」のイデアルにおいて、螺旋的進化上昇して行くところに、その「真実の結晶」が開在するのである』と記した。「人が人であることの希望と理想」と記したが、これは「人が人であることの苦悩と絶望」と書いてもよい。「苦悩と希望」「絶望と理想」のあいだで、人は人として生きることの意味を求めて、形而上学的な根拠神話を求めるというのが、「宗教の真理」探求の基本機制である。人の共同体は野蛮から文明へと進歩し上昇するというのは、一つの仮説であり、何が野蛮で何が文明かということも、自明的に決まっているとは必ずしも言えない。ユダヤ教、キリスト教、イスラーム教を代表とする、唯一絶対神の啓示宗教は、膨大な信徒を擁する世界宗教にも発展したが、それらが「文明の宗教」と呼べるかというと疑問がない訳ではないのである。
「敵の殲滅と侵略・差別化の思想または慾動」は、文明的というより野蛮共同体の社会原理のようにも思えるが、原始的な共同体はむしろ、「平和共存的」原理を志向していることが多く、「殲滅原理・絶滅原理・差別原理」は文明が生み出すという側面もまたあるのである。キリスト教、イスラーム教などにあっては、「絶滅と差別」の文明原理が、これらの宗教によって妄想的に正当化されるが故に、西欧文明やアラブ文明などにおいて、これらの宗教は大宗教となった可能性がある。「人間の尊厳・平等・共存」を唱道する救済宗教や人類宥和の思想は、敵対者殲滅原理を持つ、キリスト教・イスラーム教などによって、殲滅され、滅ぼされた可能性が高いのである。キリスト教・イスラーム教・ユダヤ教などの絶対神を宣明する啓示宗教に限らず、仏教・儒教・道教・ヒンドゥー教なども、「我らこそ《宇宙の真理》を知っている」という自負を顕在的に、あるいは潜在的に備えている。しかし、「人間の尊厳」思想の宗教は、「他者の絶滅原理・排他原理」で成立するものであってはならないのであり、その意味からは、「この教えは、状況における相対的な真理である」と教える宗教にこそ、「真理」が宿っているとも言える。
言葉を換えれば、人間の思考能力の次元においては、「真理」は相対的にあるというのが、「真実(Veritas)」である。これに依り頼む「絶対の真理の救済宗教」は、言葉の矛盾になるのである。「絶対真理教義」と「魂の救済」は両立しないと云っても間違いではないのである。「魂の救済」は個人の実存の問題であって、特定共同体で適切な救済宗教はあっても、その「真理性」や「妥当性」は共同体ノモスとの調和性にあると考えるべきである。そして共同体あるいは人間の社会は、一般に「差別構造」の構築において、その共同体の「構造維持原理」を支えているのが一般的事態である。
かくして、「この教えこそは、至高の救済の教えである」と宣明する救済宗教は、共同体の唯我性と調和するのであり、共同体の「差別構造」を理念的に支持する救済のイデオロギーとしてこのような宗教一般は機能するのだとも言える。イエズス神話が伝えるイエズスは、共同体の「差別構造」に何よりも反対した存在であった。イエズス神話は、イエズスが共同体の秩序攪乱者として、暴徒・犯罪人として処刑された真相を伝えているとも言える。聖パウロスの神学は、それに対し、何よりもパウロス自身の内面の「魂の救済」「実存苦悩の解消の救済」を宣明している。パウロスが伝えるキリストの復活は、パウロスの「魂のなかでの出来事」であり、キリストの復活を通じて「パウロスもまた新生を得た」のである(そして付言すれば、このような「魂の救済」の機制を端的に救済の智慧として宣明する宗教、あるいは思想こそは、「真理の実存的覚醒」に最大の秘蹟を見る「グノーシス主義」であり「グノーシスの諸宗教」である)。
イエズスとパウロスで何が共通するかと云えば、イエズスは個々人の実存において、「神の霊(Pneuma Theou)」が宿ることを知っていたということである。「人間の尊厳と平等」とは、どのような人でも「霊の神性に、魂の内面で与っている」という確信から齎されるものだという真実がある。イエズスが「天国はあなたがたのあいだにある」と述べたとき、イエズスは、神性をうちに持つ人と人の交わりのなかにこそ、「天国・神の国(Basileia Theou)」は実現していると述べているのである。そしてパウロスは、彼の実存の暗黒において、うちなるキリストの光明と出逢うことで、彼自身の復活が、彼の内部なる魂における《神性》の顕現を通じて現成したことを知ったのである。これらの「救済」の根源的な原理は、魂のうちなる「《光明》の自覚」つまり、「グノーシスの覚知」ということに他ならない。
上天の神や天帝が、人間の尊厳や平等を主張するが故に、人間の尊厳と平等の「光明思想」が現実的な真実の意味を持つのではないのである。イエズスもパウロスも共に、それは個々人の実存における「救済の光明・うちなる光の神性」であるということを理解していた。しかし、人々は、イエズスのこの「人の心の内なる天国」も、パウロスの「魂の甦りと光明の復活」も、共同体の差別支持の救済原理として利用したのであり、イエズスもパウロスも、後に彼らを救世主・使徒として奉る人々によって、人間を差別し搾奪し迫害するための原理思想・救済宗教の恣意的絶滅原理の根拠とされたのである。
― グノーシスの真理 ―
グノーシスの真理とは、人の魂のうちに光明の神性が等しく宿るという真理である。人はこの神性を持つが故に、人としての尊厳を持ち、互いに平等であるのである。それは個々人の実存の状況に応じて開示される真理であり、《信仰(pistis)》において、自己の生と死を賭ける真理ではなく、《理性》において、合理的に現在し開現する真理でもある。『トマス福音書』はその冒頭に、「この言葉の解釈を見出す者は、死を味わわないであろう」と記されている。この言葉が編集句であるかどうかは別に、「真理の光明」は自己の実存のなかに、理性的解釈において見出されるものであり、それは「真理に対する覚醒・認識(gnosis)」である。
グノーシスの真理とは、うちなる光明の霊への覚醒であり、何ゆえ、光明の霊であるこのわたしが、矛盾と苦悩と敵対のこの暗黒の世界に生まれてあるのか、自己の魂に問いかけるとき、「本来性」についての解釈(Deutung)が流出するのだと言える。自己の魂が本来的に救われているのなら、《永遠のいのち》は、いま此処に実存しているのである。
La Fin
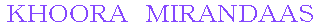
![]()
