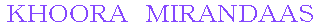
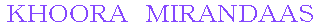
|
文明と地球人類 |
![]()
![]() 【Humanitas Terrestris】 [LINK] 「都市の生成とパターン」
【Humanitas Terrestris】 [LINK] 「都市の生成とパターン」
![]()
![]() 【Humanitas Terrestris】 [LINK] 「死すべき定めと不老技術」
【Humanitas Terrestris】 [LINK] 「死すべき定めと不老技術」
[LIST] [HOME] [END] [THOUGHTS] [LITERARY] [MISCELLAN] [INFOR]![]()
![]() 【Humanitas Terrestris】 [TOP]
【Humanitas Terrestris】 [TOP]
|
Types and Formation
of Cities
『都市の生成とパターン』 − Fundamental Phase Considerations − ☆☆ ☆☆
都市の形状のパターンと、その成立に関して、理論的な考察を試みてみたく思います。本文書はラフ・スケッチとして、概説的展望を考えます。その最初の考察として、都市における、「碁盤目状」と「放射状」という二つのパターンを考察します。これらの都市形状は、都市のパターンにおいて観察される代表的な様式であり、ここでは、これらのパターンどこから起源するのかを仮説的に考察してみます。
人類の集落の起源は、文明史的には遙かな歴史の薄明の彼方にありますが、まず、本文書では、人類の文明や都市文化が発祥し始める、紀元前4千年頃で考察を始めます。この歴史段階においては、日本や西欧は、生態学的には、その土地の大部分が森林に覆い尽くされていました。それに対し、中国大陸、インド亜大陸、北アメリカ大陸などは、気候的には亜熱帯から、温帯、亜寒帯に属し、そこには、大山脈に付属する森林の広がりと混在して大草原があったと考えられます。 紀元前五千年期には、中国大陸、またインドでは、農業生産が、安定した食料供給を可能とし、定住の巨大集落があちこちに成立し始めます。他方、日本もそうですが、主に西欧では生産の手段はいまだ農業ではなく狩猟が主体で、大森林を切り開いたごく狭い区域に散在する小集落が成立し、小集落のあいだを結ぶ森林のなかを貫通する連絡路が発達します。この連絡路を通じて文化や物品が相互小規模文化圏のあいだで流通し、従って、これは森のなかの交易路であり、複数の交易路の交差する地点に自然地形に大きく制約と支配を受けつつ「交易交差集落」が成立します。これらが現代の西欧の都市の原形だと、仮説的に考察されます。 農業生産が開始された紀元前七千年期頃の段階で考えれば、農業集落の原始パターンは、放射状ではなく点分布で、やがて人口の増大と農耕地の拡大による密度の濃淡の生成から、密度の濃い部分を中心とする円形分布になって来ると考えられます。これは、インドや中国のように、大平野があって地形にあまり影響されることなく集落が形成される場合の一般パターンと云えます。このような分布密度の集約が生じ、集落に濃密な中心部分が生成されて発展して行くのと、「権力や富」の発生と展開は同期しているとも考えられます。 中国の集落の場合、考古学的に観察される例では、原始的小集落は集落の周りに壕を掘っていましたが、これは野生動物を防ぐためであり、集落の規模が大きくなり中心が濃密になるにつれ、中心部の中集落は壕ではなく土塀や板塀で囲まれるとされます。これは人間の侵略を防ぐためとも考えられます。野生動物は壕を造り水で満たすと侵入できないが、人間は壕など平気で乗り越えて来るからです。人間の侵入を防ぐには、物理的に有効な障害物で集落を囲まねばならず、これが都市防衛城壁の原始的起源と云えます。 中国・インドの都市は、こうして、最初には円形集落の形状を取り、中心に権力者の住居やその権威の象徴の建造物などが造られ、周りを囲む環状防壁と、そこに開いた、集落外に通じる門に向かう放射状の道路が成立する構造になります。 他方、西欧の集落の場合には、森林のなかの開拓地に集落は散在して存在し、地形的制約より発展する「主要交易路」に沿って交易集落が成立し、地域中心部に位置する「交差集落」には、権力者とその権威の象徴が存在する構造になります(現在、キリスト教の教会や市庁舎がある場所には、古代には、ケルトやゲルマン、またはそれ以前の異教の神の聖域や民会の広場があったと考えられるのです)。地形の支配を受けて、複数の交易路に沿う都市発展と中心集落の構造化の両者が同時に進行すると考えられます。そして都市は周囲の濃密な森林の克服へと向かい、農地を外部に広げて行きます。西欧の都市はこの生成パターンで近代まで展開して来たと考えられます。 中国の場合、紀元前五千年期には、大平野にあって、あいだに幾つもの森林や山地などを挟みつつ大集落が拮抗して成立し、互いに勢力争いを始めます。それらの大集落は、「原始都市国家」を構成し、殷や周の時代は実質的に地方権力を握る大集落国家が幾つも併存しつつ、勢力を競っていた時代とも云えます。春秋戦国時代の都市は、まわりを環状防護壁に囲まれた円形都市が基本形で、大集落都市内部にあっては基幹道路は放射状であったと云えます。 では、中国の都市集落において、どこから「碁盤目都市」の設計が出てきたのか。一つに、中国の古代の世界観では、西の山の彼方に神仙が住み東の海の彼方にも神仙が住むという考えがありました。この二つの神の世界に挟まれた大平野を舞台に、「南北」で文明が衝突したのが中国文明だとも云えるのです。それは、統一帝国が成立した後は、中原を支配する中華帝国対北方遊牧民族という対立構図になりますが、中原の中華帝国そのものが、起源的に北方文明の雄であったと考えられ、南方文明に対する支配の上に中国の統一帝国が成立したという事実前提があるのです。 中国の天子は「南面する」と云われ、また臣下は「北面して、臣下の礼を取る」とされます。何故天子は南面するのか。それはおそらく、統一中華帝国の皇帝は北方文明の代表者で、かつ南方中国の征服者であり、南方をこそ監視せねばならないという意味なのでしょう。こうして、統一中華帝国の首都の設計においては、北に自然の要害となる山地を要請し、もっとも北方に天子の座する宮城を置き、そこから南に官僚街、そして商人や一般市民の街という配置にし、宮城より見て南の端が見通しがよいように中心に大南北路を置き、南北東西に大路を置き、こうして長方形の形となった都市の南端に外部からの使者を迎える門(日本の平安京だと、ただ門だけで、その先のなかった羅城門)を設けたのだと考えられます。 これは四方八方に監視の目を向けねばならないが故、円形集落の形であった古代都市とは設計思想が違い、その根本は風水とかではなく、被支配地である南方を睨みつつ、北方は防御のため山地を選んだという合理的理由によるでしょう。つまり、「防衛のための監視視線に特定の方向性が必要」とされ、それは「南北方向」だったということです。 日本の都市は、中華帝国の首都の設計を真似た、平安京(京都)などは、東西南北の碁盤目形になっていますが、大阪になると、「碁盤目」のようにも思えますが、実際は近似的であり、大阪城を中心とするある限られた範囲でしか、成立しません(これは、海岸線が南北方向だったのと、商業用「人工水路建設」のためできた幾何構造と考えるのが妥当で、これと類似の構造は、明治以前の江戸の町の水路区画にも垣間見えるとも云えます。……日本各地の都市・村落の形状パターンの発展構造の分析は、ここでは行いませんが)。 他方、西欧の都市は、「円形都市+街道都市」というのが生成の基本パターンであると考えられ、外部に向かって展開した結果、放射線路が構成されていることがあれば、ある境界で(それは昔の都市城壁であることが多いでしょう)、パターンが崩れていることがあるとも云えます。(また、西欧の都市の内部にある、大環状道路は、この昔の都市城壁の周囲を走っていた道路の名残であることがあります)。パリが、その都市設計プランで眺める限り、現在のシテ島をほぼ中心として外部に拡大した「円形+街道都市」の典型とも云えます。河川が交通の要路でもあり、シテは「交易路交差」の中心にあったとも考えられるのです(これと似た事情の構成を持つのは、ティベレ川を西に望む七つの丘から出発したローマでしょう。パリについては、「テュルゴーのパリ地図」が、どのような構造を中世においてパリが持っていたのかを明瞭に示しているでしょう)。 西欧ではなく、ロシアにおける都市モスクヴァは、クレムリン(砦)を中心とする防衛城塞都市であるが故、その生成の起源以来、円形放射構造を持つと考えられます。西欧の都市は、中世における地域都市国家権力の生成の時代以前には、城塞都市というよりも、むしろ光なき外部の森林領域へと文化拡大して行った結果円形を取るのだと考えられます。その一方で、「街道交差都市」としては、複数の基幹街道に沿って都市が広がっているのが特徴です。このような構造の西欧の都市に対し、北アフリカ、西アジア、インド亜大陸などの都市は、防衛都市としての機能が優位である場合は円形放射構造を持ち、商業都市として展開、領域増殖した場合には不定形継ぎ接ぎ様式になるとも考えられます。 人工的に都市を設計する場合、区画秩序のためには碁盤目形が合理的ですが、中国の宮城都市のような「南北の軸線」は必然性がなく、ブラジリアのような、左右部分でそれぞれ碁盤目であるが、その軸線が傾いているという都市デザインができるのです。このことは、二十世紀の人工的な設計都市の場合、一般的に適用できる原理とも云え、人工都市は地形的制約を超越し、あるいは歴史的地理的条件に応じて、合理的区画構造を適合させるとも考えられます(こう云った都市設計の歴史的文化的条件における具体的構造生成の吟味は、目下の考察では、取りあえず省くこととします)。 |
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ HAGIAI SANCTAE
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ HAGIAI SANCTAE
|
Miranda et Marie RA. 2003:0828:2157 |
[TOP] [LIST] [HOME] [END] [THOUGHTS] [LITERARY] [MISCELLAN] [INFOR]![]()
![]() 【Humanitas Terrestris】 [TOP]
【Humanitas Terrestris】 [TOP]
|
Hee Moira tou Thneetou kai Tekhnee anti Geeraiou
『死すべき定めと不老技術』 ― 精神は本来、永遠性を持つのか ― ☆☆ ☆☆
思い出すに、光瀬龍氏は、人類の文明の行く末とその運命をその目で確かめたいので、自分は、千年でも二千年でも、それ以上でも生きていたいと述べていました。
不死不老、あるいは、可能的不死で、不老の技術について考えるに、不老技術ができる場合、まず、力のある者のあいだで、その権利の奪い合いが始まるでしょう。その混乱が一定の収拾を迎えるのに、何年、何十年、または何世紀を要するのか分かりませんが、人類の文明や社会が、存続の基盤を喪失して崩壊しない限り、一つの新しいステージへの上昇の結果起こる混乱は、やがて、ある安定時期を迎えるでしょう。その頃には、生きるとはいかなることであるのか、また年老いるとはいかなることであるのか、身体の不老化に、精神をどのように調整するのか、個人の世界観や倫理観から社会のノモス(規範ルール)まで、様々なものが変化するでしょう。 そう言った変化の後で、振り返って見れば、これまでの多くの人々が語り考えてきた、「自然の摂理」とか「寿命」とか「神の定め」「生命の定め」などは、まったく違った認識や考察のアスペクトのもとに置かれるのだということが明白に分かるでしょう。現在であっても、そのような、生命や人間の精神の不死性の意味について、有効な考察はできるはずであるのに、ある条件や環境においては、「こうであった」というルールというか、「生の様式・存在のスタイルの倫理」を何時までも主張するということは、未来が、人を置き去りにする何かだということの認識が欠けているのだと思えます。 近世・近代に始まる西欧医学は、これまで、「運命の病」だとして、多くの社会や文明が諦めていた様々な病や、身体・精神の問題を解決し、例えば、レプラ(癩病)も、病原菌が確認され、それを根治する薬物や治療法が確立されました。『旧約聖書』には、レプラ患者の守られねばならない過酷なルールが記されています。しかし、レプラは治療可能な病だとなった現在、そのような、「不治の汚れた病」という前提から造られた「神の法=律法」に、なお従って、レプラに罹っても、治療すべきでなく、墓場で、孤独に飢え死にを待つのだというような、ノモスに従うのは、正気ではないと考えるべきでしょう。輸血にしても、『旧約聖書』の律法を根拠に、輸血を拒否するエホバの証人を非難する声はあっても、外部からそれを擁護する声は、ほとんどないというべきです。 しかし、自分で「血液=命のもと」を作れなくなった者は、「輸血」というような「他人の血を食するに等しい行為はせず」、そのままに死にまかせるべきだというような話がないことも、また奇妙なことではないでしょうか。医療行為で、寿命を延ばすことは認められ、しかし寿命は有限で、「人間は死すべき存在である」というのは、どこから、こういう確信や主張の根拠が出てくるのでしょうか。 人間が増えすぎるのは、地球環境を破壊することなので、人口増大を結果する、寿命の「超長寿化」は、どこかで歯止めをかけねばならない、というのが理屈として通るというのなら、現時点で、あるいは何世紀も前から、人類は、地球環境を破壊し続けてきたのであり、「行き過ぎ」はすでに既成現実で、これを撤回して、人類の総人口は、いまから2万年ほど前の、百万人か五十万人程度に縮小せねばならないという話にはならないのでしょうか? 既存の医療の進歩や、技術による食料生産や、様々な製品の製造は、これらを認めて是とし、これに対する申し訳として、フロンの発生を幾分減らすとか、有害物質の発生と拡散を規制するとか、極めて緩やかな方法でしか、環境快復の処置を執らない現状を暗黙に肯定して、結局、築き上げた、現人類の文明社会が、もし、過去のバランスを理想とする論理からすれば、存続していることがおかしいという発想にはならないのかということです。 人類の数はともかく多すぎ、現在も増加途上にあるので、これを徹底的合理的解決するには、例えば、確率的に作用する、致命的な不妊薬品を人工衛星などから、地球の全域にばらまき、何も人間が継続的に介入しなくとも、人口が、年々、決定的に減少して行き、やがて100年後には、人類の総人口は、百万人になり、この段階で、薬物の効果は消えるというような、強行手段による、環境の「正常化」というようなものも、考えとしておかしくないのではないかとも思います。 わたしは、環境問題を解決したいのなら、このような方法も、オプションとして当然あり得、それを否定する根拠として、「現状態」を維持しても、また更に、技術の進化や精神の進化が、地球環境や他の生物を犠牲にして行われても構わないという「現時点での人類中心主義」発想を暫定的に据えても、それはそれで構わないのではないかとも思惟するのです。環境破壊を止めるというのなら、本当に有効な方法は、非常に悲惨で不愉快な方法しかないのではないかということは、或る意味、本当のことだとも言えるのです。 ☆☆ ☆ ☆ ☆☆
疫病が展開してしまうと対処法のなかった時代、疫病の兆候があれば、関係した人や家畜を、みな焼き殺し、建物を焼き落とし、廃棄するという残酷な方法しかなかった時代もあり、未熟児は、育たない運命にあるので、これを、捨ててしまうという残酷な慣習も、やむを得なかった時代もあったのです。これらの緊急事態での対応を考えれば、いまは、まさに緊急状態であり、地球の生物のこれ以上の滅亡・攪乱を防ぐには、人類に滅亡してもらうのが、一番だという考えもありえるのです。
しかし、「獲得した安楽さ、安全、健康、生活水準」こう言ったものは失いたくないというのが、人間のエゴイスムでしょう。このようなエゴイズムも、現に人間は、いま現在、認めているのだという事実を確認すべきだとも思います。 コンピュータを利用し、インターネットでページを検索している人たちは、自分たちが、いかに膨大な電子ネットワークを前提にしたシステムの上に立って、この利便性や快適性を手に入れているかということを、思い起こす必要があるとも考えます。このようなシステムを存続させ維持するのに必要な「人為的インフラ」が、どれだけ自然環境を破壊し、人為環境を構築して、地球の生態系も環境も、恣意的に操作し、それによって人間に都合のよい利用の仕方をしているのか、省みるべきでしょう。それは、「自然の摂理」などとは、とても言えないことでしょう。 しかし、なお、この現状の快適さや生活の豊かさや、進歩した技術の恩恵を我が手に維持したいのなら、その「エゴイズム」を直視し、認めるべきでしょう。「人間五十年」という自然的な或る段階の平均寿命が崩れた結果、このような環境破壊や人口爆発が起こっているのなら、「自然の摂理」を語るなら、まず、「人生五十年」状態を、人間の手で、もう一度再現すべきでしょう。しかし、それは「嫌だ」というのが、多くの人の心なら、「不老は不要」と言っている人たちは、七十歳か八十歳の寿命で、静かに死んで行ってくれれば、よいので、もし、更に先の未来へと進もうという計画そのものを、「自然の摂理」に反すると言うなら、現在生きている人類のほぼすべてが、「自然の摂理に反して、生存を獲得した」のだという事実を、冷静に考えるべきでしょう。 最初に述べたように、「不老技術」が開発され、実用化されれば、その技術の恩恵に与かろうと、必然的な競争が起こる可能性が非常に高いのです。人類の社会が、より、倫理的・精神的に向上した段階で、不老化技術が公開されるなら、問題は、また別の形になるかも知れませんが、不老化技術が実現するかどうかは別に、現人類文明は、やがて「破綻」するのです。それは、換言すれば、何かの調節点を、どこかの時点でか、具現せざるを得ないということです。無限の経済成長も、無限の技術革新もないのであり、いつかは、成長や革新の速度は低下し、やがて、ある準安定状態に達するでしょう。この準安定状態で、環境問題や人口問題などが解決していれば、宜なる事態ですが、そうでない場合は、なお別の高度な準安定状態が必要になるでしょう。 このような、進歩と展開と破壊と混乱、循環的準安定状態における、交互的な歴史過程の後で、何時か、何かの安定が訪れるでしょう。「不老技術」など考えなくとも、その段階で、すでに、人類の「社会ノモス」は変化していますし、倫理観も価値観も、世界観も変化しているでしょう。新しい「自然の摂理」の概念ができていることでしょう。 「不老技術」についても、現実的には多くの人が、それを望むでしょう。無論、写真を撮ると、悪魔に魂を奪われるとか、自動車は悪魔の乗り物だとか、医療は不自然で、祈りや信仰ですべての治療は可能だという人も過去にはいましたし(現在もいます。クリスチャン・サイエンスがそうです)、「不老技術」など要らないと言う人は、八十歳なり、自己の信じる「自然の寿命」で、この世を去れば、それでよいのです。 「より長い寿命」が可能となれば、長い寿命を選ぶか、選ばないかの選択が可能になるのです。肉体が長寿になっても、大脳や精神がそれに追いつけないで老化するという場合、記憶容量に問題があるなら、人間の記憶も外部記憶媒体に保存し、必要に応じて、記憶を再生利用すればよいでしょう。知識も同様でしょう。大脳細胞は死滅する一方だというなら、大脳細胞を活性化させ、再生を促し、シナプス結合を活性化する脳細胞技術を、研究すればよいことでしょう。 サイバーナイフがないとき、脳内部の腫瘍は、取り除くことができなかったのです。腫瘍を除去すれば治療できると、一つの技術では、可能性がありながら、それを実現する別の技術が未発達であったということが、過去、現実にあり、このような事態は、現在、なお幾らでもあることなのです。コンピュータの発展の歴史が、より小型で、精度が高く、高速で動作する基本回路素子の構築技術の研究の歴史でもあったというのは、知られていることでしょう。プログラム計算機のコンセプトは、バベッジやテューリングが、すでに二世紀前、理論的には考えたものです。しかし、LSIのような素子に思い至らなかったし、それを構成し設計し生産する技術も、社会基盤もなかったのです。 「人類のエゴイズム」が将来、「普遍生命への博愛主義」に代わるのか、代わらないのか、なお疑問でしょうが、現在すでに、エゴイズムを黙認の形で承認しているのが、いま生きてある人たちなのです。この過程は「進行形」であり、ある位置で止まっているのではないのです。社会は、自走しているとも言えるのです。それに暗黙のOKを、いま生きる人たちは出しているのです。環境破壊反対というなら、まず、自己の生命を絶ってでも、人口減少に寄与すべきでしょう。先進国の人口一人の存在維持は、発展途上国の十人、いや百人よりも、多くの環境破壊・自然破壊の要因となっているのです。「そんな自己の生命を絶つことなど、自然に反した行いなどできない」と言うのなら、「文明の自走」に積極的、消極的かは別に、畢竟、参加しているのだということになります。 「文明の自走」と共に、社会は変化し、展開し、世界観、価値観、倫理観、思想なども、社会や文明の変容と交互作用において、変化し、展開して行くでしょう。「恐ろしい未来」とも言えるでしょうが、すでに人類は十分恐ろしい経験をしてきたのですし、「恐ろしい過去」があったのであり、実は、いまこのときも、「恐ろしい現在」であるのです。 ☆☆ ☆ ☆ ☆☆
人間は、精神と肉体の特殊な統一体存在で、肉体の細胞には、「死の予定時間」が刻印されており、死に向かい、着々と準備し、秒読みしているのですが、「精神」は、肉体とは少し位相の異なる存在であるようであるというのが問題の要です。人間は、例えば、生物界の食物連鎖のピラミッドの頂点にいた訳ではなく、中間にいて、横滑り斜め上がりで、ピラミッドを見下ろす位置に立ったのです。最強の捕食動物も、死ねば、微生物や小型昆虫に溶かされ食べられ、分解されます。人の遺骸を土に葬るというのは、このような食物連鎖に人間をまた戻すことを意味していたのですが、火葬は、これまた、死後の遺骸を、食物連鎖のチェーンから外してしまいます。
なぜ、この「横滑り」が起こったのか。それは、人間の精神が自我を持ち、知性を持ったからだとも言えます。また精神とは、意識と自我と知性などから特徴付けられる何かだとも言えます。精神・意識もまた「年老い」「死の準備をする」というのも、観察されているというか、深層心理学では、「死への準備のタイマー」が一見あるようにも見えます。ユングは、「無意識は死を恐れていない。死の準備をしている」と述べ、「十分に老いる」ということの意味を述べました。フロイトは実証根拠が不明であるが、「死の本能」を考えました。精神もまた年老い、「死の予定時間」の起動プロセスがあるように見えるのです。 しかし、それは、意識や精神を支える物質的基盤としての肉体や大脳細胞や機構などの劣化、老化の反映ではないかとも考えられるのです。肉体の「死のタイマー」の影響が、その物質構造の上に立脚する精神にも、同じような「死の予定時間」を現出させているのではないかという可能性です。年と共に、「物忘れがひどくなる」というのは、精神が老いることなのか、脳細胞や神経回路の経年劣化、回路障害の増大ではないのか、という疑問の方が大きいと思えます。「退屈になり」「生きることに飽き」「新しいことが受け入れられなくなり」「記憶力が低下し」「過去の記憶の重さに自我が耐えられなくなる」とき、精神は老化しているのであり、一旦クリアし、内容を無にする必要があるようにも見えます。 しかし、身体の老化と不自由さの増大、脳細胞の回路的劣化と、細胞ネットワークの要素細胞の消滅による障害、そして社会的に「死を容認」し、「老化と死のプロセス」をライフサイクルとして、社会的・文化的に個人に強要するシステムの存在は、内的に、個人の精神が、死へ向かい老化し、死の準備を否応なく意識させられると共に、外的にも、役割において、「老人の役割」が社会や他者から求められ、「死の受容」を要請されているのだとも言えるのです。一見、精神にも備わっているように思える「老化と死の準備時計の起動」過程は、肉体細胞の老化と死の準備タイマー、そして社会的な老化と死の役割負荷の影響の元で構成されている可能性が大きいのです。 ユングが見出した、「無意識は死を恐れていない」とは、本来、精神は不死の性質を持つことの内的自覚の象徴的顕現ではないかとの可能性もあるのです。自我の経年経験蓄積には限度があるとしても、自我の構造再調整で、それは、無限に延長展開できる可能性が高いとも言えます。肉体の老化から解放され、新鮮な若い身体が復元され、脳細胞における経年劣化や回路障害も回復・再生され、また、心における、精神のバランスを乱す記憶の調整や感情の発現機構に修正が加えられるなら、九十歳を越えたが、なお身体は二十代のときと同様であり、知識や経験や思索の技術などは、九十年の蓄積を持つが、記憶力も、更に、新しい情報や事態への意識の関心も対応も、障害なく、昔日の若い頃と同様に機能する場合、「九十は寿命だ」というのは、どう納得が行くのでしょうか。 自我意識の「死の受容プロセス」については、キューブラ=ロスたちの研究が、受容プロセスに展開とパターン性を確認していますが、このプロセスは、「死の自我による自覚」に基づき、年齢に関係なく、解発されます。逆に言えば、「老衰過程での死の自覚と受容プロセス」は、この年齢に関係しない、普遍的な、自我の危機の救済プログラムの緩やかな展開である可能性が高いのです。つまり、精神においては、人は本来、「永遠に生きる存在」である可能があるということです。インマニュエル・カントは、人の精神が、解決に無限の時間が必要な課題を意識として持つことは、人の精神が「不死」で「永遠性」を持つことの証明だとも考えたのです。 人が五百年、千年あるいは、それ以上の年齢を生きることで生じる人口の増大の問題などは、それ以前に、伝統的ライフサイクルの崩壊あるいは根本的変革が前提になり、社会の「永遠精神」的構造の構成へと向けての全体的な変容過程が当然あるべきと考えるべきです。現在、人間は「人間のエゴイズム」に従い、生物界において、前例のない異常状態を作り出していますが、これも、準安定状態に達するはずであると述べたように、「不老社会の構成」へと向けての社会とノモス、個人の精神的自覚も、やがて、準安定状態を迎えるはずだとも言えるのです。 現在、人類は「不老社会」へと事実上、近づきつつあり、そのような状況が現実のものとなったのは、歴史上前例のないことであり、大きな当惑が、人々の心に起こっているとも言えます。自我が、集団において、社会において、九十を越えようと、その存在意味を社会や他者が認め、役割があるとき、精神は「生きることを健全」とするのです。対人的関係において孤立し、役割の無意味さを社会から宣言され、社会から「死を要請」される状態の老人にとっては、「自己の生存」を、「社会が否定している」のであり、「よりよく生きたいと願う思いさえ」、執着とか、年齢の自覚がないなどと決めつけられ否定されては、生存の意欲が消えるでしょう。 青年においても、何かの身体失調で、労働等が行えないとき、社会が、おまえは社会に無用なもので、早く死ねばよいのであり、おまえを生かすために、他人の労力が慈善として費やされ、おまえの存在は社会の害である、社会のためには、生命への執着を捨て、死ぬのが当然のことであり、これが世のなかの当然のあるべき姿であり、運命である、「自然の摂理である」などと言われていると、よほど強固な意志ある人であっても、「この世で生きている意味・価値」が自分にはなく、不要物であるから消えるのがよいという、悲観的思いに捕らわれるでしょう。また自殺か、死へと進む道を選ぶ可能性が高いです。 従って、年老いて社会の役に立たなくなれば、死んで、若い者にその場所を譲らねばならないというのは、老人への死に向けての圧力となっている訳で、精神的にも、「間もなく死ぬことになる」のである以上、死に逆らっても意味がないと考え、豊かな老後の人でも、寂しい老後の人でも、同じように、「死は自然の摂理だ」という考えにならざるを得ないでしょう。また、「死は避けがたい」という事実事態においては、死に対する恐怖を克服するには、「死は自然」であるとして、肯定するしかないでしょう。しかし、「死にたくない」というのが、おそらく人の本当の心であり、これを否定する、生物的な事実条件、つまり自己の身体、精神の明確な衰えの事実、社会的な条件、そして精神もまたすでに述べたような事情で、年老いるが故に、「死を運命と認めざるを得なかった」というのが、従来の事態なのでしょう。 しかし、「反老化技術」が生み出され、身体の老化だけではなく、精神の老化にも対処できるとなれば、また社会的な高齢者に対する「除外圧力」が低下ないし消え去れば、「死なねばならない理由も必然」もなくなります。「不老技術」は、肯定できることであり、何よりも、自己の生存について、より長く生きたい人には、選択の自由を保証することになるということが重要でしょう。超長寿化の実現した将来においては、何故、千歳まで生きることが可能なのに、九十歳が寿命だとか、「神や天の定めた運命」だなどと、昔の人は信じていたのか、時代的制約で、視野が限定されいたのは、やむをえなかったのだろうと人々は考えるでしょう。 「人は死なねばならない」という命題が妥当であるか否かは、状況的に、「人は死なざるを得ない」外的現実条件がある状況において、論じて、果たして意味があることなのだろうか、ということです。千年、一万年、いや、百万年を越えて、健全な身体と、劣化することなく明晰さを維持できる精神が実現できるとき、また過去の悔恨や、苦悩や、記憶の蓄積の重圧的錯綜効果が人の精神の均衡を阻害することを解決できるとき、この「現実的可能性」の存在において、はじめて、人の死の「運命性」の当否を判断するに必要な条件を人を得たと言えるでしょう。 |
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ HAGIAI SANCTAE
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ HAGIAI SANCTAE
|
Miranda et Marie RA. 2003:0214:1930 |
[TOP] [LIST] [HOME] [END] [THOUGHTS] [LITERARY] [MISCELLAN] [INFOR]![]()