|
Sein und Seiendes

『存在と存在者−随想』

par Marie RA. S. et Noice
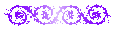
存在物が存在するということは驚異である。私は曾て宇宙の謎を三つ数えた。その第一は存在は何故存在するかという存在の根拠を尋ねる質問である。その第二はこの宇宙がこのような存在であること、このようなありようであることの根拠は何であるのかという問いである。そしてその第三は、この私が存在することの根拠、私がこのような現なる私であるとは何を意味するのかという問いである。
存在物が何故存在するのかという問いは、第一の問いに係わっている問いであると言うことになる。だがこの問いはまた、第三の問いともまた第二の問いとも関連する質問でもある。そもそも何故存在物は存在するのか。これに対する私の回答は、回答ともしそれを呼んでよいとするなら、回答であるとして、それは、私たちの意識・理性の水準においては、このような問いは、<謎>であり、私たちの水準の理性・知性においてはその合理的回答すなわち私たちの理性・知性に準じた回答は存在しないだろうという回答であった。
私たちはこの位置より開始して、質問の回答が、私たちの水準の意識・理性・知性よりも高次な理性・知性・意識の水準においては意識し得、確証し得るのではないかという仮説を立てた。これは例えば視覚という感覚を例に取れば、視覚を持たない者には視覚とは何かということはまったく了解も理解も経験もできない。視覚とは何であるかは視覚を備える時に始めて了解でき認識でき経験でき確証できることである。これとアナロギアにおいて、存在物の存在の根拠も、私たちが超理性あるいは超精神あるいは超意識と呼ぶ理性、精神、意識の水準においてはその回答が明瞭に認識でき経験でき納得でき確証できるものであると考えるのである。
この考えと、私たちの理性・意識・精神より高次で、存在物の存在の根拠を了解できる水準の理性・意識・精神を超理性・超精神・超意識と呼ぶという議論は、あくまで仮定の議論でしかない。それは私たちの期待し解答を希望するレベルの議論ではあっても、私たちの意識・精神・理性の水準において了解し得る問題では当然ながらないのである。存在物が何故存在するのか、このような私たちの理性の水準の疑問を超越した問いを、私たちは<超謎>と呼ぶこととした。私たちは私たちの理性・意識・精神の水準を越えるより高次の段階にある時にこの<超謎>の解答を得ることができるであろう。これが私たちの期待であり、またこれが<超謎>の定義でもある。存在物は何故存在するのか、この驚異の質問の答えを私たちは超謎と呼ぶことによって、問題を一見において解決あるいは回避したことになる。私たちの問題は、超理性・超意識・超精神が存在するかどうかという質問に置き換えられるのである。
この質問に対する解答は、私たちの水準、そして私たちとは異なる水準および質の意識・精神・理性への徹底的な反省によって、その解読のヴィジョンが展望し得るものであると私たちは仮定して、それに基づいて、試作としての議論である『 Liber Nacht 』の記述を試みそして現在の時点ではその試みは中途半端なところで停止している。(『 Liber Nacht 』はその記述の挫折の時点で、400字詰原稿用紙換算で400枚から500枚あり、これで考察のためのキー概念のイントロダクション的な概略説明でしかない。このエスキースは精神の問題を総合的に把握しようと試みているため、議論と考察が現象論レベルの存在の定義まで遡及して、確実なるもの・ことは何であるかという問いになってしまう。それは「構造として立ち昇ってある現象」であるということになるが、実はこの実在の定義を導入すること自体に大きな困難が存在するのであり、それが『 Liber Nacht 』の挫折の理由でもある)。
私たちの意識・精神・理性(これらを纏めて今後は簡略に「精神」と呼ぶことにする)を越える、質的に異なりより高次で、先に述べた<超謎>に対する解答の了解と確証の経験が可能な超精神の存在の可能性は、私たちを初めとして諸精神の現象の反省的思索による展望によって、認識の地平が切り拓かれるかも知れないと私たちは仮定し想定したのであるが、その仮定・想定が妥当であったか欠陥を含む不完全なものであったかの解答はまだ私たちには得られていない。そこで私たちの思索への試行はなお継続し得るのであり、継続するのである。……この<超謎>そして<超精神>をめぐる問題に対し何らかの展望のプログラムが存在し得るであろうか。プログラムとはつまり、どのような思索の方向を私たちは選べばよいのか、どのような論理の道筋がこの問題に対し適用できるのか、その見込みあるいは予想される展望図である。図式的に問題はどのように整理されるのか?
私たち及び私たち以外の精神の一般の現象、あるいはありよう、その本質態とは何であるのかという質問あるいは考究の主題がまず第一に考えられる。精神の現象一般の徹底的反省的思索、これがまず最初に要請されることである。そしてこの反省的思索を遂行するためには、そもそも<現象一般>とは何であるのか、私たちが思索し反省し考究するとは一体何を行う行為であるのか、この行為には何らかの筋道つまり論理が存在するのか、また論理が存在するならその論理とはどのようなものであるのかという疑問が湧き起こるのである。ここで私たちは問題が、西洋哲学で一般に言われる本質としての存在つまりエッセンティアの問いかけになったことに注意しなければならない。つまり思索とは本質的に何であるのか、論理とは本質的に何であるのか。何であるのか(ティ・エスティン?)という質問こそ、西洋形而上学の濫觴であるアリストテレスの形而上学で問われている本質探究に対する疑問の定式である。
本質を尋ねるのではなく現象としての<ありよう>を尋ねてみるのであると言ってみればどうであろうか。その場合は<現象>とは何であるのか、現象という現象は現象としていかなるあるありよう、物事の事態の状況・様態・位相であるのかという疑問が起こる。現象とはそもそも何を指す言葉で、現象とはいかなる様態・状況であるのだろうか。
インマニュエル・カントの主観的批判哲学では、主観が客観を認識しているのが現象のありようの真相・実態であった。カントは物自体を客観の彼方に想定し、我々が認識し経験する主観的現象とは物自体と私たちの主観の相互作用的な所産であるとの見解を示した。現象のありようはカントの見解では、物自体の属性・ありようではなくむしろ主観の側の構造の投影であるということになる。純粋客観つまり物自体は我々が出会う経験・現象からは導出できないのである。それは物自体の本質存在つまりエッセンティアが我々には不可知であるということを意味する。カントのカテゴリーは主観の構造に起因する現象経験の形付けのタイプであるいうことができる。アリストテレスのカテゴリーはそれに対し私たちの理性あるいは論理の構造的形付けのタイプの一覧表・整理表であるということができる。
アリストテレスは人間の認識はロゴスによるものであり、ロゴスつまり言葉あるいは論理が対象認識に対し形付けを行うと考えた。カントが考えたものは、ロゴスではなく主観が現象経験の全体を形付けるというものである。プラトンにとってはウーシア(本体)はエイドスとして万物の形象に形付けを行う永遠のイデアーであり、アリストテレスにとってはウーシアは具体的個別的な個人の意識つまり精神でありそのロゴスであった。ロゴスとは単に論理あるいは言葉であるだけではなく、生命から運動・本能を含む広範囲な精神の可能的広がりの機能であった。
プラトンは存在者をイデアーと素材であるヒューレーに分割したのであるが、アリストテレスは古代の知者の考えていた立ち昇る存在としてのピュシスつまり自然の存在の全体性の再現をもう一度もくろんだのであり、アリストテレスの個物・個体とはピュシスの顕現であり、エイドスとヒューレーの分割されない統合体であったのである。これらのかなりに散乱した展望においてキーワードとなるのは、ロゴス、イデアー、ヒューレー、ピュシス、スブスタンティア(実体)、主観などである。ロゴスとは何なのか、主観とは何なのか、これらの疑問がカントそしてアリストテレスの哲学の展望の理解のキーワードであることは間違いないことである。
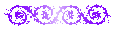
現象とはピュシスであるのか、プラトン流にドクサ(臆見)であるのか、主観と客観の相互作用的合成物であるのか、あるいはこれがヘーゲルの考えであるが、客観である主観である絶対精神の部分テーシスであるのか。アリストテレスが考えるように現象とは古代の知者が語るように立ち昇るものであるとするならば、それは一切の存在物の根源事象であり、一切の前提である。ロゴスもまたピュシスとして立ち昇っているのであり、立ち昇るもののなかの一者である。現象をプラトンが考えるようにドクサとすれば、イデアーへの無限の接近としてエピステーメー(真知)の存在が当然考えられる。エピステーメーは現象的には不可知となる。エピステーメーあるいはイデアーは洞窟の比喩に語られているように私たちにとってはその影だけが認識・経験可能なものとなる。
ここで認識の審級、あるいは真理のランクというものが導出されるのである。カントの考えにより現象を純粋客観に対する生命の枠付けつまり主観構造による具現化とすれば、合成実体としての現象あるいは主観の経験は、それ自身で一つの真理となる。カントの考えでは客観と主観の恣意的な分離は不可能であり、存在するものは実は主観の形付けを行われた物自体の合成実体ということになる。この合成実体の彼岸に物自体の認識可能性・経験可能性を想定することは錯誤であるということになる。主観と客観は対構造としてのみ存在し現象し得るのである。
ヘーゲルの考える絶対精神の部分的テーシスあるいは部分的顕現としての現象という概念は、プラトン流の真理の審級性を導入していることになる。プラトンにおいては極限の秘跡はエピステーメーの存在でありイデアーの存在であり、現象を越えた位置に構想される純粋ウーシアつまり真実の隠されたスブスタンティアである。ヘーゲルにおいてはこの秘跡が時間において自己実現をして自己展開してその秘密を顕現する過程へと進んでいるとされる。完成の未来へ向けて絶対精神が現象の弁証法を反復しているのが歴史であり、現象の真理の審級は認められるが、最終真理は秘跡ではない。それは、このあれこれの現象を通じて弁証法的に、と言うことは部分テーシスの自己矛盾と部分的総合を反復して歴史のテロス(目的)として構想されるのであり、この構想において一切の現象つまり部分テーシスがそれぞれの位置と審級を与えられるのであり、人間の自我も精神も意識も多様な認識も、ロゴスとして知られる論理の構造次序もすべてが弁証法的に構想されるテロスの光の下でそのしかるべき位置を与えられるのである。
シェリングは絶対精神の部分テーシスとしてのヘーゲルによる自我の規定を否定し、自我つまり主体的精神反省意識の自由意志を主張した。自由自我は既在としての諸現象の厚いヴェールの底に輝く星であるが、絶対精神の部分テーシスではなく、逆に絶対精神こそはこの自由自我の既在の諸現象の様態に対する一つの解釈・一つの展望に過ぎないのである。弁証法的運動とは自由自我にとってそれ自らが自己を展開して行く一つの道筋であるのであり、ヘーゲル流弁証法の論理が自由自我の運動を規定するのではなく、自由自我が論理を規定し展開しそれを自己展開の道具として駆使するのである。シェリングにとって現象は自由自我の前に顕在している解釈対象である。現象の総体は自由自我が無意識で構想したものであり、現象の解読を通じて自由自我は自己を回復して行くのである。シェリングの自由自我はしてみると隠された絶対者・神であったということになる。
フリードリッヒ・ニーチェは現象の一切は過去であると考えた。現象の総体はすでに完了しているのであり、自我つまり精神は現象総体を繰り返し追体験しているのである。一方でニーチェは精神は偉大な生命であり、生命とは躍動をその本態とし、生命に対する桎梏を克服しようとする実在的な力の現象形態であると考えた。生命に対する桎梏とは何のことか、ニーチェにとってはそれはある意味で西洋哲学の全体系であり、西洋文明の全文化的実体であった。精神のありようは文化が決定するのであり、この文化の総体は既に完了しているものであり、その意味で生命精神の文化に対する超越は永遠の反復であり永遠の課題であり未完結の作業となるのである。ニーテェにとって現象とは生命と文化の相互矛盾・相克のあいだに構成される精神の合成経験事実であった。この合成経験事実に対してはプラトン流の真理の審級は有効ではなかった。フリードリッヒ・ニーチェは生命としての精神を重視し、ロゴス・理性・論理に対し否定的な立場を取った。……だがニーチェの対立したロゴスとは、古代の知者のピュシスを称賛するロゴスではなくアリストテレスの合成現象を解読するための形付けの枠としての構造手順と形式であった。ニーチェはアリストテレスのカテゴリーに否を唱えたのであり、アリストテレス以来の西洋存在論・形而上学の論理構造に否を唱え、論理を超越する実体・ウーシアとして生命を構想したのである。
倫理は広い意味での論理に下属する審級性であり、ソクラテスの倫理はアテーナイの最高の文化的論理・ノモスを立ち昇る本源のウーシアとして認める<人間的>ピュシスのロゴスであった。ソクラテスは現象のエピステーメーとしての審級の解釈とウーシアとしての解読ではなく、人間的意味すなわち「いかにより良く生きるか」「たましいにいかなる気遣いを行うか」、プシューケーとしての人間の存在つまり現象の意味の探求に心を注いだ。ソクラテスは自然的事物のあいだにあってアルケーを求め尋ねることの無意味さを嘆いたと伝えられる。アルケーは水であるか火であるか気息であるか、まさにピュシスの現象を何らかの原理に帰着させようとする思索をソクラテスは回避した。「人は死すべき者である」というテーシスはギリシアの古代よりよく知られていた原理であった。ソクラテスは一見このテーシスに忠実に反復を行ったように見える。しかしソクラテスの行為の意味は畢竟、ソピストたち、そしてアルケーの探求者であった古代の知者たちの現象了解に対し、人間であること、人は人として現象つまりピュシスの前に立ち現れ、自らのピュシスなることを自覚するという基本的事実にそのいのちをかけて論証を行ったということである。
ソクラテスは神話を語り、神話でその教えを説き、現象を神話で解読した。神話とは立ち昇るものつまりピュシスに外ならない。ソクラテスは人間的社会的ノモスもまた広義のピュシスであることをその死において主張したのである。プラトンもまた神話を重視した。しかし彼はロゴスのゲームに魅惑されたのであり、ソピストたちとほぼ同じ地平において秘跡の真理の審級を導入した。ソクラテスにとっては生きること、死ぬこと、そのアテーナイ市民としての人生はかけがえのない真実であった。ソクラテスは論理的であったが、私が先に<超謎>と呼んだ問題群に対しては神話の解答を用意した。それらの問題群は畢竟人間の水準の精神にとっては論理の対象とはならず神話でしか表現がしようがなかったという認識がソクラテスにはあったのである。……弟子プラトンはそうは考えなかった。プラトンは神話を援用しつつ、真理に審級性を導入し、最高の真理を隠された秘跡エピステーメーつまりイデアーとした。プラトンにとってはこの世の現象の一切は臆見つまりエピステーメー(真知)に非ざるドクサであり、現象の本体はイデアー世界に起源を持つものとして、個別的現象の意味を臆見に貶めたのである。
先に述べた通りアリストテレスはプラトンの秘跡を排除して、現象をドクサとは見做さず、個別的現象こそがウーシアでありスブスタンティアであるとした。その個別的現象の研究の書たる「自然学」の後にアリストテレスの後世の弟子たちはなお一書を編集して置き、これを「自然学の後」(メタ・タ・ピュシカ)と呼んだ。アリストテレスは個別的現象が存在するという事実の背後に現象の存在の存在することの意味を尋ねたのであり、まことに存在物が存在する事実は驚異(タウマゼイン)であると述べた。
プラトンは論理をソピスト的に駆使したが、アリストテレスは論理を現象反省整理総合の主要な道具として意図的に使用したのである。論理に対するこのような反省的自覚的立場によってアリストテレスは自ら一書を著し此れを「カテゴリー論」とし、また自然物についての個別的現象の研究において彼は「自然学」(ピュシカ)を中心とする自然諸現象記述諸書を著し、個別的現象としての個人そして社会の秩序と構造の論理的解明として「ニコマコス倫理学」を著し、人間的ノモス的個別的現象としての社会制度としての文化を総合的記述するための予備資料収集および予備考察として「アテナイ人の国制」を著し、文化現象とりわけ文芸について「詩学」を著した。アリストテレスは現象は個別的に存在するとし、プラトンのように秘跡を説かなかったが、現象の存在の問題を「形而上学」において取り扱うことによって、現象の存在と存在物の存在において本質的存在(エッセンティア)と実在的存在(エクシステンティア)の区別を明瞭に行った。現象個別の重視と論理の駆使、そして存在の形而上学の構想を示すことによって、アリストテレスは以降の西洋存在論と形而上学の原型とその完成形態を提示したのである。
存在物あるいは存在が何故存在するのかという<超謎>への問いかけはこうして見ると幾つかの鍵となる概念・視点の持ち方によって幾つかのパターン的な解答の種類が導かれていることになる。西洋哲学の存在論のありようの全体を展望するなどということは不可能事であり、私もそんなことを意図している訳ではないが、プラトン、アリストテレスからカント、ヘーゲルまでの現象に対する解釈を以上のように概観してみると、現象を客観存在・スブスタンティアの部分テーシスあるいはドクサとする考え方と、それ自身においてピュシスでありアレーテイアーであるとする考え方の二つが大きく分けて存在することになる。
現象とは何か、現象の存在とは何か、現象はそれ自体実体であるピュシスであるのか、それとも精神あるいは客観あるいは秘跡としての謎のイデアーの部分テーシスであるのか、このような問いそのものが現象への本質存在論的な問いかけである。現象はエクシステンティアとしてまず認識者の現前に存在を立ち昇らせる。これをロゴスのフィルターで解釈する時、それはドクサであるとか全体存在の部分テーシスであるという解釈が出現して来るのである。現象が実在存在としてのピュシスであるという主張も実はロゴスにおいてそのような解釈を下しているのだということになる。
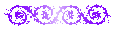
エドムンド・フッサールの現象学的現象解釈は、学つまりヴィッセンシャフトの厳密で確実な根拠を求めるという点よりその思索が開始されたことを考えれば、プラトンの秘跡としてのエピステーメーそしてドクサの真理審級と似た構造を持っていることになる。現象はドクサであり確実なヴィッセンシャフトの根底とはなり得ない。ではプラトンの言う真知つまりエピステーメーには人間は達することができるのか。フッサールの現象学において現象学的還元が二段になっていることがこのことの答えを示唆しているように思える。第一段の現象学的還元は、現象を一旦すべてドクサとして従来考えられていたその真理審級を廃棄することを意味する。判断を中止し、一切の現象に対し等距離で接する位置を措定することがこの第一段の還元の意味である。
フッサールは人間主観における現象のありようと位置付けを展望しようとした。だが現象はいかに還元しようとプラトンの意味でのエピステーメーになるわけではない。つまりフッサールの求めた厳密な学の基底としての客観的存在の原理は畢竟得られないのである。だがこのことはフッサールの思索の試行の出発点から予想されていたことであった。フッサールの第二段の還元、本質還元とは、言ってみればエピステーメーとしての現象、イデアーとしての現象のありようを構想する手順であったということになる。フッサールが結局達した結論は、現象学的還元は限りなく繰り返される、つまり永遠の現象還元であるということである。絶対的精神をエピステーメーの基底なしで構想して体系の上に人類史最高の思想体系を構築ししかもそれがウーシアを撃っていると確信したヘーゲルの錯覚は別として、フッサールの試行の行き着いたところは、プラトンのイデアーという名の秘跡を別の名称で呼ぶと言うだけのことであった。永遠に継続される現象学的還元とは結局、到達できない神話的真知への地上でのバベルの塔の構築作業にまさに外ならないからである。
こうして現象の学を名乗った二十世紀のフッサールの試みは一種のプラトンのパロディとなってしまった。この事実は逆に、いかに現象を現象それ自体として考察あるいは反省あるいは知的省察の対象とすることが困難であるかということの今世紀における実例である。このフッサールの最大の弟子と当時は見做され現象学の若き壮徒と見做されたハイデッガーはでは現象に対しどのような態度と思索・反省の視角を取ったのか。フッサールとハイデッガーが決定的な袂別をなす前にイギリスのエンサイクロペディア・ブリタニカより依頼された「現象学」の項目の説明を二人が共同で執筆していた当時のハイデッガーの書いた解説の部分が今日残っているが、それによればハイデッガーはフッサールの厳密な学の根底としての現象の追求という企図が哲学史的にはそれほどオリジナリティのある作業ではなく、また発想でもなかったことを認めつつも実に的確にフッサールの現象学の本質的な位置と意味を簡潔な明晰な文章で説明して見せている。
ハイデッガーは西洋哲学の歴史においては常に存在論がその中心主題としてあり、そして存在に対し西洋の偉大な哲学者はそれを論じるにおいて常に存在を認識し把握する人間の存在が密接に係わって来たことを指摘する。何故存在論の歴史において人間とは何者であるのかという問いが纏綿してやむことがないのか。ハイデッガーは自己に独自の考えをここで述べはしないが、だがこの存在論の歴史に人間の存在の本態への問いが纏綿していたという事実を指摘し、他方現象学とは、アリストテレス以来の形而上学でもヘーゲルの独断的主観論的客観主義でもなく、現に人間の前に立ち現れてある現象という事態を解読することによって世界の謎に肉薄しようとする学の路である限り、存在物の存在への問いかけにおける人間のありようの関与というこの事項は見逃すことのできない重要項であり、人間のありようと存在論が密接な関係を持つことよりして、人間論への徹底的な反省を通じて存在のありようその本態、現象という事態の真相へと肉薄して行くことこそが現象学の主要な課題に外ならず、これが現象学の持ち得る意味であると結論付ける。
フッサールは現象のなかに審級を持ちこむことによって真理のヒエラルキーを構想したのであり、結果的にそれはプラトンのエピステーメーを限りなく憧憬するものとなった。科学的認識、学問の厳密性の基礎付けというフッサールの動機からすればこのような結論はやむを得ないものであったろう。ハイデッガーはしかしその師を越える思索を展開した。ハイデッガーは西洋存在論つまり形而上学の歴史を画期的に再構成して描いて見せた。ハイデッガーの問いこそは「存在物は何故存在するのか」「何故存在が存在して非存在だけが宇宙にあるのではないのか」という疑問に直接に立ち向かうものであった。しかしハイデッガーのこの問題に対する答えは、畢竟、存在物の存在の現存在(人間)的根拠を開示する努力となった。人間つまりダーザインの場を通じて存在の概念は構成され造形されているのであるという答えは、画期的なものであるが、現象総体(そういうものがあるとするなら)の存在に対する根拠への問いかけとその答えはハイデッガーにはない。それは結局のところ<超謎>であるからであろうか。
ジャン・ポール・サルトルは現象を現象として受け止めそれとして解釈するという技術をハイデッガーから学び取った。人間とはいかなる存在者なのか、<物>とは何なのか、それらは現象それ自体への問いかけにおいて俎上に乗せられる質問である。ハイデッガーはその西洋存在論の歴史の再構成の論文であったはずの「存在と時間」の第一部において人間存在の現象論的分析を丹念に行った。サルトルはこの分析を更に敷延して、人間とは対象に対する者、エートル・プール・スワ Etre pour Soi であると考えた。人間とは存在者ではなく現象であり現象のあいだで精神の緊張関係において成立するある関係性の緊張のネットワークなのである。だから存在としての人間は実は関係性でしかなく、従って<無>であるということになる。現象それ自体について思索することを求めつつもサルトルは人間という存在者のありようつまり現象的構造分析に終始したと言える。……本質(エッセンティア)ではなく実在(エクシステンティア)こそが優先するのであるというサルトルの宣言をハイデッガーは嘲笑したが、ピュシスとしてのそれ自体が生成する有である現象を、本質と実存に分離するのは、プラトン・アリストテレス以来の西洋哲学の伝統的図式に外ならない。
中世哲学とキリスト教神学はイブン・ルシュドのアリストテレス解釈を出発点として<神>を最高の存在者、プラトンのイデアー、秘跡そしてアリストテレスの最終原因者、最高の個体存在であると解釈する立場を取ったが、このような論理においては存在物つまりレースの本質とその実在性は共に神からの流出あるいは恩寵としての付与ということになる。古代の素材、質料原因であるヒューレーはここではマテリアでありヒュポケイメノン(基体)としての本質も実在も持たない無性質無形の何ものでもない何かであり、これに神よりの付与である本質が与えられてそれが何であるかが定まり、更に神より存在(エッセ)が不断に付与されることによってそのものつまりレースは何かでありつつ(エッセンティア)、同時に実在として存在する(エクシステンティア)のである。
サルトルは自らの哲学を無神論的実存主義と唱えたが、人間つまりサルトルの言う実存の分析については犀利な着想が認められるものの、存在物の存在の根拠という哲学の中心的問題に対しては、サルトルの答えは、「ない」というのが正しいところである。サルトルにとっては生まれることも死ぬことも不条理であり、人間が死ぬことは戦慄ではなく、それを時間的に先取りすることによって現存在が頽落状態より救われる認識的契機という訳でもなく、それは自明の理に過ぎなかった。そうであればサルトルにとっては存在物の存在の根拠はその哲学的課題・主題とはならなかったことは自明である。存在が存在するというのは自明であるというのは素朴な無反省な臆見に外ならないのである。
モーリス・メルロ・ポンティはハイデッガーが言うところの世界内存在としての人間の現象的ありように犀利な洞察を示したが、存在論的な展望については私たちは浅学にして展望を持たない。カール・ヤスペルスのシフレ(暗号)としての神と限界状況の前に立つ人間実存という展望は、人間論と知識論における精緻な分析ではあるだろうが、存在の根拠自体はやはり神同様にシフレとなってしまうのである。これは私が存在の存在の謎を<超謎>と呼んだことに類似する事態である。ヤスペルスは人間の人間としてのありようをその生きる様態から逆照射して了解しようとした。これはソクラテスに似た立場であり、知識論的にはアリストテレスに類似する。ヤスペルスにおいては存在の問題は中世哲学におけるトマス・アクィナスの解釈と類似して、シフレとしての神からの暗号としての存在の付与あるいは存在の成立となるのであろう。
ここで整理を行うと、存在の根拠となる<超謎>を解読する手掛かりとして私たちは<現象>の存在の解明を志向したのであり、存在の謎の問題と現象了解の哲学史上における幾つかの思索の例を簡略に素描して概観して見たのであった。すでに述べた通り、現象をどのように哲学的思惟において取り扱うかについては、幾つかのパターンが認められる。その一つはドクサからエピステーメーへと上昇して行く真理の審級の階梯を現象に対し適用するもので、この考えの代表者はプラトンである。今一つは現象に対し真理の審級を要請せず、現象を立ち上るピュシスと把握する考え方でこれはアリストテレスの考えに見られるものである。
ロゴスや倫理、実体やアルケーの把握の仕方によって様々なヴァリエーションが生まれて来るのであるが、プラトンもアリストテレスも本質存在と現実存在の区別を立てていたことに変わりはない。マルティン・ハイデッガーはこのような二つの存在の区別を西洋形而上学の陥った陥穽であると見做し、哲学以前の古代の知者の思索、大いなるピュシスとしての存在の生成に二つの存在の分離する以前の統一体を見ようとした。ハイデッガーによれば現存在が時間について構成されるその仕様によって存在は異なる様相で顕現するはずであり、存在物の存在としての現れにおける様態にヴァリエーションを認めたのである。だがハイデッガーにしても畢竟根源的な問いである<超謎>の解答、すなわち存在物の存在の根拠を答えることはできなかった。<超謎>とは私たちの精神の水準で確証も認識も不能な質問であればこれは当然のことであると言ってもよい。
(だが私はハイデッガーが「存在と時間」第二部において存在とは何かを終に答え、存在の根拠を開示してくれているものと期待していたのであったが、この期待は満たされるはずもなかった。ハイデッガーが答えたのは、存在とは何かという問いの答えではなく、存在とはどのような場、どのような条件、どのような状況において顕現し姿を現すかというこの条件あるいは人間の存在との緊密な相関を解明しようと試みたに過ぎない。「語れぬものについては沈黙せねばならない」あるいは「言語の境界が認識の境界をつくる」というルートヴィッヒ・ヴィトゲンシュタイの言葉はしてみると、<超謎>が不可知のものであり、私たちの言語を一つの基盤とするロゴス・精神がそれ自身の精神的存在としての在り方故の限界を負った存在であり、私たちにはこの存在の謎に対する解答はないということを言語と論理の精緻な分析からして結論付けてみたものとも言えるのである)。
存在の根拠の謎に対する思索の第三のパターンと言えるのは、聖トマスの神学に典型的に見られるような、存在物の根拠を純粋至高存在とも言える神からの付与、恩寵、あるいは何らかの形の分与が存在物の存在の根拠であるとする思考のパターンである。プラトンは確かにイデアーを構想しこれを神とも呼びまたエピステーメーともし秘跡ともした。だがプラトンの思索のなかでは存在の根拠は驚嘆(タウマゼイン)があるだけで、イデアーが存在物の根源根拠であると主張している訳ではない。プラトンの真理の審級は現象の存在に対し下されたその秘跡のレベルである。現象は存在であるが、存在は必ずしも現象として顕現する訳ではない。
一方アリストテレスは第一原因というものを構想し、第一哲学すなわち存在の根拠を尋ねる思索の体系を構築しようとし、このような思索は西洋の伝統においてその編集された書名から転用されてメタピュシカー(形而上学)と呼ばれている。ではアリストテレス型の思索において存在の根拠はどのような答えとなるのであろうか。アリストテレスの答えを先取りすると、それは存在してあるものなべてピュシスであり自ずからにおいて存在を生成させ立ち昇るものであるということになるであろう。論理的にはアリストテレスは第一原因者・第一動因を考えてこれを神とも呼んでみた。だがアリストテレスにおけるイデアーは個物なのであり、古代の知者たちのように個物の存在の起源を大いなるピュシスの生成運動の過程に見ていたのである。……カテゴリーを提示した論理学者としてのアリストテレスと自然現象観察者および哲学者としてのアリストテレスそして形而上学者としてのアリストテレスはそれぞれに密接に関係しつつ異なる原理に立って思索を行っているように思える。(あるいはアリストテレスが思索を行う時に利用する様々な道具に違いがあると言った方が正確であろう)。
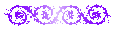
|
もっともこのような限定を行うと、例えばプラトンも同様に様々なアスペクトで思索を行い、様々な切り口から哲学的問題を考究しまた論議していることになる。実際、アリストテレスの場合には様々な著作のパターンとしてその思索の形態とアプローチの差異が現れるところが、プラトンにおいては修辞学的にあるいは美的文芸的に対話編としてその考究と思索が展開されており、我々はプラトンの対話編的著作を読んでみても、対話と議論のなかで様々に提出されている思索・展望・解釈の裡でどれがプラトン自身のものであるのか、結局のところ散乱して行くように見える対話編の論理の展開においてどの主張にプラトンが肩入れしているのかを見極めることが困難であり実際上不可能に近い。
古代ギリシアの著名な思索家たちの名を借りて行われる多様で錯綜したプラトンの対話編の議論の進行は、何か一つの究極の真理を論理のフィルターによって提示するというより、様々な解釈と論理の適用性のアスペクトの渦の中から、このような錯綜性を越える何かとして所謂処の真知つまりエピステーメーまたはアレーテイアーすなわちプラトンの言葉では永遠のイデアーが神話的に垣間見えるという形を取っているとしか考えようがないのである。このことはプラトンの対話編が美的文芸的作品であると同時に神話的・宗教的作品であるということをもまた意味していると私は思う。詩人ホメロスはその叙事詩の劈頭において詩神ムーサへの祈りを欠かさなかった【それは例えば「オデュッセイア」の冒頭の第一行において詩人がこのように歌い始めることからして明らかである。すなわち「オデッュセイア」の第一行は「アンドラ・モイ・エンネペ・ムーサ Andra moi ennepe Mousa.....」(あの男のことを、我に、語れよ、詩神(ムーサ)よ)という句から開始するのであり、この句は、結局の処、ホメロスが歌う叙事詩が実はムーサがホメロスの唇を仮に借りて述べ歌うものであるということを明示していることになる】。
こういった形式から逆に窺え得ることは、ホメロスのこの祈りは、詩神ムーサへの祈りを歌い、それによって我が詩の語りの成就を祈念するというよりも、詩神が彼ホメロスに憑依し彼ホメロスが詩神の地上での代理者として詩神の知る真実の物語り・言葉すなわちエポス・エペアを死すべき人間たちに伝えるという神話伝達行為の開始宣言であると言った方がよいということである。ホメロスはその朗唱の中で言葉を「翼ある言葉」すなわち「エペア・プテロエンタ」と呼ぶ。ホメロスの歌う言葉は神の言葉であり、彼の歌う物語り・叙事詩すなわちエペアは翼ある言葉そのものであり、それはミュートスつまり神話なのである。ホメロスはこのようにして「神話」の形で神々のみが熟知している秘密の真実を死すべき人間たちに伝達したのであり、これはまたホメロス以外の叙事詩詩人たち一般のあるべき存在のモードであり、これはホメロス風叙事詩詩人たちを通じてヘシオドスにまで伝えられているのであり、ギリシア抒情詩が個人の感情や思念や自然に対する思いを歌い始めた後にもなお神話伝達のもっとも伝統的な格式の高い方法としてギリシア社会に伝えられたのであり、プラトンの対話編とてもこのエペア・ミュートスの伝達伝統の延長線上に明らかに位置すると考えなければならないのである。
すなわちプラトンはその対話編において正にミュートス・神話を語ったのであり、その神話の語りはヘクサメトロンの叙事詩的韻律は持っていなかったとしても独自な韻文であったことに変わりはなく、例えばその対話編の一である『饗宴』においては、この作品に含まれるエロースすなわち愛神に対する様々な議論・意見・言説すなわちエペアが宴会の最初において出席者の一人であるエリュクシマコスによって提案された、エロースを讃美する言葉を我々全員で順次に述べてこの偉大なる神を称えようではないかという提案に沿って行われたものであるという記述上の事実からして、これが神に捧げられた言葉であり、実は神自らが神話の形でその姿をイデアーとして現すための枠形式であったということが明らかなのである。この対話編においてソクラテスは昔教えを受けたさる女神官すなわちディオティマから聞いた話として愛神エロースについてまったく神秘的で意外性のある真相を語るが、このホメロスにまで遡行し得るプラトンの対話編でのエペアの形式・内容それ自体がプラトンの洞窟の比喩におけるイデアーの開示の実例そのものではないのかと思えるのである。
畢竟プラトンは神話を語っているのであるが、だがプラトンはその師ソクラテスが偉大なる知者の系譜に連なるアルケーの探求者でありソピステースの一人であると同時にイク・エン・アトン以来最大の反省的倫理主義者であったのに比し、ソクラテスがその実践的な生死を通じて結局は否定し乗り越えた処のソピステースたちと同じ水準の思索・プロタゴラスの言う人間は万物の尺度であるというピュシスからもピュシスとしてのノモスからも独立した・人間=ロゴスあるソポスは、そのロゴスによって万物を思索・修辞学によって支配できるとする驕りの思索の水準に立って真知を知識的に論じた最大のソピステースなのである。ソクラテスはもっともソピステース的なソピステースとして思索を重ねた結果、ソピステースを否定しそれを乗り越えたが、弟子プラトンは再びソピステースの思索の水準に帰ってしまったのである。だがプラトンは最大のソピステースであったが同時にホメロス以来最大の神話伝授者でもあった。タレス、アナクシマンドロス、パルメニデス、ヘラクレイトス、エンペドクレスといった古代ギリシアにおいてアルケーを探求した偉大なる知者の系列の最後に位置するソクラテスの弟子に当たるプラトンは、最大のソピステースとしてソクラテスの境位から一歩後退する一方で、ロゴスとミュートスの関係の把握においてその師とは別の地平を切り拓いたのである。ソクラテスはロゴスを志向しアルケーを尋ねて自ら自然的実験を試み、ダイモーンとの精神・魂における交流を通じて「魂への気遣い」を意識化し、古代ギリシアにおいて最初に<プシューケー>という語に<幽霊>、<影>といった従来の意味と根柢的に異なる近代的な<人格的原理>としての意味を付与した。
|
| 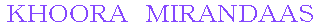
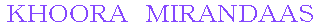
![]()
![]() 【Sophia Mirandae】 【LINK】 「存在と存在者−随想」
【Sophia Mirandae】 【LINK】 「存在と存在者−随想」![]()
![]() 【Sophia Mirandae】 【LINK】 「存在と存在者−用語集」
【Sophia Mirandae】 【LINK】 「存在と存在者−用語集」![]()
![]()
![]() 【Sophia Mirandae】 [TOP]
【Sophia Mirandae】 [TOP]![]()
![]()
![]() 【Sophia Mirandae】 [TOP]
【Sophia Mirandae】 [TOP]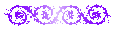
![]()