秋が過ぎ、冬の季節をむかえたある日、クネヒト博士は、散歩にでかけた。
すでに、雪が空に舞う時節で、博士がいつもの散歩道を歩いていると、顔に冷たいものが触れる。
葉を落とした林のなかで、空をみあげてみると、天のはるかな高みから、白い雪ひらが舞い降りて来るのが見えた。
赤い夕日のなか、それはキラキラと光りながら、地上へと、少しづつ降って来る。
山際の墓地に来ると、博士は、少し青みがかった色の墓石の前にたたずんだ。平たい石の墓石の上にも、雪は少しだが降りかかり、薄くヴェールを作っているように見えた。
(エレン)と博士は、心のなかでつぶやいた。(また、雪が降る季節が訪れたね)。
博士の妻だったエレンは、十年前、まだ六十歳であったが、突然倒れ、そのまま二度と帰らない人となっていたのである。
(エレン)と博士は、もう一度心のなかでつぶやき、墓所を見た。その時、不思議な光が、妻の墓石の上で、一瞬、閃いたように博士には見えた。
博士は、眼鏡の前をぬぐって、付いた雪を払い、もう一度亡き妻の墓石を眺めた。
空から、少しづつ白い雪が舞い降りてきて、妻の墓石の上に降りかかって行く。
見ていると、墓石の上の空中で、舞い散る雪のなかに、虹のような光のすじが見えた。
けれども、それはほんのわずかな時間のことで、後は、幾ら待っても、それ以上何も起こらない。
博士はしばらく墓石の前に立って、舞う雪を見ていた。(あれは、夕日が、雪の結晶に反射してできた虹なのかも知れない)博士は心のなかで思った。
暖かく暖房された家に帰ると、博士は、書斎へと行った。
机の前に座ると、読みかけの本の文字をしばらく博士は追っていた。しかし、なぜか本に集中できず、顔をあげると、博士は、机の上に飾られた妻の写真を見やった。
初夏の緑の光のなか、まだ若い頃の妻の顔が、博士に微笑をよこした。
写真のなか、妻は緑の眸[ひとみ]で、博士に問いかけるような顔をしていた。普段そんな風に見えたことはないのに、なぜか、そのとき、博士には、エレンがなにかを博士に求めているようにおもえた。
妻の胸には、白百合[しらゆり]をデザインした模様の飾りがあり、ドレスの膝の上には、藤の編み籠[あみかご]が置かれていた。籠のなかには、リンゴやナシなどの果物があり、また黄金色のパンがならんでいた。
籠[かご]にはリボンがついていて、そのリボンには文字が記されていた。
博士はそれらの文字が何と書いてあるのか知っていた。
《世界中のこどもたちにパンを!》
それは、ある団体のスローガンだった。世界の貧しい国には、飢えのため、毎日のパンさえ食べることのできない子供たちがいることを知ったエレンが、若い頃から熱心に活動していた慈善団体の標語だった。
(四十年前から、エレンは、世界のこどもにパンを、といっていた)
博士は、とおい記憶を振り返って、若い時代のことを思い出した。
エレンは長いあいだ、パンを世界の貧しい国のこどもたちに贈る活動にたずさわってきたが、その活動には終わりがないみたいだった。
二十年、三十年とたっても、貧しい国は存在し、飢えている子供たちの数は、増える一方だった。
十年前、妻が倒れたときも、エレンは、ある貧しい国の子供たちのため、パンや薬や衣類を送る準備をしていた。
(これで、こどもたちを助けることができる)倒れる前に、エレンがうれしそうに言っていた言葉が、耳にきこえてくるようにも思えた。
博士は、さびしそうな微笑をうかべると、そっと声にだしてつぶやいた。
「エレン、きみは去ってしまった……」
博士は、妻の写真の横にならべてある十数冊の本に目をやったあと、首を振った。
部屋は、しん、として、雪のように冷たい静寂に包まれていた。
翌朝、クネヒト博士が目覚めると、窓のそとは一面の銀世界になっていた。
二重扉をひらいて、玄関に立つと、博士は、降り積もった雪に白く隠された地面をみた。まだそれほど、雪は積もっていなかったので、博士は、門の前まで、歩いていった。
銀色の飾りをつけた樹の枝や、遠くの山々の白い姿。博士は、ふと、何かがキラキラ光るのをしった。
光は、足下ちかくにあるようだった。眼鏡をかけると、博士は地面を見てみた。足下から五、六メートルほど離れた地面に、不思議な光を反射させる、丸い雪の円があった。
博士は、昨日、妻の墓所でみた光を思い出し、夕べ、眠る前、かんがえていたことを思い出した。
白い雪に覆われた地面の上の光る円は、そのとき、虹色にきらめき、まるで博士をさそうように、一メートルほど、遠ざかっていった。
博士は、そのきらめく雪の円を追って、数歩を歩んだ。すると、地面の雪の光の円は、さらに、こちらにいらっしゃい、とでも言うように、さらに向こうへと、移動して行くのだった。
それは、普通の雪の地面にしか見えないこともあれば、ところどころが、キラリキラリと輝き点滅するようにも見え、また、虹の光が、銀色の雪の上で、舞っているようにも見えた。
博士は、不思議なことだと思いつつ、光る円に導かれて、雪のなかを歩いていった。まだ雪はそれほど積もっていなかったので、普段の靴でも、歩くことができた。
不思議な雪の光に導かれ、十分ほど歩いたとき、博士は、光がどこへ向かおうとしているのか気づいた。
それは、険しい山道を登って、聖母マリアの御堂がある山頂に通じる道だった。
光は、切り立った崖を左に見る、細い道へと博士を導いた。
博士は、マリア様の御堂のある、遙かな高い山の上をみあげて見た。
雪が青く晴れた空から、静かに降ってきた。あたりが、雪の結晶の光の反射によるのか、銀色のかがやきで満たされた。それは山頂あたりから、遙か下の博士を照らし出すように放射される光のようだった。
銀色のきらめきが周囲をおおった。虹色の透明な帯が、くるくる回りながら、博士を囲み、ある〈方向〉へと博士を導いているように思えた。
博士は、地面を見て、あの雪の光の輪が、道を左にそれて、博士を導くのを知った。
その方向に数歩、歩みをすすめたとき、クネヒト博士の足は止まった。
(あと数歩……)
博士は、あえぐようにこころの中でつぶやいた。
あと数歩、その危険な崖ぎわの地面を進むと、その先には、なにもなかった。
博士は、自分が切り立った崖の端に立っていることを思い出した。地面の雪の光の輪が示す先には、何もない空間があった。
崖は、数十メートルの高さがあった。遙か下には、麓[ふもと]の町から、食料や郵便などを運んで来る車両が走る狭い道がある。
あと、一メートルも進んでいたら、博士は崖から転落したはずなのだ。
博士は、胸がはげしく動悸するのを感じた。
(いや……これは?)
博士は、息が乱れ、恐ろしさに全身がつかまれるように思えた。心臓が苦しくなった。
頭のなかに靄[もや]がかかるような気がし、博士は、切り立った崖の向こうの空間を見つめた。
何もない空中に、星のように、雪の結晶がきらめいていた。そして、あざやかな緑の宝石の色の草が茂り、白い花が咲いているのが、かすかに見えた。
虹色の透明な膜[まく]を通して、その向こうの花園が見えた。
「エレン!」
宙に浮いた、まぼろしの花園のなかに、エレンの姿が見えた。三十年以上前の、まだ若い頃の妻の姿があった。
エレンは、いつも博士が妻を思い出すたびにそうであるように、パン籠[かご]を手に持っていた。パン籠のなかには、七色の不思議な果物と、そして金色のバターの色でかがやくパンの束があった。
(夢? まぼろし?)
美しいエレンの身体は透き通っていて、その身体を通して、背後の白い花――〈百合の花〉が見えた。
エレンは、パン籠を左腕に抱え、右手を博士の方に差し出した。
博士は数歩、後ろにさがった。すると、宙に浮かぶエレンと花園は、透明な空に溶け込むように、姿が薄れ、代わりに銀色の雪の結晶がヴェールのように舞うのが見えた。
クネヒト博士は、どうやって崖のそばから自分の家に帰ってきたのかおぼえていなかった。ただ気づいたとき、博士は自宅の門の前に立って、冷たい空気に、白い息をはきだし、あえいでいた。
食事を作ったり、部屋の掃除に来てもらっている近所のヘルツリープ夫人が、心配げに尋ねたが、博士には、その声も聞こえなかった。
博士は書斎に入ると、妻の写真の飾られた机にむかって座った。
ながいあいだ、写真を見つめていると、ようやく呼吸もおさまり、こころが落ち着いた。
博士は、そのとき、妻の写真の横にならべておいていた本の背表紙が目にはいった。
『十分に生きた人は死をおそれない』
『魂は永遠のいのちを知っている』
………………
それは、臨床心理学者として、また晩年は思想家として高名であったクネヒト博士が、人間にとって、《生きること》、《死ぬこと》とは何かという、永遠の問いに対し、世の人の疑問に答えようとして著した本の数々だった。
博士は、ふるえる手で、そのなかの一冊を取り出し、ページを開いた。
そこには、不治の病にかかり、死をまえにした人と、博士が交わした言葉の記録があった。
(最初は、死を否定していました)と死を前にした人は、博士に語った。
(けれども、本当に自分が死ぬと理解できたとき)
(……そうです。〈予告〉がおとずれます)
(それは、《幻[ヴィジョン]》の形で、私の前に現れました……)
(ヨハン、きみは死んでゆくのだよ、とその〈霊のひと〉は言いました)
博士は、本を閉じた。
ふたたび、妻の写真に目をやると、博士は、確かめるようにつぶやいた。
「《幻視[ヴィジョン]》なのだね、エレン?」
写真のなかで、白い百合の花を胸に持った、亡き妻が、優しくほほえむように博士には思えた。
部屋に飾っていた聖母マリアの画の前でひざまずくと、博士は祈った。
そして、うめくように博士は言った。
「私は準備ができていなかった。私は、こころの準備が……」
窓の外では、ふたたび降り出した雪が、白い華[はな]を宙に舞わせていた。
はっと、博士は、誰かの呼び声を聞いたような気がして、目覚めた。
そこは自分の寝室で、灯りの消えた部屋のなかは暗かった。
ただ、窓の外から、白い雪の光が、部屋に射し込んでいた。
(カール・クネヒト博士)
誰かが、自分を呼ぶ声を耳にして、博士は暗闇のなか、声の方向を向いた。
そこにエレンが立っていた。はじめて博士が、妻に会ったときのような若々しい姿で。
博士は目をしばたいた。(……エレンではない)
一瞬、エレンに見えたのは、実は、もっと幼い、十二歳ぐらいの少女だった。金色の髪を持ち、青い眸[ひとみ]だった。
しかし、その少女の顔には、エレンの面影があった。いや、遙か遙かな昔に忘れていた、博士の母の若い頃の面影もあった。
不思議な少女は、微笑をうかべた。
そのとき、博士は、少女のまわりが、淡い虹色の光で満たされているのを知った。
(君は、どこから?……)言いかけて、博士は驚きに声をあげた。(ああ……!)
天井から白い雪の華が降ってきた。
見上げると、天井の羽目板はなく、そのまま星の輝く天が頭上にあった。
はるかな高みから、真っ白な雪の結晶の花が、無数に舞い降りてきていた。
(カール・ヨハネス・クネヒト博士)と少女は言った。
(死を、すべてが無となる、暗黒の穴とかんがえたとき、《死》は、ただ恐怖であり、意味のない《事実》となる……こう言ったのは誰でしたか?)
(……偉大なカール・ユングだ。そして私がユングの言葉を引用した……)
博士の声はふるえていた。
白い雪は、寝室の床に積もり、寝台の上にも積もり、あたり一面が、雪の白い結晶で光りかがやいた。
(ユングが語り、そして博士も、そう人々に語ったのでした)
博士は、相手が語るのを聞きながら、少女だと思っていた姿が、少年のようにも見えることに気が付いた。
それは少年の面影があった。博士には懐かしい、よく知っているはずの顔だった。しかし、博士には、それが誰に似ているのか分からなかった。
(死は、すべてが無意味になる、《暗黒の虚無の穴》ですか? クネヒト博士)
博士には、言葉がなかった。
ただ首を振っていた。その頬に涙が流れていた。
(死は無意味なものではない)
ながいあいだの沈黙のあと、博士はようやく言葉に出した。
ぱっと、虹の光が部屋中を満たした。
少女に見える不思議な存在は、まばゆい光に包まれた。その背中に透明な翼が幾枚も幾枚も、まるで、花が開くように広がるのを博士は見た。
そして、天から降って来るものは、雪ではなかった。寝室の床にも博士の横たわる寝台にも、数知れない白百合の花が開いていた。
(カール・クネヒト博士)と、はるかな空の上から声が響いた。
(あなたには、しなければならないことがあるはずです)
博士は、暗闇のなか、星の輝く天を見上げ、答えた。
(分かっています。もうすぐです……)
博士の視界は、涙にくもっていた。
「クネヒト博士、クネヒト博士!」とヘルツリープ夫人は叫んだ。
「何をしておられるのですか?」
二階の物置に入ったまま、なかなか出てこない博士を心配して、夫人が声をかけたのである。
「やっと見つけた」
博士はそう言いながら、何かを大事そうに両手に抱えて、階段を降りて来た。
博士の両手も上着の裾も、埃だらけだった。しかし、不思議なことに、博士が抱えているものには、ちり一つ付いていなかった。
「まあ、それは藤の籠[かご]ですね」
ヘルツリープ夫人の問いに、博士は無言でうなずいた。
「妻の形見の品物だよ」
「亡くなった奥様の?」
博士は再びうなづいて、ふと思い出したように言った。
「書斎の机の上に、大事な書類がある。今朝、清書して署名した」
「けれども、言葉でも伝えておこう」
「何でしょう、博士?」
ヘルツリープ夫人は、人の良さげな顔を不思議そうにして、たずねた。
「私が死んだあと」
「まあ、死ぬだなんて、縁起でもない」
「黙って聞いて。……私が死んだ後、残された財産をすべて《白百合協会》に譲る。……私の財産はささやかものだ。しかし、協会を通じて、それは、世界の飢えた人々を……飢えた子供たちを、わずかであっても、助けることができる」
「それは?」
博士は晴れやかな声で言った。
「それが、妻の……エレンの《希い》だった」
「私は、もう少し準備することがある」
クネヒト博士はそう言って、両手で、藤の籠を抱きかかえながら、その場に夫人を残して、歩み去った。
クネヒト博士がいつ家を出たのか、ヘルツリープ夫人も知らなかった。
幾日か前の夕暮れと同様、夕陽の光が、あたりを、赤く染めるなか、博士は、あの崖の前に立っていた。
右手には、山頂の聖母マリアの御堂へと続く険しい道が続いている。
博士は、両手でしっかりと妻の遺品を持ち、白い雪でおおわれた地面を静かに眺めやった。
雪の結晶がキラキラとかがやき、静かに降り始めた雪のなか、雪の表に、あわくあの虹色の光の輪があった。
博士は崖へと一歩進んだ。
雪の上の光の輪は、更に向こうへと進んだ。
博士は、懼れにふるえる、みずからの心を励ました。
雪の光の輪は、いま、何もない中空に浮かんでいた。博士はその光に向かい、迷うことなく歩みを進めた。
白い雪のなかに、緑の森が広がり、白百合の花の開く園に、エレンが――若々しい姿のエレンが立っていた。
博士はエレンに向かい、手にしたパン籠を差し出した。
夕食の時間が過ぎても、クネヒト博士は帰って来なかった。
何年も、博士のために、夕食を作って来たヘルツリープ夫人も、こんなことは始めてのことだった。また、今朝、博士が言っていた言葉も気にかかった。
夫人は、すぐ近くの自分の家に帰ると夫に、心配事を告げた。
まもなく、村の牧師と警官がやって来た。二人は、クネヒト博士の身体が、癌に蝕まれていることを、ひそかに主治医から聞かされていた。
二人は、クネヒト博士の書斎に入り、机の上に、〈遺言書〉が残されているのを見つけた。
その夜は、村の多くの人々が、遅くまで、博士の行方を探した。
翌朝、食料や雑貨を積んだ、何時ものトラックが、あの崖の下の道を登って来た。そのとき、運転手は、ふと金色の光が目を射るので、ブレーキを踏んだ。
あやうくスリップしかかったため、運転手は舌打ちして、金色の光は何だろうか、と辺りを見回した。
地面は白い雪でおおわれ、あたりは一面、銀色の世界だった。
崖近くの地面に、雪の白さのあいだで、何かが金色にかがやいていた。
運転手は車を降り、その金色の光へと近づいた。
それは、朝陽の光を受けてかがやいていたのか、褐色の毛皮のコートが、なかば雪に埋もれているのが、一部分、表に出ているのだと分かった。
クネヒト博士が日頃来ているコートだった。
村の牧師や警官、そしてヘルツリープ夫人も、夫と一緒に、崖の下の場所を訪れた。
人々は、銀色の清らかな雪の下から、クネヒト博士を掘り出した。博士の顔は、崖から落ちたにもかかわらず、損傷がなく、静かな威厳とともに、微笑を浮かべていた。
その両手は、黄金色のパンが詰まった、藤のパン籠を、しっかりと握りしめていた。
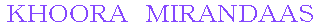
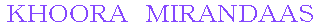
![]()
![]()
![]()