|
☆☆ ☆☆ ☆☆
ところで、聞く処によると、岩波文庫に英国ロマン派のワーズワースの日英対照の翻訳本が出ており、Penguin Booksに『ワーズワース詩集』が出ているそうです。岩波文庫のワーズワースの翻訳と云うと、田部氏の翻訳が長いこと唯一のものとしてあったのですが、対訳本が出ているとは知りませんでした。また、Penguinでペーパーバックの本が出ていると云うのもはじめて知りました。(Penguinには、各国語別の詩の翻訳アンソロジーは昔出ていましたが、個別的な詩人のアンソロジー詩集は出ていなかったはずです)。
ワーズワースは好きなのですが、わたしの大部分の趣味と同様に、まともに詩作品は読んでいないと云うのが実状です。好きな詩があれば、それで充分と云うのがわたしのスタンスですので、難しい詩は、読む気がしないと云うことです。(いま、ワーズワースの田部氏の訳本も、原文の本[ハードカヴァーの詩のアンソロジー本を持っているはずですが見つからない]も見当たらないのですが、とりあえず、岩波の対訳本は入手しました。とまれ、以下は、追想に基づく、断章的なワーズワース及び英国ロマン主義についての随想です)。
☆☆ ☆☆ ☆☆
さて、話が少し逸れるようですが、science fiction いわゆるSFと呼ばれる小説の分野について少し述べます。これが、どうワーズワース、また英国ロマン派に関係して行くのかは、話の展開において明らかになると思います。
そこで、SFと云う形式または作品群においては、その起源または系譜論と云うものが、稚拙ながら、或る程度詳細に論じられた時機があります。大体SFが持つとされる、「科学夢物語」の側面はフランスのジュール・ヴェルヌ Jule Verne[1828-1905]、「社会批評的側面」はイギリスのH・G・ウェルズ Herbert George Wells[1866-1946]に起源があると云われています。(社会批評はヴェルヌにも無論含まれていますが)。
しかしSFは色々な要素を持っています。一見して、考えるほどに単純ではないのです。ウェルズは、『タイムマシーン』で、プロレタリアートと資本家階級が極限まで階級分化したまま、その分化が固定され、種族的分化にまで至った未来像を描きました。これは社会批評ですが、文明批評にもなっている訳です。ヴェルヌは、科学の未来あるいは、科学と技術を通じて、人間には何が出来るかを構想したとも云えます。また科学技術の否定的利用と云う事態も想定していたとも云えます。これも広義の批判的視野・文明への反省に通じているとも云えます。
SFの起源は多様であると云うのは、「未知の世界・次元への人間の探求」の物語と云う位相を持つことで、ヴェルヌの作品は、この位相を表現しているとも云えます。ところで、これは「人間の知的好奇心」の存在を作品において具現化していると云うことになり、こういうアスペクトでSFの歴史的系譜を辿ると、無数の夢想談やホラ話や哲学的・思想的・宇宙論的想像力の具象化物語も系譜に含まれてきます。
(また、先のウェルズの社会批評的小説は、「タイムマシーン」で未来と云う未知の世界に行ったり、火星人の来襲の話で、科学的可能性がなきにしもない「未知の脅威」を描きつつ、実は、文明批評・文明風刺の視点も持っていたのです。この「社会批評・社会風刺」と云う観点からすると、例えば、痛烈な風刺批評家であるイギリスのスウィフト Jonathan Swift[1667-1745]の著した『ガリヴァー旅行記』も、疑似科学性・ホラ話性・社会文明批評性と云う点から、SFの源流とも見做されます。こういうタイプの風刺譚は紀元前から存在し、未知の世界に出かける空想譚も、神話と交じり合って、遥かな古代より存在します。SFの起源・系譜論には、宗教や神話なども遡源として考慮されることがあります。例えば、古代ギリシアのホメーロス Homeeros[c.B.C.10C.]の『オデュッセイアー』なども淵源と見做されます)。
「未知の世界」の探求が、未知の場所・未知の土地への探求と云う形を取り、形而下的な冒険活劇を取ると、これは、『ターザン』の原作者であるエドガー・ライス・バロウズ Edgar Rice Burroughs[1875-1950]の『火星のプリンセス』シリーズとなりますし、ライダー・ハガード Sir Henry Rider Haggard[1856-1925]の『洞窟の女王』などが、SFの先駆と云うことにもなります。(未知の世界・土地を、SFで、「テルラ・インコーグニタ Terra Incognita」と云います。冒険談では、アフリカの奥地とか南米の奥地、東洋の神秘の島だとか、ティベットの奥地などですが、SFでは、「海中」「地中」「空中」「月・惑星世界」「星辰世界」「異次元世界」など色々とあります。ヴェルヌは、『海底2万リーグ』で海中、『空の征服者ローヴァー』で空中、『地底旅行』で地中と云うテルラ・インコーグニタを描きました。南米の奥地に台地があり、そこに中生代白亜紀の生物相が保存されていると云う話はコナン・ドイル Sir Arthur Conan Doyle[1859-1930]の『失われた世界』で、気球に乗って月に到達する話はポーが書いています。またティベットの奥地に神秘の世界があると云うのは、ジェイムズ・ヒルトン James Hilton[1900-1954]の『シャングリ・ラ』ですが、このヴァリエーションは一杯あります。……また「未知の世界の探求」は、哲学的・思想的見地から構想されることがあり、現代のスペキュレーティヴSFの系統的起源は、イギリスの哲学者オラフ・ステイプルドンの壮大な銀河や時空の思想的小説にあるとも云えます)。
他方、SFは怪奇小説・推理小説の位相も備え、推理小説とは、隣接していると云うか、物語の形式としては、怪奇現象(非日常的現象)を、科学乃至疑似科学的手法で解明・説明して行くと云う形式を持っているのだとも云え、この時、SFの起源の系譜にアメリカのエドガー・アラン・ポー Edgar Allan Poe[1809-1849]の名前が出てくることになります。また、怪奇なもの、未知なもの、人間の知り得ない不可解なものと、ロマンスが組み合わされた様式がSFの一つの位相だと云う考えもあり、この時、SFは怪奇小説や幻想小説、そしてメアリー・シェリー Mary Shelleyの『フランケンシュタインの怪物』を系譜の起源に持つとも云われ、或いは、ゴシック・ノヴェル、特にその嚆矢とされる、イギリスのホレース・ウォルポール Horace Walpole[1717-1797]の『オトラント城綺譚』を系譜的起源に考えることがあります。
☆☆ ☆☆ ☆☆
さて、これはSFの起源の話ではないのです。
しかし、以上述べて来たなかで、SFの起源の一つの作品にメアリー・シェリーの『フランケンシュタインの怪物 Frankenstein』[1818]が出てくることには示唆する処があります。メアリー・シェリー Mary Wollstonecraft Shelley[1797-1851]は、英国ロマン派の詩人パーシー・シェリーの奥さんであり、彼女がこの作品を書くきっかけになったのは、同じく、英国ロマン派の詩人ロード・バイロン Lord Byron, George Gordon[1788-1824]のスイスの別荘(だったと思う)で、シェリー Percy Bysshe Shelley[1792-1822]、バイロン、彼女、そして後もう一人か二人いたと思うのですが(ドクター・ポリドリだったか)、一夜、怪奇小説を皆で書いてみようと云う話になり、彼女も作品を構想するのです。しかし、シェリーは、この後しばらくして、泳いでいて溺死し、夭折し、バイロンも、ギリシア独立戦争に参加して負傷を負い、結局その傷が元で、彼も死去します。そこで、彼女の作品だけが完成します。
メアリー・シェリーの『フランケンシュタインの怪物』の話は、フランケンシュタイン博士が、死体を材料に、みずからの科学技術の力で、新しい生命を生み出そうと試みる話ですが、博士は、雷(電気)のエネルギーを利用して、竟に、死体の継ぎ接ぎ(つぎはぎ)に生命を与えることに成功し、フランケンシュタインの造った「怪物」は生命を持つようになり、更に、人間としての知性や思索力・自我意識・反省力までも持つようになります。メアリーの作品の眼目は、この「怪物」が自己の与えられた存在の不条理に苦悩し、結局、悲劇のなかで死に、滅びて行くと云う処にあったと思います(こういうストーリーだったと思うのですが、記憶が違っているかも知れません)。
このテーマは、「人間は、〈自然の摂理〉に反して、〈苦悩する人間〉を勝手に造ってよいのかどうか」と云う点にあるはずです。いまで云うと、遺伝子工学がもたらす「生命倫理」の問題だとも云えるでしょう。……ところで、〈自然の摂理〉に反してと云いましたが、それは果たして〈自然の摂理に反して〉なのかどうかと云う問題もあります。キリスト教的世界観のなかにおいて、〈生命〉の人間による創造や、〈知性〉の人間による創造が、〈神の秩序・摂理〉に反すると云うことなのであって、メアリー・シェリーの構想は、確かに「悲劇」に終わる物語の構成なのですが、しかし、それはキリスト教の「人間の限界」を警告するために書かれたのかと云うと、どうもそうではないでしょう。
〈神の秩序・摂理〉における、中世的キリスト教調和宇宙秩序から、逸脱して、人間の科学技術や、創造・探求への意志を肯定して、未知の限りない探求、自然の奧に潜む〈神秘〉を探求し、人間がその知識を我がものとする時、その結果は、何か「薄気味悪い」何かではないのかと云う懸念を著したものだとも云えるのです。「怪物」の創造者、いわば、人間の力の万能性・全能性を探求したとも云える、フランケンシュタイン博士には、悲劇は起こっていないとも云えるからです。神の秩序を侵犯した者としては、中世的キリスト教秩序からは、フランケンシュタイン博士にこそ、神罰がくだり、彼が滅びの道を辿る、あるいは滅びると云うのが公式でしょう。しかし、そうはなっていないのです。
☆☆ ☆☆ ☆☆
メアリー・シェリーの『フランケンシュタインの怪物』と云う作品は、実は、英国ロマン主義文芸運動の或る「理念」を具現化していた作品だとも云えるのです。ロード・バイロンの長編詩に、〈神に挑戦〉しようとして、竟に、〈死〉に敗れるロマン派的英雄を歌ったものがあります。〈人間の意志の力・人間の構想する力〉は、〈神の秩序〉をも凌駕するのだ、と云うテーゼが前提としてあり、それを実践しようとした男が、竟に〈死〉に敗れると云う構成ですが、しかし、この作品は、人間の限界の警告や、神の超越性の確認の作品にはなっていなかったはずです。
まさに、〈挑戦する存在〉〈無限を希求し、自ら無限を具現しようとする存在〉……それこそが「人間」であると云う理念の表明であるとも云えるのです。「無限の自由・無限の可能性・無限の夢」を実現する「人間の意志と構想の力」……これが、ロード・バイロンの主張したものであり、この基本的テーゼが、実は、英国ロマン派の作品の根柢的理念だとも云えるのです。ドイツ・ロマン派の詩人たちにもそれと同等の理念・思想・世界観があったのですが、いま、それを考える準備はありません。
☆☆ ☆☆ ☆☆
ウィリアム・ワーズワース Willian Wordsworth[1770-1850]は英国ロマン主義詩人の中心的人物で、三人の夭折した天才的な英国ロマン派詩人(シェリー[1792-1822]、ロード・バイロン[1788-1824]、そしてジョン・キーツ John Keats[1795-1821])よりも、約二十年早く生まれ、彼らよりも三十年長く生きて、桂冠詩人の栄誉に燦やいた人物でした。(ワーズワースについては、フランス革命[1789-1799]が、その若き日の彼の思想や言動に大きな影響を及ぼしており、革命を讃美し、共和制政治の理想のために、過激な論陣を張ったこともあります。「無限の自由・無限の可能性・無限の夢」を実現する「人間の意志と構想の力」と云うのは、ロード・バイロンについて述べたのですが、若き日のワーズワースにも、このような「無限の自由」への希求と云う理念があったとも云えるでしょうし、それは外的に過激な形をその後取ることはなかったとしても、終生、彼の詩作活動の主題であったとも云えるのです)。
彼は処女詩集を、サミュエル・コールリッジ Samuel Taylor Coleridge[1772-1834]と共著で出版することからスタートし、イギリスの湖水地方と呼ばれる田園風景と自然、そして素朴な田舎に伝わる詩情を再現しようと試みたのです。それは、ずっと時代がくだって、ウィリアム・バトラー・イェイツ Willian Butler Yeats[1865-1939]が、若き日、詩的神秘主義直観で、アイルランドの古叙情詩・歌を蒐集し、再現を試み、「神話的世界の枠組み」のなかで、情熱的で神秘的な魔術的ヴィジョンを構成したのと似て、しかし、「自然に対する直接的な感応」に基づく「ヴィジョン」で生の叙情的交感を歌ったのだとも云えるのです。イェイツは、詩人のイメージにおいて、「失われた原故郷」を言葉によって意識的に構築しようとしたのに対し、ワーズワースにとって「原故郷」は、その自然との交感の歓喜・素朴な人々との交わりにおいて、「想起」されたものだったとも云えるのです。
ワーズワースの場合、「原記憶の想起」があったとも云えるのです。ワーズワースの心において、「自然の原風景的美」が、ヴィジョンとして立ち現れ、彼は、自覚的再想起において、それらの美のヴィジョン・聴覚的視覚的イメージの光の燦爛と、心の深みにおいて一体化したとも云え、原風景は、彼の心の外部にあると同時に、彼の心の内奥から湧き出る何かでもあったのです。ワーズワースの詩は、その言葉は、眼前に見る何かについてうたわれているものではなく、実は、心のなかの再想起像に対する、内的再構成としてあったのだと云うことが重要でしょう。それは、例えば、有名な『ダッフォディルの詩(黄水仙の詩)』が、水仙の黄金の光の燦やきを眼前にして詩人が詩句を連ねているように思えて、実は、「水仙のイマージュ」は、心の回想における、内面的な再想起イメージを言葉にしたのだと云うことからも云えるでしょう。
外部にある情景であって、しかし同時に実は内面の深層のイマージュであり、そのように自然の美・世界の謎の美しさを把握したと云うのが、英国ロマン派詩人のイメージ把握のありようなのです。シェリーにとって、雲雀の声が、自然の秘密を語る霊妙なメッセージであり、キーツにとって、夜啼鳥が、夜の闇に響くその玄妙な囀りと、姿の見えない、しかし心のヴィジョンとしてありありと視える、その姿において、自然と人間の奥義を伝えるメッセージであったように、ワーズワースにとっては、或いは、夕暮れに響く郭公の声、夜明けの森に響く郭公の声、その見えざる姿、春を告げる聖なる鳥・郭公の囀りが、自然と世界と人間の謎を伝えるメッセンジャーであり、その声と姿の意味は、彼の心の奥底で美の残像イメージとして或いは、再想起イメージとして、把握され、これをワーズワースは言葉に置き換えて行ったとも云えるのです。
☆☆ ☆☆ ☆☆
絶妙な言葉で、哀惜の思いを、美しい四季の情景と、花や樹や鳥や墓石の苔生す様などに託しうたった古典派のトーマス・グレイ Thomas Gray[1716-1771]の『墓畔の哀歌 Elegy Written in a Country Churchyard, 1751』には、自然描写と、叙情性と云うことでは、ワーズワースに負けない美しさと、言葉と共に展開して行く情景・心理の綾の見事さがあるのですが、グレイは、深い心の感動から、言葉を紡ぎだしていたのだとしても、それは、「言葉の高度に洗練された詩的技巧の宝石細工」とも云える何かで、グレイは、古典的均衡において、詩句やイメージを技術的に操作したと云うことが云えます。「自然の美しさと、そこに内在するリリシズム」をグレイは、よく知っていたのでしょうが、ワーズワースがそうしたように、それらを、心の内奥から湧き出るイマージュの展開・原風景の再想起としては、把握していなかったと云う点が、イギリス・ロマン主義を代表するワーズワースとグレイの自然の美と感動の表出において、根本的に異なっている何かなのです。
ワーズワースにとって、自分が、ヴィジョンとして再想起し、垣間見ているものはまさに自然の奥義であり、彼は「詩人」であり、彼の「心・魂」は「自然宇宙」と魔術的に交感し、「一つのものに融合している何か」であるのです。……このようなワーズワースの「詩的エクスタシー=万象との魂における交感・コレスポンダンス」は、しかし、「素朴な何か」と云うのとは、ほど遠いとも云えるのです。ワーズワースが、自然や人間の世界を、あたかも眼前にするかのように、美しい、豊かな、意味深い「広がり」においてうたう時、それは、詩人が、かくも美しく豊かな燦然たるイマージュを、心の外部に見出し、それを魂の反射板に映して、言葉を綴っているのではないと云うべきなのです。「黄水仙の燦然たる姿のイマージュ」は、まさに、「詩人の魂の深層において回想されたイマージュ」として現前するのです。「郭公の声」も、また「不遇の乙女ルーシー」も、黄水仙のイマージュ同様に、詩人の魂が、それを魔術的に回想する〈場〉において、叙情的に成立していると云うべきでしょう。
|
『ルーシー詩篇』より
Lucy
She dwelt among the untrodden ways
Beside the springs of Dove,
A Maid whom there were none to praise
And very few to love:
A violet by a mossy stone
Half hidden from the eye !
- Fair as a star, when only one
Is shining in the sky.
She lived unknown, and few could know
When Lucy ceased to be;
But she is in her grave, and, oh,
The difference to me !
彼女は、ダヴの泉のかたわら
人の訪ねぬ地に住んでいた、
讃える人なく
愛する人なき孤独の乙女。
人眼になかば隠れし
苔生す岩根に寄り添う菫!
― 空のなかにただ一つ
輝く星に似て美し。
人は彼女の日々を知らず、また知ることもなし
ルーシー逝きしいまはの時を。
乙女はいま奥津城に眠り、ああ
我ぞ詮すべもなし!
|

この詩を読む時、同時に尋ねるべきでしょう。「ルーシーとは、そもそも誰であるのか?」「ルーシーとは何であるのか?」ワーズワースは、何故「ルーシー」と云う名の乙女について、これらの幾つかの詩篇のヴァリエーションをうたったのだろうか。「何が〈わたし〉にとって〈違う〉(and, oh, the difference to me!)と云うのか?」……それは勿論、「ルーシーが生きているか、死んでいるのか、その〈大いなる違い〉」の意味だと考えられるでしょう。ワーズワースは、墓石の下に眠る「乙女」と、その「心を一つ」にして、交感しているのです。『私たちは七人よ We are Seven』 において、ワーズワースは、彼が対話している少女の存在の奥底に入り込み、心が魔術的に合一しているとも云えるのです。
☆☆ ☆☆ ☆☆
この『ルーシー』の「the difference」には別の解釈も可能なのです。何故「ルーシーとは誰で、何か?」と云う問いが起こるかと云うと、上の詩は十二行三連あるのですが、最後の第十二番目のラインを除くと、この詩は「三人称描写」の形式を持っています。「不遇の少女ルーシー」の話を「ダヴのコテッジ」(ワーズワースが、若き日に暮らした、湖水地方の住居)にあって誰かに聞いたワーズワースが、「ルーシー」の人生に詩的感興を覚え、それを詩にしたのだと云う解釈が妥当なのですが、しかし、それなら、何故、十二行目に、突如「to me」と云う表現が出てきて、一挙に「一人称」形式の姿を現すのか。つまり、「ルーシー」が、まったくワーズワースにとって話の上の伝聞の乙女だとすると、最後の「私にとっての difference」とは何かが分からなくなります。
これについては、この『ルーシー詩篇』が記された頃、ワーズワースは、終生共に暮らし、独身であった、彼の実の妹ドロシーに恋愛をしていて、その表面に表現できない感情を、「ルーシー」への詩の形で昇華したのだと云う説があります。これが本当のことなのかどうか、確認する術はないでしょうし、直接に論証した文章をわたしは読んだ訳ではないので、何とも言い難いことです。……ただ、ワーズワースは、フランス革命のさなか、フランスを訪問し、そこで或る女性と恋愛関係になり、娘キャロラインをもうけ、またイギリスで妹ドロシーと終生暮らすのですが、独身だったかと云うと、正式に妻メアリー・ハッチンスンと結婚しており、子供達も多数います。しかし、ワーズワースには、女性関係でもめ事があったと云う話はありませんから、彼の愛が深かったのか、心が豊かであったのか、家庭生活は安定していました。
☆☆ ☆☆ ☆☆
そして、このように世界・自然・他者とのあいだに、回想のイメージ、心の深層を一旦潜らせた後で再想起した時現れる、魂の交感の魔術的効果を、目の当たりにし、感動し、それが言葉となって変換され、湧き流れ出るような「存在」が、ワーズワースにおいて、「詩人」の謂いであると云うことになります。「わたしは〈詩人〉である」と云う明確な自覚をワーズワースは持っており、〈詩人〉であることは、自然のメッセージ・神々である自然と宇宙のメッセージを、魂と心にあって、回想する存在であると云うことを自覚しているのです。世界はワーズワースにとって、驚異と謎と神秘に満ちた至福の〈場〉であり、彼の魂こそは、この世界のなかに彷徨う郭公であり、燦然とかがやく黄水仙であり、山々、水、木々の碧、栗鼠や狐や小鳥などの小動物、そして空にかかる虹であり、風であり、沼地の青さであり霽れた空の美しい蒼でもあるのです。そして、このような〈詩人〉の生き方、生きるありようは、世の人のそれとは、恐らく異なるものなのです。
ワーズワースは、『霊魂不滅の歌 Intimations of Immortality』の最後のスタンツァ[XI]で、次のようにうたいます(山内久明訳:岩波文庫):
|
And O, ye Fountains, Meadows, Hills, and Groves,
Forebode not any severing of our loves !
Yet in my heart of hearts I feel your might;
I only have relinquished one delight
To live beneath your more habitual sway.
…………
泉よ、牧場よ、丘よ、森よ、
自然との愛が裂かれるなど不吉な予感は捨てよう。
私は心の奥底で自然の力を感ずる。
私は一つの歓びを失ったが
より恒常的な自然の支配のもとで生きる。
…………
|
原文で見る通り、「Forebode not any severing of our loves !」であり、「自然との愛」とは、「our loves」である。ワーズワースと自然(Nature と云う言葉は原文にはなく、具体的な、「泉・牧場・丘・森」が述べられている)が構成している「一体的宇宙の愛」は引き裂かれることはない。「心の奥底(in my heart of hearts)」で「汝らの力を我は感じる」。つまり、ワーズワースは、自然=泉・牧場・丘・森などを、自己の「外」に観察しているのではないのである。「自然」は単数ではなく、「ye」であり、「多様なる自然の数多くの愛の交感において、汝らの関係性の支配において、生きる〈ため〉、私は、かの幼年時代の榮光を失った。されど、榮光は至る処にあるではないか」。「かの《人の心 The Human HEART》」において。
|
Thanks to the human heart by which we live,
Thanks to its tenderness, its joys, and fears,
To me the meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tears.
|
|
生きるよすがとなる人の心のお蔭により、
人の心の優しさや、歓びや、恐怖のお蔭により、
私にはつつましく開く花でさえしばしば
涙よりも深く底知れぬ感動をもたらす。
|
ここで、ワーズワースは、霊妙なる自然との一体感、魂の魔術的汎心論的感応の宇宙をうたい挙げていると云えるのです。もっとも素朴に聞こえて、しかし決して素朴ではない、深い内面での交感あるいは、原型の共有における宇宙の魔術的把握とも云えるものでしょう。キーツは、もっと深遠に朦朧として神秘的にこの一体感応を歌い、シェリーは、雲雀が描くようなイマージュと意味の模様でこの一体感応を歌い、コールリッジは、戦慄性を帯びた、神秘的・黙示的な方法で、直裁に象徴の構成を行うのです(『クーブラカン』『クリスタベル姫』『老水夫行』等の作品において)。
ワーズワースは、誰よりも、自然との神秘的一体感応において、実質の重みある宇宙を感応表明しているとも云えるでしょう。そして、そのような神秘的感応存在者こそが、〈詩人〉Poieetees であり、「詩人の運命」についてワーズワースは自覚的であろうとするのです。『決意と自立 Resolution and Independence(蛭取る人)』で、ワーズワースが問いかけ、形象を構築し、自分自身を省察して、「決意」を表するのは、このような魂の深淵に通暁する「詩人の運命の自覚」においてのことだとも云えるのです。
| 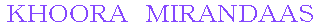
![]()
![]()
![]() [Libellus Litterarum] [TOP]
[Libellus Litterarum] [TOP]![]()
![]()
![]() [Libellus Litterarum] [TOP]
[Libellus Litterarum] [TOP]![]()